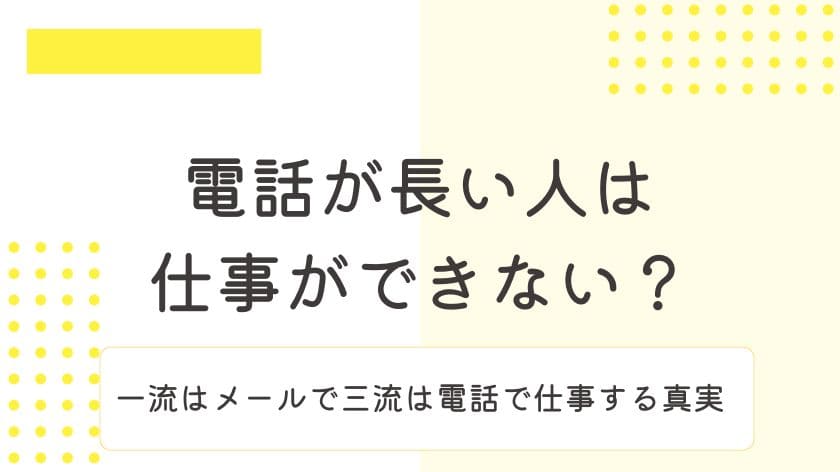あなたの職場に、仕事中にうざいと感じるほど電話が長い人、いますよね?
仕事中の電話が長い人は、基本的に、仕事ができないことが多いです。
そういう人は、メールで済むのに電話してきたり、忙しそうに電話ばかりしていて、さも仕事ができるという感じで振る舞っています。
なぜ電話が長い人は、仕事を頑張ってるように見えて、本当は仕事ができないのか?
その理由や特徴、さらには電話対応で失礼な人の特徴や電話が下手な人の特徴について、解説していきます。
さらに、すぐに電話してくる人の心理や、仕事で使える電話が長い人への対処法、話を上手に切る方法、電話が失礼な時間帯といったビジネスマナーまで詳しく解説します。
ただし、普通の生活では、女性の長電話は報告ではなく共感が目的なので、仕事ができないとかは関係ないです。
この記事を読んでもらえれば、電話で短く話すコツを身につけられて、電話が長い人とは仕事しないという判断ができるようになり、あなたの仕事の質をレベルアップできます。
- 電話が長い人が仕事ができないと言われる根本的な理由
- 周囲を困らせる長電話の心理と具体的な特徴
- 仕事の効率を上げるための長電話への実践的な対処法
- 自分が簡潔に話すための具体的なテクニック
「電話が長い人=仕事できない」は本当?その理由を解説
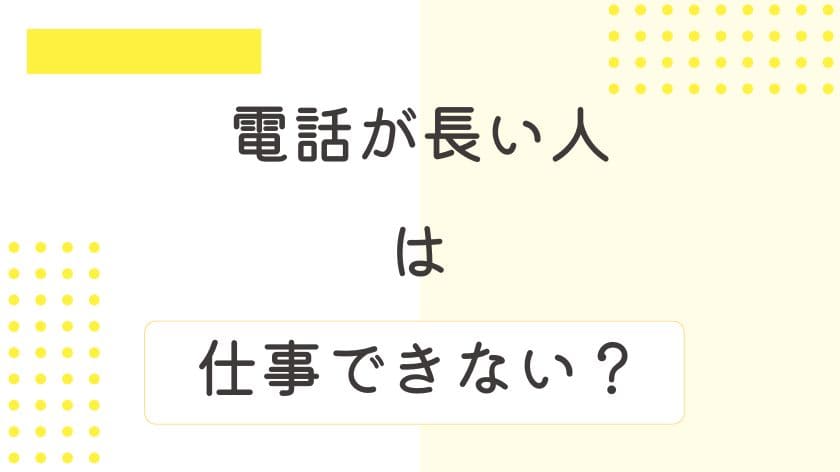
- 仕事中にうざいと感じる長い電話
- メールで済むのに仕事で電話する訳
- 電話が長い人の心理的な特徴とは
- すぐに電話してくる人の隠れた心理
- 電話をかけると失礼な時間帯とは?
- 電話対応で失礼な人の特徴は?
仕事中にうざいと感じる長い電話
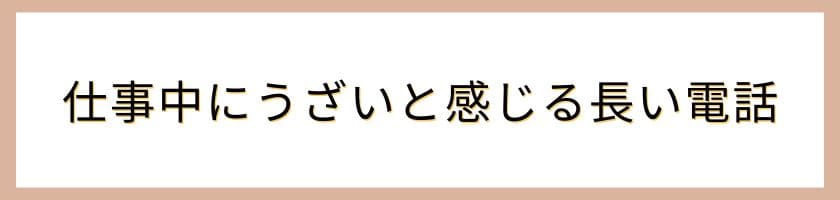
オフィスの静寂を破り、延々と続く同僚の電話。
業務に関係があるのかないのか分からない雑談が聞こえてくると、集中力がなくなって「うざい」と感じてしまうのは無理もありません。
本来3分で終わるはずの用件が30分にまで引き伸ばされると、聞いている側の業務効率まで低下させてしまいます。
多くのビジネスパーソンが経験するこの問題は、個人のストレスだけでなく、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす深刻な課題です。
特に、電話をしている本人は「コミュニケーションも仕事のうち」と捉え、自分は仕事熱心だと勘違いしているケースが少なくありません。
しかし、その実態は要領を得ない話し方で相手の時間を奪い、周囲に騒音をまき散らしているだけという場合がほとんどです。
このような状況は、健全な職場環境を維持する上で見過ごせない問題点と言えるでしょう。
メールで済むのに仕事で電話する訳
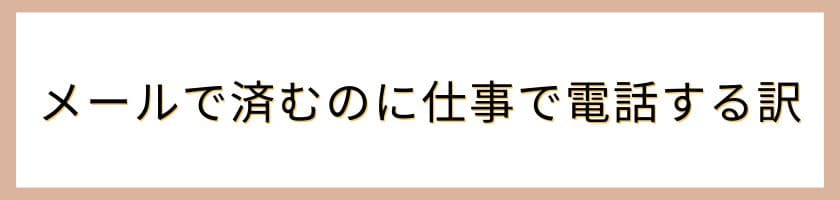
「この内容ならメールで十分なのに」と感じる用件で、わざわざ電話をかけてくる人がいます。
その背景には、いくつかの心理的な理由が隠されています。
最も大きな理由は、「言語化」という思考コストを相手に押し付けたいという心理です。
簡単に言うと、自分の考えをまとめるのが面倒なので、話しながら相手に整理してもらおうと思ってるんです。
メールを作成するには、自分の考えを整理し、相手に伝わるように文章を構成する必要があります。
このプロセスを面倒だと感じる人は、「とりあえず電話して話した方が早い」と考えがちです。
電話であれば、まとまらない話を相手に聞いてもらい、質問してもらうことで思考を整理できるため、自分は楽ができます。
つまり、相手の時間を中断させて、言語化の労力を肩代わりさせているのです。
また、パソコンを打っているよりも電話で話している方が「仕事をしている感」を得られるという、旧来の価値観を持っている人も少なくありません。
しかし、現代のビジネス環境において、このようなコミュニケーション方法は非効率の象徴と見なされがちです。
電話が長い人の心理的な特徴とは
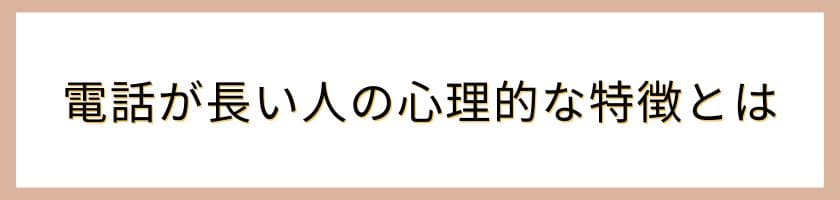
電話が長くなりがちな人には、共通する心理や特徴が見られます。これらを理解することで、その行動の背景が見えてきます。
主な心理的特徴は以下の通りです。
- 承認欲求が強い
電話で多くの情報を話したり、相手と長く繋がったりすることで、自分が「必要とされている」「頼られている」と感じたい心理が働いています。 - 孤独感を抱えている
誰かと繋がっている感覚を求めて、用件が終わっても雑談に移行し、会話を引き延ばそうとします。 - 話すことが目的化している
用件を伝えることよりも、会話そのものを楽しむことが目的になっています。暇つぶしやストレス解消の手段として電話を利用しているケースもあります。 - 自己顕示欲が強い
「自分はこんなに忙しい」「多くの問い合わせが来る」といった状況をアピールしたいという欲求の表れであることも考えられます。
これらの心理から、次のような行動特徴が現れます。
- 話の要点がまとまっておらず、同じことを何度も繰り返す
- 一つの用件が終わると、次々に関係のない話題を持ち出す
- 本題から脱線し、個人的な雑談が多くなる
- 相手の都合を考えず、自分のペースで話し続ける
これらの特徴を持つ人は、総じて相手の時間を尊重する意識が欠けており、コミュニケーションを客観的に見直す視点がありません。
すぐに電話してくる人の隠れた心理
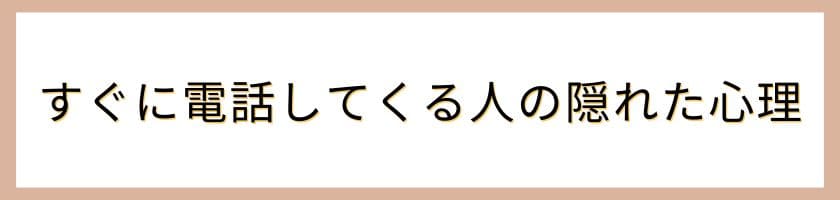
用件の大小にかかわらず、すぐに電話をかけてくる人にも特有の心理が働いています。
これは「電話が長い人」の心理と重なる部分もありますが、より「即時性」を求める点に特徴があります。
第一に、自分で考えて判断することへの不安感が挙げられます。
些細なことでも自分の判断に自信が持てず、電話で誰かに確認することで安心したいのです。
これは、責任を回避したいという心理の裏返しでもあります。
第二に、情報の共有方法が稚拙であるという問題があります。
例えば、社内の担当者であれば、本来はマニュアルや共有ドキュメントを整備して問い合わせを減らすべきです。
しかし、その努力を怠り、場当たり的な電話対応で済ませてしまうため、いつまでも電話が減りません。
クライアントからの電話が多い場合も同様で、製品やサービスの仕様に関する事前の説明が不十分である可能性が考えられます。
すぐに電話をかけてくる人は、相手の作業を中断させることへの配慮が欠けており、自分の不安解消や手間を省くことを優先していると言えるでしょう。
電話をかけると失礼な時間帯とは?
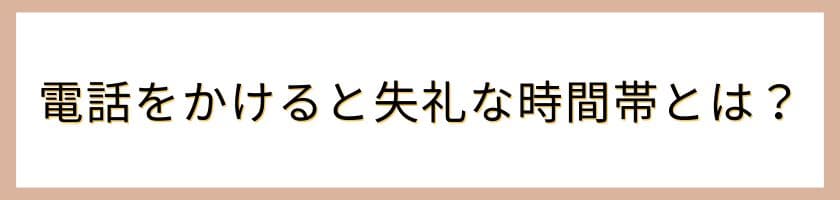
ビジネスにおいて、電話をかけるタイミングは相手への配慮を示す重要なマナーです。
相手の都合を考えずに電話をかける行為自体が、仕事のできない人の特徴と見なされることもあります。一般的に、以下の時間帯は電話を避けるべきだとされています。
| 避けるべき時間帯 | 理由 |
|---|---|
| 始業前・始業直後 | 朝礼やメールチェック、一日の業務準備で最も多忙な時間帯であるため |
| 昼休憩(12時~13時頃) | 食事や休憩で席を外している可能性が非常に高い |
| 終業間際・終業後 | 業務の整理や退勤準備で慌ただしい時間帯。緊急でない限り避けるのが賢明 |
| 深夜・早朝 | 言うまでもなくプライベートな時間であり、緊急時を除いて非常識とされる |
もちろん、緊急の要件や相手との関係性によっては例外もあります。
しかし、その場合でも「お忙しいところ恐れ入りますが」と一言添え、相手の都合を伺うのが最低限のマナーです。
こうした配慮ができない人は、相手の状況を想像する能力が低いと判断されても仕方ありません。
電話対応で失礼な人の特徴は?
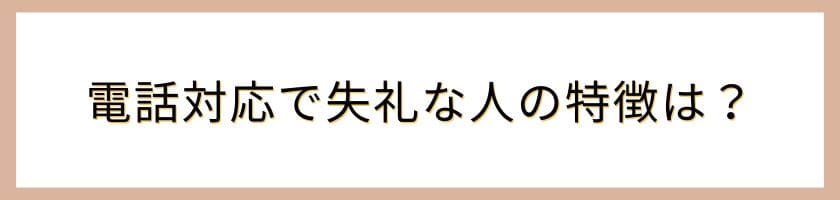
電話が長いだけでなく、電話応対そのものが失礼な人もいます。
本人は無自覚でも、相手に不快感を与え、会社の評判を落としかねません。
以下に挙げるのは、もっとも基本的な失礼な応対の例です。
- 「もしもし」と電話に出る
ビジネスシーンでは不適切です。「お電話ありがとうございます。株式会社〇〇の△△でございます」が基本です。 - 声が暗く、不機嫌に聞こえる
表情が見えない分、声のトーンは重要です。ワントーン明るい声を意識するだけで印象は大きく変わります。 - 早口でまくし立てる
相手に威圧感を与えるだけでなく、内容が聞き取れず、何度も聞き返す手間を発生させます。 - 語尾を伸ばす
「~でーす」「~ますぅ」といった話し方は、幼稚で馴れ馴れしい印象を与えます。 - 感謝の言葉がない
「お問い合わせいただき、ありがとうございます」といった一言があるかないかで、大きく印象が変わります。 - 相槌が「はいはい」などと雑
「なるほど」「へー」といった相槌も、相手を見下しているように聞こえる場合があり、注意が必要です。
文字で読むと、誰もが「こんなこと、おれはやってないよ」とか「非常識だよね」と思うはずです。
ところが、実際の電話では、本人の意識が電話から離れていれば離れているほど、こういう状況になっています。
わかってないのは、本人だけなんです。
例えば、もっと重要な案件でトラブルが起きてしまった時などに、小さいトラブルの報告があると、「はいはいはい」「あー、ちょっと忙しいんだけど」とか、「そんなの、そっちでうまくやって」と不機嫌に早口にまくしたてるはずです。
そもそも、そんな対応したことも忘れてしまってるのですが、電話先の相手は、「なんなんだ、こいつは」「うざい」「仕事できない奴」と思ってしまい、ずっと忘れません。
これらの特徴は、ビジネスマナーの基本が身についていないことの表れです。
「そんな事やってない!」と思われたとしても、もう一度、初心に戻って丁寧な対応を心がけることを覚えておいてください。
仕事ができない電話が長い人への対処法と改善策

- 仕事で使える電話が長い人への対処法
- 実践的な電話が長い人の話を切る方法
- 誰でもできる電話で短く話すコツ
- 電話が長い人とは仕事しないという選択
- 長電話の心理は女性特有の共感?
- 上司や客の長電話を「スマートに」切る高等テク
- 成果に繋がる「戦略的雑談」とは?営業電話の効率を最大化する技術
- 実は「話させる」が正解?会話の主導権を握る“聞き方”の技術
- 結論:やはり、ムダに電話が長い人は仕事ができない
仕事で使える電話が長い人への対処法
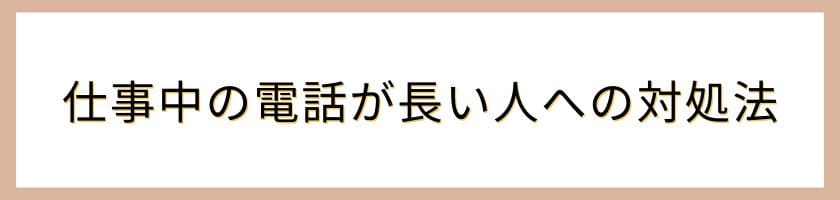
身の回りにいる電話が長い人に対して、ただ我慢しているだけでは状況は改善しません。
仕事の効率を守るために、いくつか実践的な対処法を試してみましょう。
いつも長電話になる人に対しては、電話の冒頭で「恐れ入りますが、〇分ほどしか時間が取れないのですが」と、あらかじめ持ち時間を伝えてしまう方法が有効です。
これにより、相手にも時間を意識させ、話を簡潔に進めるよう促すことができます。
また、話が脱線しそうになったら、「その件も大変興味深いのですが、まず〇〇の件から結論を出してもよろしいでしょうか?」と、こちらから軌道修正するのも一つの手です。
相手を尊重しつつ、会話の主導権を握ることがポイントになります。
最も重要なのは、毅然とした態度で「業務に支障が出る」という事実を伝えることです。
ただし、角が立たないように「あなたの時間を無駄にしないためにも、要点を絞りませんか」といった、相手を思いやる伝え方を工夫すると良いでしょう。
実践的な電話が長い人の話を切る方法
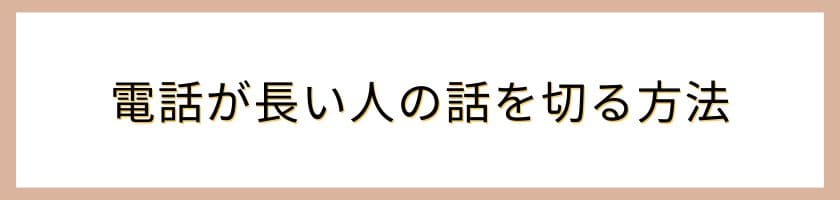
対処法を試しても話が終わらない場合、少し強引にでも電話を切る勇気が必要になる場面もあります。
相手との関係性を損なわずに話を切り上げるには、テクニックが必要です。
定番の方法は、「次の打ち合わせの時間が迫っておりますので、申し訳ありませんがこの辺で失礼いたします」と、外部要因を理由にすることです。
自分の都合ではなく、やむを得ない状況を伝えることで、相手も納得しやすくなります。
また、ある程度話が進んだ段階で、「承知いたしました。では、その件は〇〇という理解で進めさせていただきますね。結果は別途メールでご報告します」と、話をまとめて一方的にクローズしてしまうのも効果的です。
相手に反論の隙を与えず、かつ用件は確認したという形を作れます。
話を切る際の注意点
話を無理に切る際は、必ず最後に「本日はありがとうございました」「引き続きよろしくお願いいたします」といった丁寧な挨拶を忘れないようにしましょう。最後の印象が良ければ、多少強引な切り方でも悪い印象を和らげることができます
これらの方法は、相手によっては失礼だと感じられるリスクも伴います。
しかし、自分の貴重な業務時間を守るためには、時に必要なスキルと言えるでしょう。
誰でもできる電話で短く話すコツ
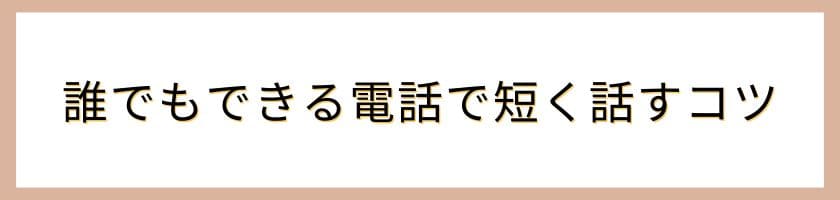
自分が「電話が長い人」にならないためにも、簡潔に話すコツをいつも心がけながら話すことは非常に重要です。
以下の点を意識するだけで、コミュニケーションの質は劇的に向上します。
- 結論から話す(PREP法)
結論(Point) ⇒ 理由(Reason) ⇒ 具体例(Example) ⇒ 結論(Point)の順番で話す方法です。話のゴールが最初から明確なため、相手は非常に理解しやすくなります - 電話する前に要点をメモする
伝えたいことを箇条書きにしておくだけで、話が脱線するのを防ぎ、漏れなく用件を伝えられます。5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識すると、より整理しやすくなります - 一つの文章を短くする
「~で、~なので、~ですが」と文章を繋げるのではなく、「~です。なぜなら~だからです。」のように、一文を短く区切ることを意識しましょう
PREP法とSDS法の比較
PREP法と似たフレームワークにSDS法があります。
プレゼンテーションや報告など、様々な場面で使い分けが可能です。
| フレームワーク | 構成 | 特徴・適した場面 |
|---|---|---|
| PREP法 | Point(結論) → Reason(理由) → Example(具体例) → Point(結論) | 説得力があり、ビジネス報告や提案に向いている |
| SDS法 | Summary(概要) → Details(詳細) → Summary(まとめ) | 全体像を掴みやすく、ニュースやスピーチなど短い時間での情報伝達に向いている |
どちらの方法も、一番初めに話す内容を伝えるということです。
一番初めに結論を伝えるのは、電話だけでなく、会議での発言や報告書の作成など、あらゆるビジネスコミュニケーションに応用できます。
電話が長い人とは仕事しないという選択
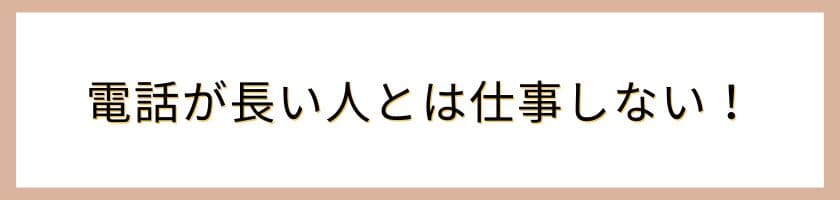
あらゆる対処法を尽くしても改善が見られない、あるいは関わることによる時間的損失が大きすぎると判断した場合、「その人とは電話で仕事をしない」という最終的な選択肢も視野に入れるべきです。
これは、特にフリーランスや経営者など、自身の生産性が直接収益に結びつく立場の人にとっては、合理的な判断と言えます。
具体的には、以下のようなルールを設けます。
- その相手との連絡は、原則としてメールやチャットのみに限定する。
- 電話があった場合は出ずに、後で「申し訳ありません、集中しておりました。ご用件をテキストでいただけますか?」と返す。
- どうしても会話が必要な場合は、アジェンダ(議題)を事前に提出してもらい、時間を区切ったWeb会議を設定する。
前述の通り、実業家の堀江貴文氏は「電話してくる人とは仕事するな」と公言しています。
これは、自分の時間を守り、パフォーマンスを最大化するための徹底した時間管理術です。
他人の時間に無頓着な人と付き合うことは、自分の人生の時間を無駄にすることに繋がります。
これは仕事だけではなく、プライベートでも同じことです。
その理由は、電話をかける人は自分がかけたい時にかけるのにたいして、電話を受ける人は、何をやっていたかに関係なく、強制的に電話がかかってくるからです。
なので電話は、かかってくる側にしたら、時間を奪うツールでしかないんです。
冷たいと思われるかもしれませんが、自分の成果と時間を守るためには、人間関係においてもシビアな判断が求められます。
長電話の心理は女性特有の共感?
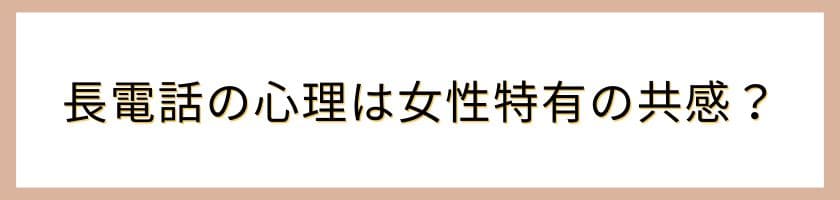
とはいえ、プライベートな会話において、長電話が好きな女性は多いです。
この背景には、コミュニケーションの目的の違いがあると言われています。
一般的に、男性の会話が「問題解決」や「情報伝達」を目的とすることが多いのに対し、女性の会話は「感情の共有」や「共感」を目的とすることが多い傾向だからです。
話すこと自体が目的であり、結論を出すことよりも、相手に「そうだよね」「わかるよ」と共感してもらうことで満足感を得るのです。
このため、話が様々な方向に広がりやすく、結果として長電話になりがちなんです。
ただし、これを「女性だから」と安易に結びつけ、ビジネスの場に持ち込むのは危険です。
ビジネスコミュニケーションの基本は、性別に関係なく「目的を明確にし、簡潔に情報を伝達すること」です。
共感を得たいという個人的な欲求が、業務の効率性を損なう長電話に繋がっているのであれば、それはプロフェッショナルな姿勢とは言えません。
多様なコミュニケーションスタイルを理解しつつも、ビジネスの場にふさわしい振る舞いをすることが求められます。
上司や客の長電話を「スマートに」切る高等テク

これまでの対処法は、主に同僚や部下を想定したものでした。
しかし、相手が役職の高い上司や、売上を左右する重要な取引先である場合、同じように「時間がないので」とは言えません。
下手に話を遮れば、自身の評価や会社の信用に傷がつくリスクさえあります。
そこで、相手との関係性を損なうことなく、かつ自分の時間を守るための、より高度でスマートな対処法を紹介します。
基本となる考え方は、「話をさえぎる」のではなく「相手のために、話を前に進めてまとめる」という姿勢です。
相手に「この人は仕事がデキるな」と思わせることで、会話の主導権を握ります。
具体的なテクニック3選
- 「要約+感謝」でクローズ
相手の話がある程度進んだら、「〇〇様、よく理解できました。つまり、今回のポイントは△△という認識でよろしいでしょうか?貴重なお時間をいただきありがとうございます。すぐに要点をまとめてメールでもお送りします」と、こちらから話をまとめることで、議論が終了したという雰囲気を作ります。感謝の言葉で締めくくるのがポイントです。 - 「次のアクション」を宣言して終了
相手からの指示や依頼が出たタイミングで、「承知いたしました。では、そのご指示に沿って、ただちに〇〇の資料作成に取り掛かります」と、即座に次の行動を宣言します。これにより、「話は終わり、これからは実務の時間」という流れを自然に作り出すことができます。 - 相手の時間を「気遣うフリ」
「〇〇部長、この後15時から部長が参加される会議の準備もおありかと存じますので、要点のみで失礼いたします」というように、相手のスケジュールを把握し、気遣う姿勢を見せることで、話を本題に集中させ、簡潔に進める大義名分を得る方法です。
これらの方法は、相手の立場を尊重しつつ、「私はあなたの時間を無駄にしませんし、聞いた内容を確実に実行します」という有能さを示すことにも繋がります。
ただ話を切るのではなく、相手からの信頼を得ながら時間をコントロールするという、ワンランク上の技術です。
成果に繋がる「戦略的雑談」とは?営業電話の効率を最大化する技術
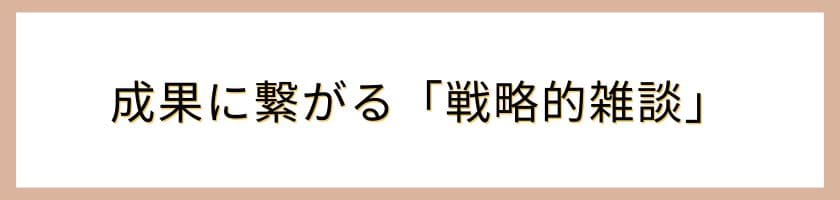
営業職やカスタマーサポートなど、電話でのコミュニケーションそのものが主要な業務である職種も少なくありません。
このような職種では、顧客との良好な関係を築く「ラポール形成」のための雑談が重要であり、ある程度の長電話は必要悪とさえ言えます。
しかし、問題は成果に繋がらない、ただの世間話で終わってしまうことです。
ここで重要になるのが「戦略的雑談」という考え方です。
これは、単なる時間つぶしではなく、「信頼関係の構築」「相手の情報収集」「本題へのスムーズな移行」といった明確な目的を持って行われる雑談を指します。
戦略的雑談から本題へ移行する流れ
- 準備段階:雑談のタネを仕込む
電話をかける前に、相手の企業のプレスリリースや業界ニュース、可能であればSNSなどから、話のきっかけとなる情報をリサーチしておきます。 - 冒頭:目的を持った雑談
「〇〇のニュース、拝見しました。素晴らしいご活躍ですね!」といった具体的な情報から入ることで、「ちゃんと自社に興味を持ってくれている」という好印象を与え、相手の警戒心を解きます。 - 移行段階:ブリッジフレーズで本題へ
雑談が温まってきたら、「そういえば、その〇〇の件で思い出しましたが、本日の本題である△△について、少しお時間をいただいてもよろしいでしょうか?」といった、関連性を持たせる「ブリッジ(橋渡し)」となる言葉を使い、自然に本題へと移行します。
以下の表は、非効率な雑談と戦略的な雑談の違いをまとめたものです。
| 項目 | 非効率な雑談(ただの長電話) | 戦略的雑談(成果に繋がる電話) |
|---|---|---|
| 目的 | 特になし。場を和ませる程度。 | 信頼構築、情報収集、本題への移行。 |
| 内容 | 天気の話、一般的な時事ニュースなど。 | 相手企業や業界に関連した、準備された話題。 |
| 結末 | 本題に入るタイミングを逃し、気まずくなる。 | ブリッジフレーズを使い、スムーズに商談へ移行。 |
ただ長いだけの電話と、成果を出すための電話は全くの別物です。
目的意識を持つことで、電話一本あたりの価値を最大化することが可能になります。
実は「話させる」が正解?会話の主導権を握る“聞き方”の技術
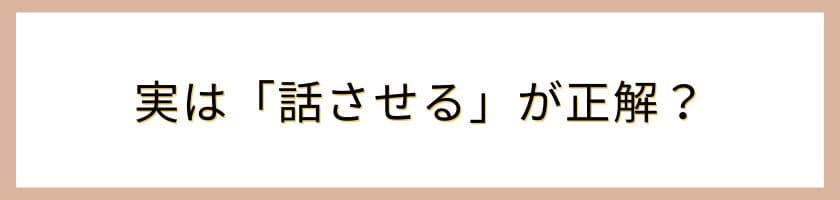
長電話を終わらせるには、自分が話して流れを断ち切るしかない、と思っていませんか?
実は、その逆のアプローチが極めて有効な場合があります。
それは、意図的に「聞き上手」に徹することで、相手に話をさせながら、最終的に会話をこちらがコントロールするという高等技術です。
これは「アクティブリスニング(積極的傾聴)」と呼ばれるコミュニケーションスキルの一環です。
ただ黙って聞くのではなく、能動的に関わることで、相手は「しっかり話を聞いてもらえた」という満足感を得て、こちらへの信頼感を高めます。
その結果、こちらの提案やまとめが通りやすくなるのです。
アクティブリスニングの基本要素
アクティブリスニングには、「相槌」「言い換え(パラフレーズ)」「要約」「質問」といった要素が含まれます。
これらを駆使することで、相手の話をただ聞くのではなく、整理し、導くことが可能になります。
具体的な方法は以下の通りです。
- まずは自由に話させる
会話の序盤では、相手の話を遮らずに聞きます。「なるほど」「そうなんですね」といった肯定的な相槌を打ち、相手に心地よく話せる環境を提供します。 - 「要約」で論点を明確にする
相手の話が一段落したタイミングで、「〇〇様、ありがとうございます。お話を伺っておりますと、現状の課題はAとBの2点で、特にBの解決を優先されたい、というご認識でよろしいでしょうか?」と、こちらが理解した内容を要約して確認します。これが会話の主導権を握る第一歩です。 - 「質問」で会話を絞り込む
要約で課題が明確になったら、次は具体的な質問で話を絞り込んでいきます。「では、そのBの課題について、具体的なご要望を伺ってもよろしいですか?」というように、開かれた質問から閉じた質問へと移行させ、議論を収束させていきます。
この技術を使えば、相手はたくさん話した満足感があるにもかかわらず、会話時間はむしろ短縮され、かつ議論の精度は高まります。
相手を無理に黙らせるのではなく、「話させて、まとめて、導く」という新しいアプローチを試してみてはいかがでしょうか。
結論:やはり、ムダに電話が長い人は仕事ができない
この記事では、電話が長い人がなぜ仕事ができないと見なされるのか、その理由から具体的な対処法までを解説してきました。
最後に、本記事の要点をまとめます。
- 電話が長い人は相手の時間を奪っている意識が低い
- 言語化のコストを相手に押し付けようとする心理が働く
- 承認欲求や孤独感が長電話の原因になることがある
- すぐに電話する人は自分で考えることを避けている可能性がある
- 始業直後や昼休み、終業間際の電話はマナー違反
- ビジネスで「もしもし」を使うのは失礼にあたる
- 対処法としてまず持ち時間を伝えるのが有効
- 次の予定を理由に話を切り上げる方法もある
- 自分が話す際は結論から話すPREP法を意識する
- 電話をかける前に要点をメモにまとめるのが効果的
- 改善が見られない相手とは仕事をしないという選択も必要
- 共感を求める心理が長電話に繋がることもある
- ビジネスでは目的を明確にした簡潔な会話が基本
- 電話のスキルはコミュニケーション能力全体の指標となる
- 効率的なコミュニケーションが職場全体の生産性を向上させる