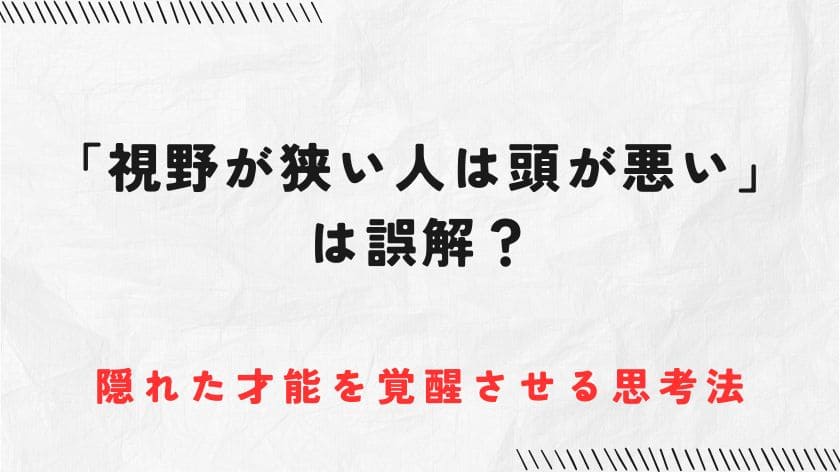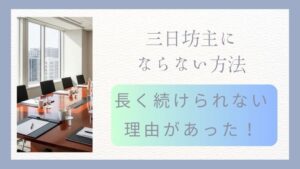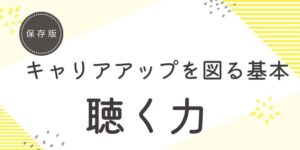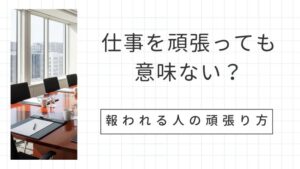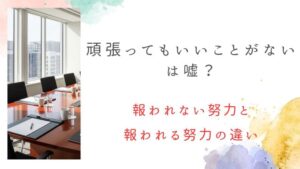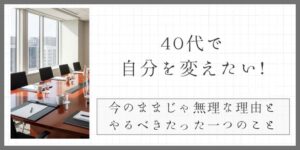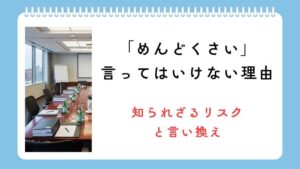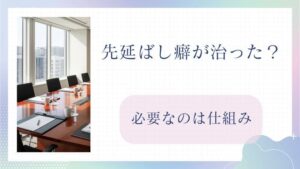「自分は視野が狭い、頭が悪いのかもしれない」と悩んでいませんか。
そのせいで、仕事ができないと感じたり、周囲との会話がうまくいかなかったりする経験があるかもしれません。
時には他人にイライラされたり、距離を置くと言われたりして、視野が狭い人の末路を想像し、不安になることもあるでしょう。
この記事では、視野が狭いと言われる人の特徴や性格、そして、そうなってしまうのはなぜか、その原因を深く掘り下げていきます。
また、視野が狭いことのデメリットだけでなく、隠されたメリットや、発達障害との関連性についても解説します。
最終的に、視野が狭いのを直す具体的な改善方法を、分かりやすくご紹介します。
最後まで読んでもらえれば、「視野が狭い」という自己否定から解放されます。
自分の特性を強みとして活かし、弱点を改善する方法を知ることで、より自分らしく輝ける未来が待っています。
- 「視野が狭い」の本当の意味と原因
- 「視野が-が狭い」ことの意外なメリット
- 仕事や人間関係で損しないための対処法
- 自分の特性を活かす具体的な改善トレーニング
「視野が狭い人は頭が悪い」は誤解?その本質を探る
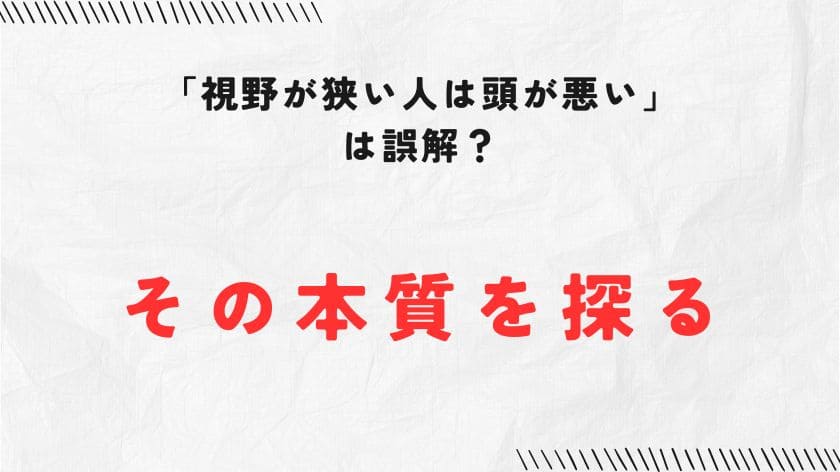
- 特徴とその性格とは?
- その原因を解説
- 発達障害の可能性も?
- デメリットとメリット
- 会話で起きがちなこと
- イライラしたら距離を置くべき?
特徴とその性格とは?

「視野が狭い」と言われる人には、いくつかの共通した特徴や性格の傾向が見られます。
これは決して「頭が悪い」ということではなく、物事の捉え方や考え方のスタイルに起因するものです。
最も代表的な特徴は、自分の経験や知識、価値観に基づいて物事を判断しようとする点です。
自分の考えに絶対的な自信を持っていることが多く、一度「これが正しい」と思い込むと、なかなかその考えを変えることができません。
このため、周りからは「頑固」「自己中心的」と見られてしまうことがあります。
【ポイント】視野が狭い人に見られる主な特徴
- 他人の意見を聞き入れない
自分の意見と違うと、すぐに否定したり聞く耳を持たなかったりします。 - 変化を嫌う
新しいことへの挑戦に抵抗があり、慣れ親しんだやり方や環境を好みます。 - 客観性に欠ける
物事を自分の視点からしか見ることができず、多角的な判断が苦手です。 - 自信過剰
自分の考えが常に正しいと信じているため、間違いを指摘されても素直に認められません。 - 想像力の欠如
「これを言ったら相手はどう思うか」といった、他人の気持ちを想像するのが不得意な場合があります。
これらの特徴は、裏を返せば「信念が強い」「一度決めたことをやり通す力がある」とも言えます。
しかし、社会生活やチームで活動する上では、他者との協調を難しくする要因となり得ます。
大切なのは、これらの特徴を自覚し、自分の思考の癖を理解することから始めることです。
その原因を解説

人が視野が狭くなってしまうのには、いくつかの原因が考えられます。
生まれ持った性格だけでなく、育ってきた環境や現在の状況も大きく影響します。
主な原因の一つは、経験の不足です。
これまでの人生で多様な価値観や文化に触れる機会が少なかったり、いつも同じコミュニティの中で過ごしていたりすると、自分の知っている世界が「常識」となりがちです。
その結果、自分とは異なる考え方を受け入れにくくなってしまいます。
また、強い固定観念や成功体験も原因となり得ます。
「こうあるべきだ」という思い込みが強かったり、過去の成功体験に固執してしまったりすると、新しいやり方や考え方に対して否定的になります。
「昔はこの方法でうまくいったから」と、状況の変化を考慮せずに同じ方法を続けようとするのは、この典型例です。
【注意】ストレスや疲労も視野を狭くする
心理的な余裕のなさも、視野が狭くなる大きな原因です。仕事やプライベートで強いストレスを感じていたり、慢性的に疲労が溜まっていたりすると、脳は目の前の脅威に対処することに集中しようとします。その結果、他の情報に注意を払う余裕がなくなり、一時的に思考が凝り固まってしまうのです。
このように、視野が狭くなる原因は一つではありません。
自分自身の経験や現在の心理状態を振り返ることで、なぜ視野が狭くなってしまうのか、その背景を理解するヒントが見つかるかもしれません。
発達障害の可能性も?
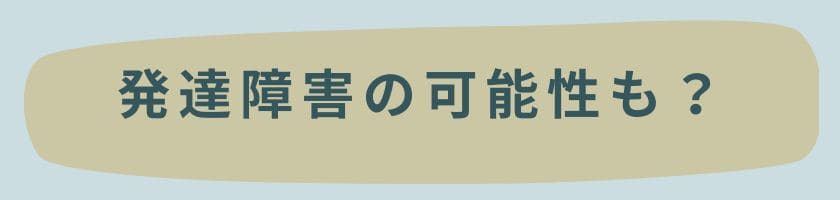
視野の狭さという特性は、ASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害の特性の一つとして見られることがあります。
もちろん、視野が狭いからといって、誰もが発達障害であると断定することはできません。
しかし、その背景に障害の特性が隠れている可能性も知っておくことが大切です。
ASDの特性の一つに、「特定の物事への強いこだわり」や「興味の範囲が限定的」というものがあります。
この特性が、ある分野においては驚異的な集中力や専門知識として発揮される一方で、興味のないことには全く関心を示さず、結果として視野が狭く見えることがあります。
また、他人の気持ちを想像したり、言葉の裏にある意図を汲み取ったりすることが苦手な場合も多いです。
これが「他者の視点を考慮できない」と受け取られ、視野が狭いという評価につながることも考えられます。
【補足】専門家への相談が重要です
もし、視野の狭さに加えて、「対人関係で極端な困難を感じる」「感覚が過敏または鈍感である」「特定の習慣や手順に強くこだわる」といった特徴が日常生活に大きな支障をきたしている場合は、専門の医療機関に相談することを検討してみるのも一つの方法です。発達障害は、適切な診断と支援を受けることで、本人の生きづらさを軽減し、特性を強みとして活かす道筋を見つけることができます。
これは、医師による診断が必要な専門領域です。自己判断せず、気になる場合は専門家にご相談ください。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)
繰り返しますが、視野が狭いという特性だけで発達障害と結びつけるのは早計です。
しかし、知識として知っておくことで、自分や他者への理解を深めるきっかけになるかもしれません。
デメリットとメリット
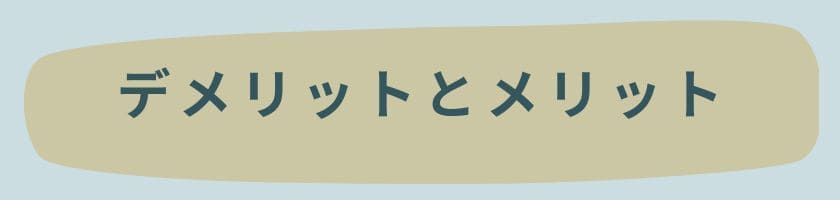
「視野が狭い」と聞くと、ネガティブな印象を持つ方が多いかもしれません。
実際にデメリットは存在しますが、一方で意外なメリットもあります。
物事を多角的に見るために、両方の側面を理解しておきましょう。
視野が狭いことの主なデメリット
最大のデメリットは、人間関係でのトラブルや孤立を招きやすいことです。
自分の意見に固執し、他人の話に耳を傾けない姿勢は、周囲との対立を生みます。
また、新しい情報や変化に対応できず、個人の成長が止まってしまうリスクもあります。
仕事においては、柔軟な発想ができなかったり、予期せぬトラブルに対応できなかったりするため、生産性の低下につながることも少なくありません。
視野が狭いことの意外なメリット
一方で、視野が狭いことは「集中力が高く、一つの物事を深く掘り下げられる」という大きなメリットにもなります。
興味の対象が限られているからこそ、その分野に対して驚異的な探求心と集中力を発揮できるのです。
これは、研究者や職人、プログラマーなど、高い専門性が求められる職業で大きな強みとなります。
いわば、「広く浅く」ではなく「狭く深く」というスタイルの天才肌とも言えるでしょう。
サヴァン症候群の人が特定の分野で超人的な能力を発揮するように、限定された領域でこそ輝く可能性があるのです。
| 側面 | 具体的な内容 |
| デメリット | ・人間関係で対立しやすい ・新しいアイデアが生まれにくい ・予期せぬトラブルに対応できない ・自己成長の機会を逃しやすい |
| メリット | ・特定の分野で高い専門性を発揮できる ・集中力が非常に高い ・物事を深く掘り下げて本質を追求できる ・一度決めたことをやり遂げる力がある |
このように、視野が狭いことにはデメリットとメリットの両面があります。
自分の特性を理解し、そのメリットを活かせる環境を見つけることが重要です。
会話で起きがちなこと
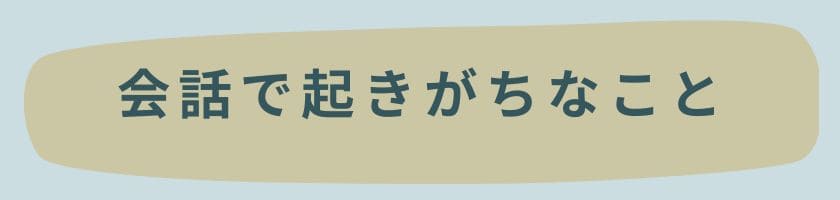
視野が狭い人と会話をすると、話が噛み合わなかったり、疲れてしまったりすることがあります。
これは、会話の前提となる考え方や物事の見方が異なるために起こります。
最もよくあるのが、会話が一方通行になることです。
相手は自分の意見や考えを話すことに集中しており、こちらの話を聞いていなかったり、理解しようとしなかったりします。
たとえこちらが意見を述べても、「でも」「それは違う」と否定から入ることが多く、建設的な議論になりにくい傾向があります。
例えば・・・
Aさん:「新しいプロジェクト、B案の方がリスクが少なくて良いと思うんです。」
Bさん:「いや、A案の方が絶対にインパクトがある。これまでもこのやり方で成功してきたんだから、今回もA案でいくべきだ。」
Aさん:「でも、市場の状況が以前とは違っていて…」
Bさん:「そんなのは関係ない。私の経験上、A案が正しい。」
また、自分の経験や知識が全ての基準であるため、自分が知らない話題や価値観については全く興味を示さないか、見下したような態度をとることもあります。
共感する能力が低いわけではありませんが、自分と違う立場や感情を想像することが苦手なため、結果的に相手を思いやれない発言をしてしまうのです。
このような会話が続くと、話している側は「何を言っても無駄だ」と感じ、次第にコミュニケーションを取ること自体を諦めてしまいます。
イライラしたら距離を置くべき?
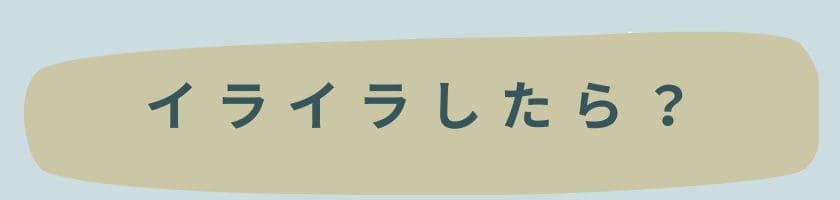
視野が狭い人の言動に対して、ついイライラしてしまうことは誰にでもあるでしょう。
正論をぶつけても変わらない相手に対して、どのように接すれば良いのでしょうか。
結論から言うと、心理的な距離を置くことが有効な対処法になる場合があります。
相手を変えようと説得を試みても、エネルギーを消耗するだけで、良い結果に繋がらないことが多いからです。
相手の言動に深く関与せず、「この人はこういう考え方なんだ」と受け流すことで、自分の心の平穏を保つことができます。
距離を置くことは、無視」ではありません。
ここで言う「距離を置く」とは、完全に無視したり、関係を断ち切ったりすることだけを指すわけではありません。
以下のような、心理的な関わり方を変えることです。
- 議論を避ける
意見が対立しそうな話題については、深く議論しない。 - 期待しない
相手が自分の意見を理解してくれたり、変わってくれたりすることを期待しない。 - 感情的に反応しない
相手の言動に一喜一憂せず、冷静に対応する。
ただし、相手の言動によって自分が明らかに不利益を被っていたり、精神的に追い詰められたりしている場合は、物理的に距離を取ることも必要です。
職場であれば上司に相談する、プライベートであれば会う頻度を減らすなど、自分自身を守るための行動を優先してください。
相手を無理に変えようとしてもムダになることが多いです。
自分がストレスを感じない関わり方を見つける方が、賢明な選択と言えるでしょう。
「視野が狭い人は頭が悪い」と言われないための改善策
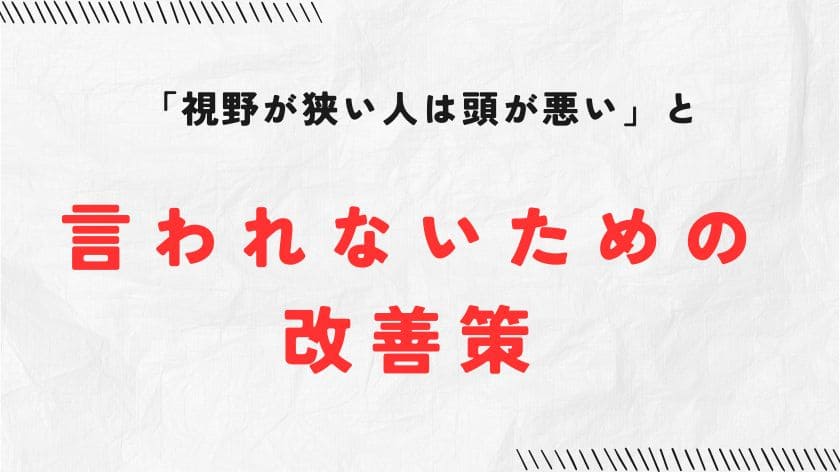
- 仕事ができないと言われる理由
- 末路はどうなるのか
- 改善する具体的な対処法
- 仕事でのを改善トレーニング
- コンフォートゾーンの正しい広げ方は?
- 虫の目、鳥の目、魚の目、コウモリの目
- 意識的に実際の視野を動かす
- 視野が狭いと頭が悪いは違う?多角的な視点を
仕事ができないと言われる理由
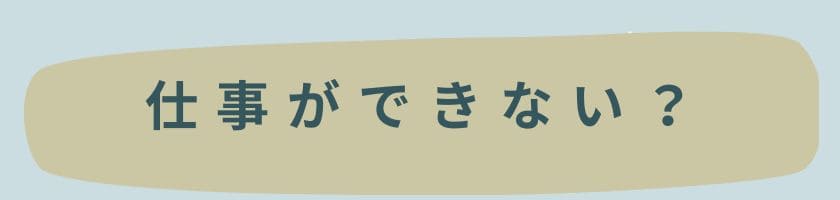
現代のビジネスシーンにおいて、「視野が狭い」という特性は「仕事ができない」という評価に直結してしまうことがあります。
なぜなら、多くの仕事は他者との連携や、目まぐるしく変わる状況への柔軟な対応が求められるからです。
具体的な理由として、まず「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」ができない点が挙げられます。
「これくらい自分で判断できる」「報告する必要はないだろう」と自己完結してしまい、チーム全体の情報共有を滞らせます。
これが原因で、大きなミスやトラブルに発展することも少なくありません。
次に、長期的な視点を持てないことも理由の一つです。
目先の利益や目前のタスクにばかり気を取られ、数ヶ月後、数年後を見据えた行動ができません。
その結果、将来的に大きな損失を招くような判断をしてしまうリスクがあります。
他にも、仕事で不利になる理由があります。
- トラブルに弱い
想定外の事態が起こると、どう対処していいか分からずパニックに陥りやすい。 - 他者への配慮が欠ける
「チームメイトはどう思うか」「お客様の立場ではどう感じるか」といった想像力が働かず、協調性を欠いた行動をとりがち。 - リーダーシップが取れない
部下や後輩の意見を聞き入れず、一方的な指示ばかり出すため、人がついてこない。
これらの理由は、個人の能力の問題というよりは、思考のスタイルの問題です。
チームで成果を出すことが求められる職場環境では、このスタイルが大きな障壁となってしまうのです。
末路はどうなるのか
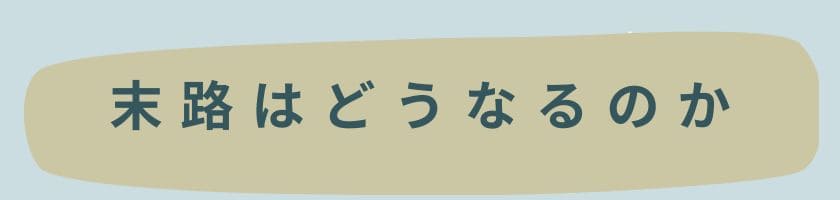
視野が狭い状態を放置し続けると、仕事やプライベートにおいて、望まない未来を迎えてしまう可能性があります。
これは決して脅しではなく、起こりうるリスクとして冷静に知っておくことが重要です。
最も懸念されるのは、社会的な孤立です。
自分の意見に固執し、他人のアドバイスに耳を貸さない姿勢を続けていると、次第に周囲から人が離れていきます。
最初は心配してくれていた友人や同僚も、「何を言っても無駄だ」と諦めてしまい、重要な情報が回ってこなくなったり、相談相手がいなくなったりします。
仕事の面では、成長の機会を完全に失ってしまうでしょう。
新しいスキルや知識を学ぼうとせず、過去のやり方に固執するため、時代の変化についていけません。
その結果、昇進や重要なプロジェクトから外され、キャリアアップが望めなくなる可能性があります。
このような末路を避けるためには、現状に危機感を持ち、自ら変わろうと意識することが不可欠です。
手遅れになる前に、次にご紹介する改善策に取り組んでみましょう。
改善する具体的な対処法
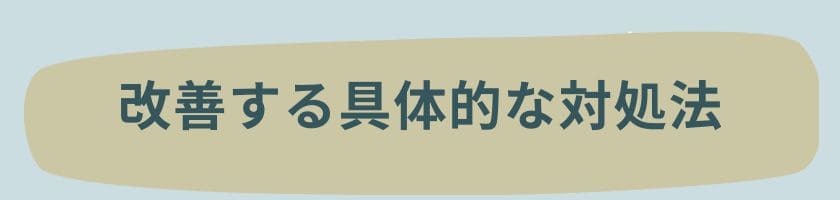
「視野が狭いのを直したい」と思っても、何から始めれば良いか分からないかもしれません。
視野を広げるには、特別な才能は必要なく、日々の少しの意識と行動で変えていくことができます。
最も効果的なのは、経験をすることです。
視野が狭い人の特徴の一つとして、絶対的な経験不足というものがあります。
経験がないので、視野が広く取れないんです。
なので、あなたにとっての「未知」に触れる機会を意識的に増やすことです。
自分のコンフォートゾーン(快適な領域)から一歩踏み出し、新しい情報や価値観に自分を晒すことが、思考の枠を広げるトレーニングになります。
日常生活でできる具体的な対処法は、4つあります。
- 多彩なジャンルの本や映画に触れる
- 新しい趣味や学びを始める
- 行ったことのない場所へ旅行する
- 批判的思考(クリティカルシンキング)を意識する
多様なジャンルの本や映画に触れる
視野を広げるには、読書が一番です。
ただし、好きな本をいくら読んでもムダで、視野を広げるには、普段は手に取らないジャンルの本を読むことです。
1冊の本には1人の人生が詰まっていますので、読んだ本の数だけ、人生を体験できるので視野が広がります。
映画も同じですが、ちょっとしたコツがあります。
それは、主人公や好きな登場人物に焦点を絞るのではなくて、脇役の人や悪役の人の心情にも想像を働かすことです。
映画の登場人物が10人いたら、10通りの考え方があります。
それを想像しながら見て、なぜこの人はここでこういうセリフを言ったのだろうか?と考えながら見ることで、視野を広げられます。
また、違った映画の楽しみ方も発見できるはずです。
新しい趣味や学びを始める
今まで全く興味がなかった分野の習い事を始めたり、オンライン講座で新しいスキルを学んだりするのも有効です。
新しいコミュニティに属することで、これまで関わりのなかったタイプの人々と出会うきっかけにもなります。
行ったことのない場所へ旅行する
国内でも海外でも、知らない土地を訪れることは五感を刺激し、固定観念を揺さぶります。
旅先での予期せぬ出来事や人々との出会いが、物事の見方を大きく変えてくれるかもしれません。
批判的思考(クリティカルシンキング)を意識する
情報に触れたとき、「これは本当だろうか?」「別の見方はないか?」と一度立ち止まって考える癖をつけましょう。
特に、自分の意見と同じ情報に触れたときこそ、あえて反対の意見を探してみることが重要です。
これらの対処法は、一つひとつは小さなことかもしれません。
しかし、継続することで確実にあなたの思考に柔軟性をもたらし、より広い視野で物事を捉えられるようになるはずです。
仕事での改善トレーニング
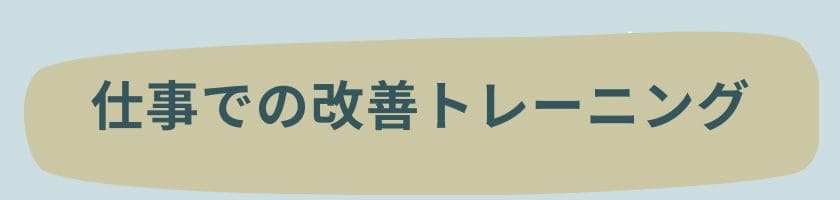
仕事の場面で「視野が狭い」と指摘されることが多い場合、日々の業務の中で改善していくトレーニングが有効です。
ここでは、明日からすぐに実践できる具体的な方法をいくつかご紹介します。
まず基本となるのが、他人の意見を「傾聴」する姿勢です。
ただ話を聞くのではなく、相手が「なぜそう考えるのか」という背景や意図まで理解しようと努めます。
すぐに反論するのではなく、一度「なるほど、そういう考え方もあるのか」と受け止める癖をつけましょう。
【ポイント】尊敬する人になりきって考える
何か判断に迷ったとき、「もし、あの尊敬する上司(や歴史上の偉人)だったら、この状況でどう考えるだろうか?」と想像してみるトレーニングです。自分の視点から一旦離れ、他者の思考プロセスを追体験することで、一人では思いつかなかったような選択肢や解決策が見えてきます。これを習慣にすることで、自然と多角的な視点が身につきます。
また、担当業務の「全体像」を把握する意識も重要です。
自分の仕事が、部署全体や会社全体のどの部分を担っているのか、そして顧客にどのような価値を提供しているのかを考えてみましょう。
上流工程や下流工程の担当者と積極的にコミュニケーションを取ることで、自分の仕事の前後にあるつながりが見え、視点が格段に広がります。
さらに、複数の情報源にあたることも効果的なトレーニングです。
一つのニュースを、複数の新聞社や海外メディアのサイトで読み比べてみてください。
同じ事象でも、立場や視点によって伝え方が全く異なることに気づくはずです。これにより、物事を鵜呑みにせず、客観的に判断する力が養われます。
コンフォートゾーンの正しい広げ方は?
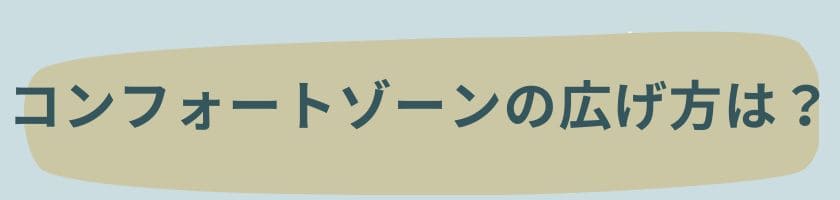
視野を広げるための行動には、時として少しの勇気が必要です。
多くの人が「新しいことに挑戦しよう」と意気込みますが、実はその挑戦の「さじ加減」が非常に重要になります。
ここで鍵となるのが、「コンフォートゾーン」効果的に広げていくという考え方です。
コンフォートゾーンとは、一言で言えば「居心地の良い、慣れ親しんだ領域」のことです。
このゾーンにいる間、私たちはストレスなく過ごせますが、一方で新たな学びや成長はあまり期待できません。
いきなり大きな挑戦をするのは逆効果
視野を広げたいからといって、いきなりコンフォートゾーンから遠く離れた「パニックゾーン」に飛び込むのは避けるべきです。
あまりに難易度が高すぎる挑戦は、過度なストレスや不安を引き起こし、「自分には無理だ」という無力感を植え付けてしまいます。
結果的に、挑戦すること自体が怖くなってしまう可能性もあるのです。
そこで大切になるのが、コンフォートゾーンのすぐ外側にある「ストレッチゾーン」で活動することです。
ストレッチゾーンに挑戦する具体例
ストレッチゾーンとは、「簡単にできる」と「むずかしい」の間の「ちょいムズ」の部分のことです。
いきなり海外の知らない人と話すのではなく、まずは職場のあまり話したことのない部署の人に挨拶してみる。
全く読んだことのない哲学書に挑むのではなく、興味のある分野の入門書や新書を読んでみる。
このように、「今の自分にとっては少し難しいけれど、頑張れば何とかなりそう」というレベルの挑戦を積み重ねることです。
そのことで、安全かつ効果的にコンフォートゾーンを広げられ、視野を広げていけます。
虫の目、鳥の目、魚の目、コウモリの目
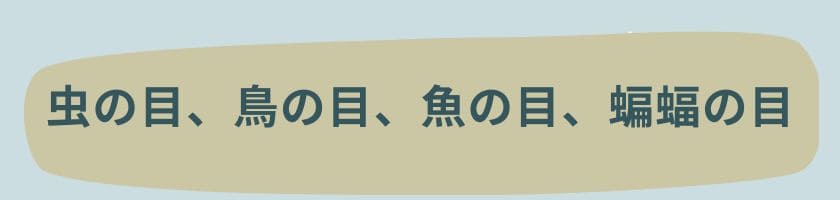
物事を多角的に見るための具体的な思考法として、古くから知られているフレームワークに「虫の目、鳥の目、魚の目」があります。
これに、現代的な視点である「コウモリの目」を加えることで、より強力に視野を広げることができます。
これらは、意識的に視点を切り替えるための「思考の道具」です。
虫の目:細部を掘り下げて見る
地面を這う虫のように、物事をミクロな視点で詳しく見る考え方です。
具体的な要素に分解したり、異なる切り口から詳細を分析したりする際に使います。
現場レベルでの具体的な課題発見や、緻密な計画立案に役立ちます。
鳥の目:全体を俯瞰して見る
空を飛ぶ鳥のように、高い位置から全体を大きく捉える視点です。
物事の全体像、他の要素との関連性、そしてその中での自分の立ち位置を把握します。
ただ、いきなり「鳥の目で見て」と言われても無理じゃないでしょうか。
そのための方法として、次のような人になりきって、その人の目線で見てみることをオススメします。
- 社長や専務、乗務
- 所属部署の部長
- 他部署の部長
- 一つ上の上司
- 顧客
いろいろな人の目線から、あなたがやってる仕事や状況を見ることで、自然に大局的な判断や、長期的な戦略を考えられます。
魚の目:時代の流れを読む
潮の流れを読む魚のように、時間軸や環境の変化を捉える視点です。
過去から現在、そして未来へと続くトレンドの変化を読み解きます。
市場の動向、技術の進化、社会情勢の変化などを敏感に察知し、次の一手を考えるために重要です。
コウモリの目:物事を逆から見る
逆さまにぶら下がるコウモリのように、常識や前提を疑い、物事を全く逆の視点から見る考え方です。
そのために必要な質問は次の3つです。
- なんのために?
- 本当に正しいの?
- 失敗は何?
固定観念を打ち破り、革新的なアイデアを生み出すきっかけになります。
4つの目をまとめると次のようになります。
| 視点(目) | 主な役割 | キーワード |
|---|---|---|
| 虫の目 | 詳細分析・具体化 | 分解する、掘り下げる、当事者目線 |
| 鳥の目 | 全体把握・構造理解 | 俯瞰する、抽象化する、経営者目線 |
| 魚の目 | 変化・トレンドの察知 | 流れを読む、時間軸、環境変化 |
| コウモリの目 | 前提の疑い・逆転の発想 | 逆から見る、疑う、本質を問う |
これらの4つの「目」を使い分けることで、一つの物事に対して立体的で深い理解を得ることが可能になります。
意識的に実際の視野を動かす
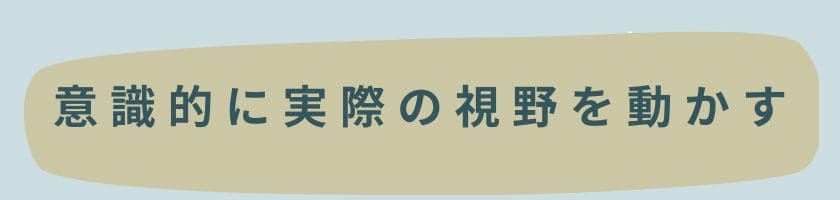
「視野が狭い」という言葉は、思考や心理状態を指すことが多いですが、実は私たちの「身体的な視野」と「心理的な視野」は密接に連動しています。
集中してPCの画面を睨み続けている時、私たちの心も同じように一点に集中し、周りが見えなくなっているのです。
このつながりを逆手にとって、物理的に「見る範囲」を意識的に動かすことで、凝り固まった思考をリセットし、心理的な視野を広げるきっかけを作ることができます。
デスクでできる3つの「視野を動かす」習慣
- 遠くを見る
1時間に1回、意識的に窓の外や部屋の最も遠い場所を数秒間眺めましょう。PC画面に固定されていた目のピントが解放されると同時に、思考も一点集中から解放されます。「木を見て森を見ず」の状態から、強制的に「森」に意識を向ける効果があります。 - 周辺視野を意識する
PC画面を見ながらも、自分の視界の端に映っているもの(例:隣の人の動き、壁のポスターなど)をぼんやりと意識してみてください。これは「トンネルビジョン」と呼ばれる、心理的に追い詰められた時に起こる視野狭窄の状態を緩和するトレーニングになります。 - 物理的に首を動かし、周りを見渡す
ただ目線を動かすだけでなく、ゆっくりと首を回して、オフィス全体を見渡してみましょう。誰がどんな表情で仕事をしているか、どんな会話が交わされているかを感じることで、自分がチームの一員であることを再認識し、独りよがりな思考から抜け出しやすくなります。
「そんな簡単なことで?」と思われるかもしれません。
しかし、思考が行き詰まった時ほど、私たちの身体は固まっています。
意識的に身体の視野を動かすことは、脳に「今はリラックスして、広く物事を見ていいんだよ」というサインを送る、非常に効果的なメンタルハックなのです。
ぜひ、騙されたと思って試してみてください。
まとめ:視野が狭いと頭が悪いは違う?多角的な視点を
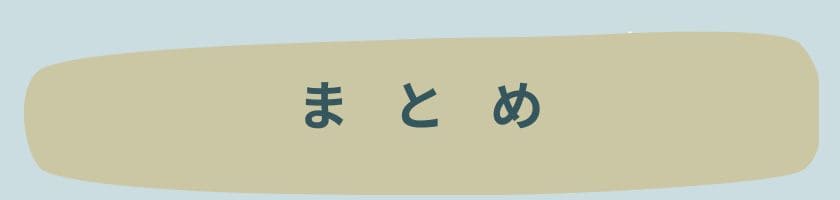
この記事を通じて、視野の狭さに関する様々な側面を見てきました。
最後に、最も重要なポイントをまとめて振り返ります。
- 「視野が狭い=頭が悪い」は必ずしも正解ではない
- 物事を狭く深く探求できるのは一つの才能
- 集中力や専門性が高いというメリットもある
- 一方で他者の意見を受け入れにくいデメリットも
- 主な原因は経験不足や固定観念にある
- ストレスや疲労で一時的に視野が狭くなることもある
- 発達障害の特性として現れる場合もある
- 仕事ではチームワークや変化への対応で不利になりやすい
- 人間関係で孤立してしまうリスクがある
- 改善の第一歩は自分の特性を自覚すること
- 意識的に新しい情報や価値観に触れるのが有効
- 本を読んだり新しい趣味を始めたりする
- 自分と違う意見を持つ人の話を傾聴する
- 「もしあの人ならどう考えるか」と想像してみる
- 大切なのは物事を多角的に見る習慣をつけること