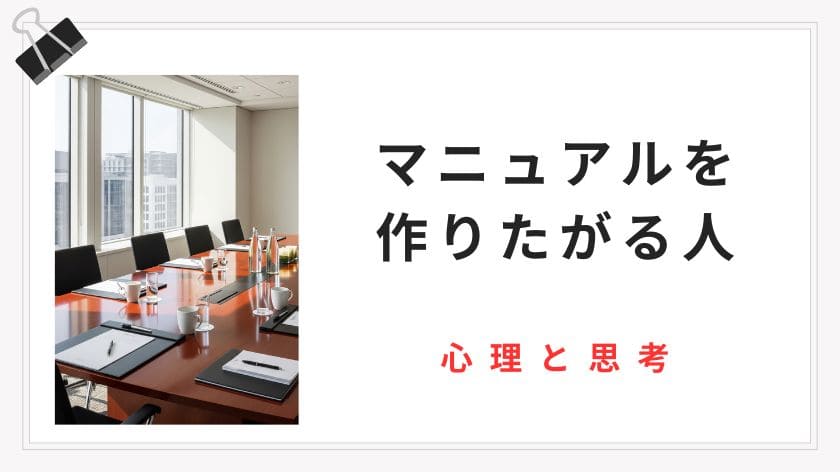あなたの職場に、何かと業務を文書化し、マニュアルを作りたがる人はいませんか?
業務の標準化に貢献してくれる一方で、「仕事でマニュアルにこだわる人だな」「少しマニュアル作りすぎでは?」と感じることもあるかもしれません。
中には、マニュアル化したがるあまり、柔軟性に欠ける「マニュアル人間はうざい」という厳しい意見も存在します。
この記事では、そうしたマニュアル作りが得意な人の特徴や、マニュアル作成に向いている人の適性を深掘りします。
業務マニュアルを作る人は頭いいのか、それとも単に融通が利かないだけなのか。マニュアル作れない人と作れる人の違いはどこにあるのでしょう。
また、新人にマニュアルを作らせる手法の是非や、そもそもマニュアル化できない仕事の領域についても考察します。
彼らの心理を理解し、その能力を組織の力に変えるためのヒントがここにあります。
- マニュアルを作りたがる人の心理的背景と5つの特徴
- 現場で本当に役立つ「使える」マニュアル作成のコツ
- マニュアルに依存するリスクと「マニュアル人間」にならない方法
- マニュアル好きな同僚や部下との上手な付き合い方
マニュアルを作りたがる人の心理と特徴
- なぜ業務をマニュアル化したがるのか
- マニュアル作りが得意な人の特徴
- マニュアル作成に向いている人の適性
- 業務マニュアル作る人は頭いい?
- 仕事でマニュアルにこだわる人の心理
- マニュアル作りすぎ?作りたがる人の背景
- 「マニュアル人間はうざい」は本当か
- マニュアル作れない人と作れる人の違い
なぜ業務をマニュアル化したがるのか
結論から言うと、人が業務をマニュアル化したがる背景には、業務の標準化によって「効率」と「品質」を担保したいという合理的な目的があります。
誰が作業しても同じ成果を出せる状態を目指しているのです。
その理由は、業務の属人化を防ぎ、組織全体の生産性を向上させることにあります。
特定の人物しか知らないノウハウや手順が存在すると、その人が不在の場合に業務が滞るリスクが生じます。
マニュアルは、そうした暗黙知を形式知に変え、知識を組織全体で共有するための重要なツールとなります。
例えば、以下のような目的が考えられます。
- 新人教育の効率化:指導者による教え方のバラつきをなくし、新人がスムーズに業務を覚えられるようにする。
- ミスの防止:作業手順を明確にすることで、ヒューマンエラーを減らし、業務品質を安定させる。
- 教育コストの削減:先輩社員が指導に割く時間を減らし、本来の業務に集中できるようにする。
このように、マニュアル作成は組織の安定と成長を目指す、非常に論理的な活動だと言えるでしょう。
マニュアル作りが得意な人の特徴
マニュアル作りが得意な人には、単に真面目というだけでなく、いくつかの共通した特徴が見られます。
彼らは、情報を整理し、他者に分かりやすく伝えるための特有のスキルセットを持っています。
マニュアル作りが得意な人の5つの特徴
- 論理的思考力と構造化能力
複雑な業務プロセスを分解し、手順を論理的に再構築する力があります。物事を体系的に捉えるのが得意です。 - 読み手への配慮(共感力)
マニュアルを読む人の知識レベルや立場を想像し、「どこでつまずくか」「どんな情報が必要か」を先回りして考えることができます。 - 業務への深い理解
対象となる業務の目的や全体像を把握しています。そのため、単なる手順の羅列ではなく、「なぜこの作業が必要か」という背景まで説明できます。 - 言語化能力と表現力
曖昧な表現を避け、誰が読んでも同じように解釈できる具体的で平易な言葉を選んで文章を作成する能力に長けています。 - 視覚的伝達能力
文章だけでなく、図やイラスト、フローチャートなどを効果的に活用し、直感的な理解を促す工夫ができます。
これらの特徴を持つ人は、単なる作業者ではなく、業務プロセスを客観的に分析・改善できるデザイナーのような視点を持っていると言えます。
マニュアル作成に向いている人の適性
前述の特徴を踏まえると、マニュアル作成という業務には特定の適性が求められることがわかります。
誰もが質の高いマニュアルを作れるわけではなく、やはり向き不向きが存在します。
マニュアル作成に特に向いているのは、情報を整理し、他者と粘り強くコミュニケーションを取れる人です。
自分の知識をまとめるだけでなく、現場の意見を吸い上げ、改善を繰り返す地道な作業を楽しめることが重要になります。
具体的には、以下のような適性を持つ人が挙げられます。
- 探求心がある:業務の「なぜ?」を常に考え、本質を理解しようと努める人。
- コミュニケーション能力が高い:現場の担当者にヒアリングを行い、必要な情報を引き出せる人。
- 根気強い:作成後のフィードバックを素直に受け入れ、改善を重ねることを厭わない人。
- 完璧主義すぎない:最初から100点満点を目指すのではなく、まずは60点でリリースし、現場で育てていくという柔軟な考え方ができる人。
逆に、自分のやり方に固執したり、大雑把な性格だったりする人は、マニュアル作成において苦労するかもしれません。
業務マニュアル作る人は頭いい?
「業務マニュアルを作る人は頭がいい」というイメージは、あながち間違いではありません。
ただし、それは学歴やIQといった尺度での「頭の良さ」とは少し異なります。
マニュアル作成に求められるのは、情報を整理・体系化し、最適な形で再出力する「構造的知性」です。
複雑に絡み合った現場の業務を、誰にでもわかるシンプルな手順に落とし込む作業は、高度な情報処理能力を必要とします。
例えば、料理のレシピを考えてみてください。
優れたレシピは、材料の分量、手順、火加減、コツなどが論理的に記述されており、初心者でもプロに近い味を再現できます。
このレシピを考案する行為が、マニュアル作成の本質に近いのです。
マニュアル作成者は、業務の「レシピ開発者」と言えるかもしれません。
彼らは業務を深く理解し、その再現性を高めることで、組織全体のスキルを底上げする知的な貢献をしているのです。
このように考えると、マニュアルを作る行為は、単なる文書作成ではなく、業務コンサルティングに近い知的な作業です。
その能力を持つ人は組織にとって非常に価値ある存在だと言えるでしょう。
仕事でマニュアルにこだわる人の心理
業務の効率化という合理的な目的を超えて、過度にマニュアルにこだわる人がいます。
そういう人の行動の裏には、いくつかの心理的な要因が隠れていることがあります。
その中心にあるのは、「不確実性への不安」や「コントロール欲求」です。
ルールや手順が明確でない状況に対して強いストレスを感じ、すべてを明文化することで安心感を得ようとします。
具体的には、以下のような心理が働いていると考えられます。
- 失敗への恐怖:マニュアル通りに行えば、失敗した際に「自分のせいではない」と責任を回避できると考えている。
- 対人関係の苦手意識:口頭での曖昧な指示や、その都度質問することを避けたい。文書化されたルールがあれば、人とのコミュニケーションを最小限にできる。
- 完璧主義:すべての業務が決められた通りに、一分の隙もなく行われるべきだという強い信念を持っている。
- 正義感:ルールを守らない人や、自己流で仕事を進める人に対して、許せないという気持ちが強い。
彼らのこだわりは、組織の秩序を守りたいという善意から来ている場合も多いです。
ただ、度を越すと周囲から「融通が利かない」と見なされ、敬遠される原因にもなり得ます。
マニュアル作りすぎ?作りたがる人の背景
「これもマニュアル、あれもマニュアル…」と、あらゆる業務を文書化しようとする人がいます。
このような「作りすぎ」の状態に陥る背景には、個人の性格だけでなく、組織側の問題が潜んでいることもあります。
考えられる背景の一つは、組織内に「心理的安全性」が欠如していることです。
ミスが許されず、一度の失敗で厳しい叱責を受けるような職場では、従業員は自分を守るためにマニュアルに依存しやすくなります。
マニュアルが過剰に作られる職場の特徴
- 指示が頻繁に変わる、または指示系統が混乱している。
- 過去に大きなトラブルがあり、再発防止のためにルールが細かくなりすぎている。
- 従業員の自主性を尊重せず、マイクロマネジメントが横行している。
- 従業員の入れ替わりが激しく、常に誰かが新人状態である。
このような環境では、従業員は自ら考えて行動することをやめ、思考停止に陥りがちです。
マニュアル作りが過剰になるのは、個人の問題というよりも、変化を恐れ、従業員を信頼できない組織の体質が反映された結果である可能性も考慮すべきでしょう。
「マニュアル人間はうざい」は本当か
「マニュアル人間」という言葉は、しばしばネガティブな意味で使われます。
指示されたことしかできず、臨機応応変な対応ができない人、というイメージが強いからでしょう。
しかし、この見方は本当に正しいのでしょうか。
この問題は、「マニュアルの質」と「マニュアルの使い方」という二つの側面から考える必要があります。
マニュアル自体が悪いのではなく、その内容や運用方法に問題があるケースがほとんどです。
| マニュアル人間の長所(メリット) | マニュアル人間の短所(デメリット) | |
|---|---|---|
| 組織への貢献 | ・業務品質が安定する ・作業の標準化が進む ・コンプライアンスを遵守する | ・イレギュラーな事態に対応できない ・業務改善のアイデアが出にくい ・顧客満足度が低下することがある |
| 個人の特性 | ・真面目で忠実 ・ルールを正確に実行する ・作業が丁寧でミスが少ない | ・自分で考えて行動するのが苦手 ・応用力や創造性に欠ける ・融通が利かない、頑固だと思われる |
確かに、マニュアルに書かれていない事態に直面した際に思考が停止してしまう点は大きな課題です。
しかし、定められた手順を正確に実行し、業務の品質を保つという点では、組織に不可欠な存在とも言えます。
重要なのは、マニュアルを「思考停止の道具」ではなく、「基礎を固めるためのツール」として正しく位置づけることです。
マニュアル作れない人と作れる人の違い
マニュアルをスムーズに作れる人がいる一方で、作成に大きな困難を感じる人もいます。
この違いは、単なる得意・不得意ではなく、思考のプロセスの違いに起因することが多いです。
最も大きな違いは、業務を「抽象化」し「構造化」できるかどうかにあります。
マニュアルを作れる人は、日々の具体的な作業の中から共通のパターンやルールを見つけ出し、それを論理的な手順として再構成する能力に長けています。
思考プロセスの比較
マニュアルを作れる人
業務全体を俯瞰し、スタートからゴールまでの流れを地図のように把握する。各工程を分解し、要素間の関係性を整理しながら、「なぜ→何を→どのように」という構造で組み立て直す。
マニュアルを作れない人
業務を個別の「点」として捉えがちで、それらの繋がりや全体像を把握するのが苦手。感覚や経験則(暗黙知)で作業しているため、それを他者にわかる言葉(形式知)に変換するのに苦労する。
マニュアルが作れないからといって、仕事ができないわけではありません。
むしろ、直感力に優れ、クリエイティブな発想が得意な場合もあります。
適材適所を考える上で、この思考特性の違いを理解しておくことは非常に重要です。
マニュアルを作りたがる人の能力を活かす方法
- 新人にマニュアルを作らせるメリット
- 「マニュアル作りすぎ」な同僚への上手な伝え方
- 現場で本当に使われるマニュアル作成のコツ
- マニュアル作成を効率化する最新ツール
- マニュアル化できない仕事とは
- マニュアル依存のリスクと注意点
- マニュアルを創造的に活用する方法
- マニュアル不要論への効果的な反論
- マニュアル化を推進すべき組織・不要な組織
- マニュアルを作りたがる人との共存
新人にマニュアルを作らせるメリット
一見すると、業務をまだ知らない新人にマニュアル作成を任せるのは非効率に思えるかもしれません。
しかし、この方法は教育手法として多くのメリットを持っています。
最大のメリットは、新人が業務を最も深く学ぶことができる点です。
マニュアルを作るためには、業務の手順や目的を他者に説明できるレベルまで理解する必要があります。
このプロセスを通じて、受け身で教わるだけの場合よりも、能動的かつ体系的に知識を習得できるのです。
新人がマニュアルを作るメリット
- 業務理解の深化
作成過程で不明点を自ら調べ、質問するため、業務の本質的な理解につながる。 - 初心者の視点を反映
経験者が見落としがちな「当たり前」のポイントや、初心者がつまずきやすい箇所が明確になり、より分かりやすいマニュアルが完成する。 - 既存マニュアルの陳腐化防止
新人の新鮮な目で既存の業務フローを見直すことで、形骸化したルールの発見や業務改善のきっかけになる。
ただし、デメリットも存在します。
熟練者に比べて作成に時間がかかることや、内容の正確性を担保するために先輩社員のレビューが不可欠である点は考慮が必要です。
丸投げにするのではなく、OJTの一環としてサポート体制を整えた上で実施することが成功の鍵となります。
「マニュアル作りすぎ」な同僚への上手な伝え方
善意からとはいえ、同僚の過剰なマニュアル作成が業務の柔軟性を奪い、かえって非効率になっていると感じることもあるでしょう。
しかし、相手のやる気を削ぐような直接的な否定は避けたいものです。
重要なのは、相手の行動そのものではなく、「目的」と「優先順位」に焦点を当てて対話することです。
「マニュアルを作るな」ではなく、「より効果的な方法を一緒に考えよう」というスタンスで提案するのが良いでしょう。
あなた:「〇〇さん、いつも詳細なマニュアル作成ありがとうございます。すごく助かっています。ところで、今作っていただいている△△の件ですが、緊急度が高い□□の業務を先に進めるために、マニュアルは要点だけをまとめた簡易版にするのはどうでしょうか?細かい部分は、運用しながらみんなで追記していく形にして…」
同僚:「なるほど、確かに□□が遅れる方が問題ですね。分かりました、まずは骨子だけ作ってみます!」
このように、感謝の意を伝えた上で、現状の課題(緊急度の高い業務)を共有し、代替案(簡易版の作成)を提案するという流れが効果的です。
相手の「貢献したい」という気持ちを尊重しつつ、チーム全体の目標達成に向けて軌道修正を促すことができます。
現場で本当に使われるマニュアル作成のコツ
せっかく作ったマニュアルが、書庫の肥やしになってしまっては意味がありません。
現場で日常的に活用され、業務品質の向上に貢献する「生きたマニュアル」を作るためには、いくつかのコツがあります。
最も重要なのは、「完璧さ」よりも「検索性」と「更新性」を重視することです。
分厚くて美しいマニュアルよりも、必要な情報がすぐに見つかり、現場の変化にすぐに対応できるマニュアルの方がはるかに価値があります。
「使える」マニュアル作成の5つのコツ
- 目的とターゲットを明確にする
「誰が、どんな時に、何のために見るのか」を最初に定義する。 - 一文一義を心がける
1つの文章には1つの情報だけを盛り込み、簡潔に記述する。専門用語は避けるか、注釈を入れる。 - 文章よりビジュアル
フローチャートやスクリーンショット、写真や動画などを積極的に活用し、直感的に理解できるようにする。 - 現場の声を反映させる
作成段階から実際に業務を行う担当者を巻き込み、フィードバックをもらいながら作成・改善する。 - 管理担当者を決める
誰が、いつ、どのように情報を更新するのか、メンテナンスのルールを明確にしておく。
マニュアルは完成したら終わりではありません。
現場と共に成長していくものと考えることが、形骸化させないための鍵です。
マニュアル作成を効率化する最新ツール
従来のマニュアル作成は、WordやExcel、PowerPointといった汎用ソフトで行われることが多く、レイアウトの調整や更新作業に多大な手間がかかっていました。
しかし現在では、マニュアル作成を劇的に効率化する様々なツールが登場しています。
これらのツールを導入することで、作成時間の短縮だけでなく、共有や管理、効果測定までを一元的に行うことが可能になります。
| ツールの種類 | 代表的なツール例 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| マニュアル作成特化型ツール | Teachme Biz, Dojo, tebiki | テンプレートが豊富。画像や動画の挿入が容易で、誰でも見やすいマニュアルが簡単に作れる。閲覧状況の分析機能も。 |
| 情報共有ツール(Wikiツール) | Notion, Confluence, Googleサイト | 複数人での同時編集やコメント機能に優れる。情報の階層化やリンク設定が柔軟で、社内ナレッジベースの構築に最適。 |
| 動画マニュアル作成ツール | tebiki, iTutor | スマホで撮影した動画から簡単にマニュアルを作成可能。操作手順や身体の動きなど、文章では伝えにくい内容に強い。 |
ツールの選定にあたっては、自社の課題を解決できる機能があるかどうかが重要な判断基準となります。
「文章だけでは伝わりにくい作業が多い」のであれば動画マニュアルツール、「情報の更新頻度が高い」のであれば情報共有ツール、といったように、目的に合ったツールを選ぶことが業務効率化への近道です。
マニュアル化できない仕事とは
マニュアルは業務の標準化に非常に有効ですが、全ての仕事がマニュアル化に適しているわけではありません。
無理にマニュアル化しようとすると、かえって仕事の質を下げてしまう領域も存在します。
「高度な判断力」「創造性」「対人コミュニケーション」が求められる業務は、マニュアル化が困難、あるいは不向きです。
これらは「感覚型」の業務とも呼ばれ、個人の経験や知識、その場の状況に応じた柔軟な対応が必要とされます。
マニュアル化が難しい業務の例
- 戦略的意思決定:経営戦略や事業計画の策定など、未来の不確実な要素を考慮して判断する業務。
- 研究開発・企画:新しい製品やサービスを生み出すための、試行錯誤やひらめきが求められる業務。
- 高度なコンサルティング:顧客の複雑な課題をヒアリングし、オーダーメイドの解決策を提案する業務。
- クレーム対応:相手の感情を読み取りながら、状況に応じた最適な対応を見つけ出す業務。
- 部下の育成やコーチング:相手の個性や成長段階に合わせて、指導方法を変える必要がある業務。
これらの業務においては、手順を定めたマニュアルではなく、判断の拠り所となる「指針(ガイドライン)」や、過去の成功・失敗事例をまとめた「ケーススタディ」を整備する方が、個人のパフォーマンス向上に繋がります。
マニュアル依存のリスクと注意点
マニュアルは業務の質を担保する上で有効な一方、過度に依存してしまうと組織に様々なリスクをもたらします。
メリットの裏側にあるデメリットを理解し、注意深く運用することが求められます。
最大のリスクは、従業員の「思考停止」を招き、自律的に行動できる人材が育たなくなることです。
マニュアルに書かれていることだけをこなすのが目的化し、それ以上の創意工夫や改善への意欲が失われてしまいます。
マニュアル依存がもたらす主なリスク
- 柔軟性の欠如
マニュアルにないイレギュラーな事態が発生した際に、誰も対応できず業務が停止する。 - モチベーションの低下
自分の工夫やアイデアを業務に活かす機会が奪われ、仕事が「やらされ仕事」になる。 - 責任感の希薄化
問題が発生した際に、「マニュアル通りにやった」と言い訳をし、当事者意識が欠如する。 - 組織の硬直化
業務プロセスが固定化され、環境の変化に対応できず、組織全体の競争力が低下する。
これらのリスクを避けるためには、マニュアルを「絶対的なルールブック」ではなく、あくまで「基本を学ぶための教科書」と位置づけ他方が良いです。
そこからの応用や改善を奨励する文化を醸成することが不可欠です。
マニュアルを創造的に活用する方法
マニュアルを単なる「指示書」として捉えるのではなく、「思考を深めるためのツール」として活用することで、個人の成長と組織のイノベーションを促すことができます。
伝統的な芸事の世界で言われる「守破離」の考え方が、ここでも役立ちます。
「守破離」とは、成長の段階を示す言葉
- 守(しゅ):まずは師の教え(マニュアル)を忠実に守り、基礎となる型を徹底的に身につける段階。
- 破(は):基礎を習得した上で、他の良い点を取り入れたり、自分なりに工夫したりして、既存の型を破っていく段階。
- 離(り):独自の新しいものを生み出し、型から離れて自在の境地に至る段階。
マニュアルが担うのは、最初の「守」のフェーズです。
しかし、そこで終わらせず、従業員が「破」や「離」のステージに進めるような仕掛けを作ることが、創造的な活用の鍵となります。
創造的活用のためのアイデア
- マニュアル改善提案制度:従業員からのマニュアル改善案を定期的に募集し、優れた提案を表彰する。
- 「あえてマニュアルを読まない」訓練:安全に関わらない業務で、意図的にマニュアルを見ずに試行錯誤させ、後で答え合わせをする機会を作る。
- 目的の共有:手順だけでなく、「なぜこの作業が必要か」という目的をマニュアルに明記し、目的達成のための別のアプローチを考えさせる。
マニュアル不要論への効果的な反論
職場によっては、「マニュアルなんて不要だ」「そんなものを作ったらマニュアル人間になるだけだ」といった根強い不要論が存在します。
マニュアル化を推進する上で、こうした意見にどう対応すればよいのでしょうか。
重要なのは、感情的に対立するのではなく、データと論理に基づいてマニュアルの費用対効果を示すことです。
相手の主張を一つずつ整理し、それに対する合理的な反論を用意しましょう。
| よくある不要論 | 効果的な反論の切り口 |
|---|---|
| 「マニュアルを作っても誰も見ない」 | 「仮定の話ではなく、まずはお試しで作成し、効果を測定しませんか?見られないとしたら、その原因を改善していくことが重要です。」 |
| 「マニュアルがなくても仕事は回っている」 | 「日常業務が回るのは当然です。問題は、新人が一人前になるまでの時間や教育コストです。この現状は最適と言えるでしょうか?」 |
| 「マニュアルを作るとそれ以上のことをしなくなる」 | 「それはマニュアルの質と使い方の問題です。業務の目的や理念を共有する『良いマニュアル』を作り、応用を促す文化を作ることが解決策です。」 |
| 「現場が忙しくて作る時間がない」 | 「時間がないのは、マニュアルがないことで発生している非効率(OJT、手戻り、ミスのフォロー)が原因かもしれません。未来への投資として考えませんか?」 |
| 「スターバックスはマニュアルがないらしい」 | 「スターバックスにはマニュアルの代替となる強力な企業文化、理念、徹底した研修制度があります。それらと同等の仕組みを我が社は持っているでしょうか?」 |
マニュアル化を推進すべき組織・不要な組織
マニュアルの必要性は、企業の規模や業種、文化によって大きく異なります。
自社がどちらのタイプに近いかを見極めることが、適切な人材育成や業務改善に繋がります。
一般的に、業務の標準化と品質の均一化が事業の成功に直結する組織では、マニュアル化を積極的に推進すべきです。
一方で、個人の裁量や創造性が価値の源泉となる組織では、詳細なマニュアルはむしろ足かせになる可能性があります。
マニュアル化を推進すべき組織の例
- 飲食・小売チェーン店:どの店舗でも同じ品質の商品・サービスを提供する必要がある。
- 工場・製造業:安全規則や作業手順の遵守が、製品の品質と従業員の生命に直結する。
- コールセンター:応対品質を一定以上に保ち、顧客満足度を維持する必要がある。
- 従業員の入れ替わりが激しい組織:短期間で新人を戦力化する必要がある。
マニュアル化が比較的不要な組織の例
- 少数精鋭の専門家集団:各々が高い専門性を持ち、自律的に業務を遂行できる。
- 研究開発部門やデザイン事務所:創造性や試行錯誤が重視され、手順を固定化することがイノベーションを阻害する。
- スタートアップ企業(初期段階):業務プロセスが固まっておらず、日々変化する状況に柔軟に対応する必要がある。
マニュアルを作りたがる人との共存
この記事では、マニュアルを作りたがる人の心理から、その能力を活かす方法までを多角的に解説してきました。
彼らを「融通が利かない面倒な人」と捉えるか、「組織の知識を体系化してくれる貴重な人材」と捉えるかで、職場環境は大きく変わります。
マニュアルを作りたがる人の特性を正しく理解し、その能力を組織のために最大限に活かすことで、あなたの職場にとってかけがえのない存在となるでしょう。
最後に、この記事のたいせつなポイントをまとめます。
- マニュアル化の目的は業務の標準化と効率化、属人化の防止にある
- マニュアル作りが得意な人は論理的思考力と他者への配慮を兼ね備えている
- 彼らの心理の根底には不確実性への不安やコントロール欲求がある場合も
- 過剰なマニュアル作成は心理的安全性の欠如など組織側の問題も示唆する
- 「マニュアル人間」の短所だけでなく、業務品質を安定させる長所にも目を向ける
- マニュアルを作れない人は、構造化が苦手なだけで、直感力に優れる場合がある
- 新人にマニュアルを作らせることは、優れた教育手法となり得る
- 作りすぎな同僚には、目的や優先順位に焦点を当てて対話する
- 現場で使われるマニュアルは、検索性と更新性を重視することが重要
- 最新ツールを活用すればマニュアル作成は劇的に効率化できる
- 創造性や高度な判断力が求められる仕事はマニュアル化に向かない
- マニュアルへの過度な依存は、従業員の思考停止を招くリスクがある
- マニュアルを「守破離」の「守」と位置づけ、創造的な活用を目指す
- マニュアル不要論には、データと論理で費用対効果を示して対応する
- マニュアルを作りたがる人の能力を尊重し、適材適所で活かすことが共存の鍵