「何度言っても言うことを聞かない部下がいる」
「部下にストレスを感じている」
「最近、部下とのコミュニケーションがうまくいかない」
管理職として、このような悩みを抱えている方は少なくないでしょう。
年上の部下であったり、逆にプライドの高い優秀な部下であったりと、その背景や心理は様々です。
言うことを聞かない部下に対して、「もしかして病気なのでは?」「これ以上は無理だから、辞めさせる?、あるいはクビにするしかないのか」と、極端な考えが頭をよぎることもあるかもしれません。
しかし、部下を一方的に無能だと決めつける前に、一度立ち止まって考えてみてください。
部下のその態度は、もしかしたら「何かを変えてほしい」という、不器用なSOSなのかもしれません。
そして、その変化のきっかけは、わたしたち上司自身の、ほんの少しの視点の変化にあることも少なくないのです。
ダメな部下とダメな上司には、しばしば共通する特徴が見られます。
この記事では、言うことを聞かない部下を放置することの危険性を解説し、その根本的な原因を解き明かします。
そのうえで、上司として取るべき具体的な対応策を紹介しますので、仕事環境を改善していきましょう。
- 部下が指示を聞かない根本的な原因と心理
- 上司自身の行動やマネジメントを見直すための視点
- 部下のタイプや状況に応じた具体的な対処法
- 部下を放置することがもたらすチーム全体へのリスク
言うことを聞かない部下を放置するリスクと背景
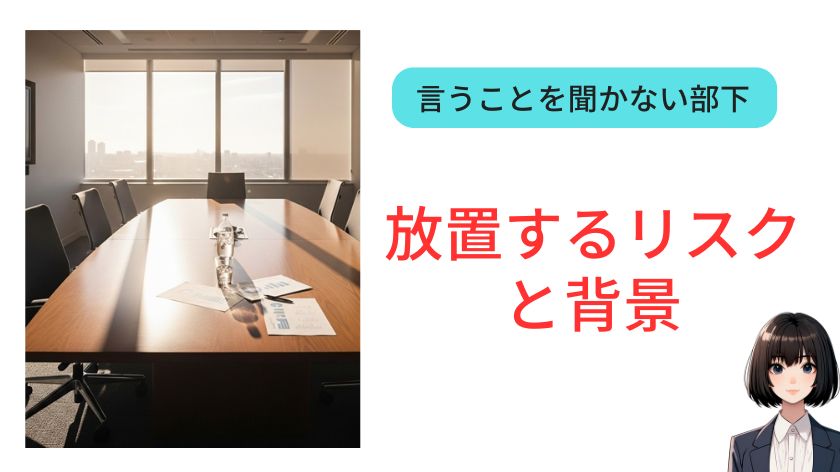
- 部下が言うことを聞かない心理とは?
- 部下の「困った行動」は、上司の「無意識の言動」を映す鏡かもしれない
- 何度言っても言うことを聞かない部下の本音
- 年上の部下が反発する理由と対処法
- 優秀な部下が指示を聞かないときのサイン
部下が言うことを聞かない心理とは?
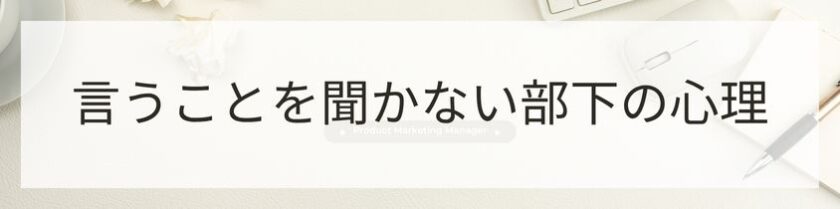
部下が指示に従わないとき、その背景には単なる反抗心だけでなく、様々な心理が隠されています。
これを理解しないままでは、効果的な対策を打つことはできません。
多くの場合、その根底には「上司への信頼感の欠如」や「指示内容への不納得」が存在します。
例えば、部下は「この上司の指示に従っても、正当に評価されない」「そもそも、この上司は自分のことを見てくれていない」と感じているかもしれません。
このような状態では、どれだけ正しい指示を出したとしても、前向きに受け取ることは難しいでしょう。
また、「なぜこの作業が必要なのか」「もっと効率的な方法があるのではないか」といった、業務内容そのものへの疑問や不満が原因であるケースも考えられます。
部下は、自分が尊重され、自分の意見にも価値があると感じたいのです。
自分のやり方で成果を出してきた経験がある部下なら、なおさらその気持ちは強いでしょう。
上司が一方的に指示を押し付けるだけでは、部下の自律性やモチベーションを奪い、結果として「言われたことしかやらない」「指示されたことにも反発する」という状況を生み出してしまいます。
まずは、部下の行動の裏にある心理を理解しようと努める姿勢が、関係改善の第一歩となります。
部下の「困った行動」は、上司の「無意識の言動」を映す鏡かもしれない
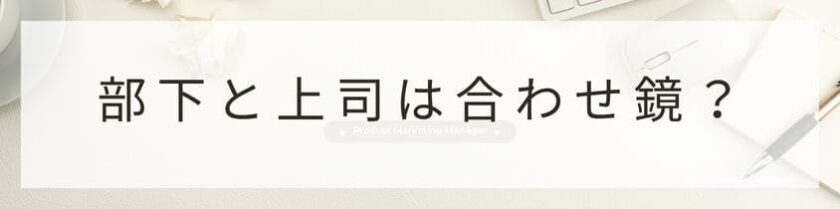
「言うことを聞かない部下」の問題を考えるとき、その責任を全て部下に押し付けてしまうのは簡単です。
しかし、多くの場合、「ダメな上司」の存在が「ダメな部下」を生み出しているという真理があります。
部下は上司の鏡と言われるように、上司のマネジメントスタイルが部下の行動に直接的な影響を与えているのです。
| ダメ上司 | ダメな部下 | |
|---|---|---|
| 指示・命令 | 指示が曖昧・一貫性がない・感情的 | 指示待ち・自分で考えない・反発する |
| コミュニケーション | 部下の話を聞かない・一方的に話す | 報告しない・相談しない・心を閉ざす |
| 責任 | 責任を部下に押し付ける・失敗を認めない | 言い訳が多い・責任感がない |
| 姿勢 | 自分は特別だと思っている・学ばない | 成長意欲がない・現状維持で満足 |
この表からもわかるように、上司の行動の裏返しが、部下の行動です。
合わせ鏡になっています。
例えば、上司が部下の話に耳を傾けず、一方的に指示を出すばかりであれば、部下が「何を言っても無駄だ」と感じて心を閉ざします。
上司が責任を部下に押し付けると、部下は他の人のせいにして言い訳します。
このような状態になると、次第に何も報告・相談しなくなるのは当然の結果と言えるでしょう。
わたしたち上司も、気づかぬうちに「聞くモード」ではなく「指示するモード」になっていることがありますよね。
良かれと思ってしたアドバイスが、意図せず部下のやる気を削いでしまっているとしたら、それはとても悲しいすれ違いです。
一度、部下の視点に立って自分の行動を見つめ直してみましょう。
何度言っても言うことを聞かない部下の本音
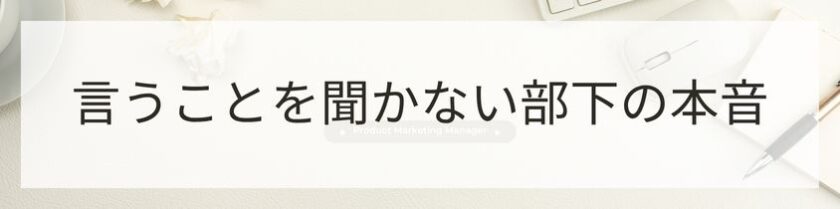
一度や二度ではなく、何度注意や指導をしても、全く態度を改めない部下がいますよね。
このような状況では、上司としても疲弊し、「どうして分かってくれないんだ」と途方に暮れてしまうことでしょう。
しかし、その頑なな態度の裏には、部下なりの「本音」や「言い分」が隠されていることがほとんどです。
多くの場合、彼らは単に指示を拒否しているのではありません。
「指示の内容に納得できていない」のです。
彼らの頭の中は、次のような不満や疑問で満ちています。
- そのやり方は非効率的だ。もっと良い方法があるのに…
- 現場のことを何も分かっていない上層部の方針には従えない
- なぜこの目標を達成する必要があるのか、目的が理解できない
- 結局、上司の自己満足のためにやらされているだけではないか
これらの本音を無視して、ただ「指示だからやれ」と繰り返しても、関係は悪化する一方です。
彼らは、自分が機械の駒ではなく、意思を持った人間として扱われることを望んでいます。
たとえ最終的に上司の指示に従うことになったとしても、その前に一度、自分の意見を聞いてほしい、考えを理解してほしい、という承認欲求があるのです。
もちろん、全ての言い分を受け入れる必要はありません。
しかし、一度立ち止まって「なぜ彼女は納得できないのだろう?」と考えてみること、そして「君の意見も聞かせてほしい」と対話の場を設けることが、固く閉ざされた部下の心を開く鍵となります。
年上の部下が反発する理由と対処法
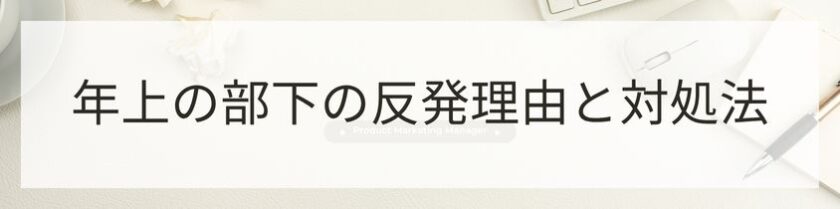
自分よりも社歴が長かったり、人生経験が豊富だったりする「年上の部下」への対応は、多くの管理職が頭を悩ませる問題です。
年下の上司からの指示に対して、素直に従わなかったり、時には公然と反発したりするケースも見られます。
年上の部下が反発する主な理由
彼らが反発する背景には、単なるやりにくさだけではなく、プライドや経験への自負が大きく関わっています。
「こんな若造に指図されたくない」「俺の方がこの仕事についてはよく知っている」という気持ちが、素直な態度を妨げているのです。
役職の上では部下であっても、一人の人間としての尊厳を軽んじられることには強い抵抗を感じます。
効果的な対処法
年上の部下と良好な関係を築き、チームの一員として力を発揮してもらうためには、上司側からの歩み寄りが不可欠です。
重要なのは、役職を振りかざすのではなく、相手への敬意を行動で示すことです。
具体的なコミュニケーションのポイントはこちらです。
- 敬意を示す
「〇〇さんの方が経験豊富かと思いますが、この点についてご意見いただけますか?」など、相手の経験や知識を尊重する言葉を選ぶ - 頼る・任せる
指導が難しい業務や若手へのアドバイス役など、彼らの経験が活きる役割を意識的に任せることで、存在価値を認める - 相談する
指示・命令の形ではなく、「この件、どう進めるのが最善だと思いますか?」と相談の形で意見を求めることで、相手のプライドを尊重しつつ、主体的な協力を引き出す
絶対にやってはいけないのは、「くん」呼びとか呼び捨てです。
いくら上司だからといって、自分よりも年齢が上の人にこれをしたらとても失礼ですし、敬意を欠く態度です。
逆に、年下に対しても、「さん」付けで呼んだほうが社会人的に認められます。
変にへりくだる必要はありませんが、「あなたの力が必要です」というメッセージを伝え続けることが、信頼関係の構築につながります。
彼らを敵対視するのではなく、チームの貴重な戦力として尊重する姿勢こそが、問題を解決する鍵となります。
優秀な部下が指示を聞かないときのサイン
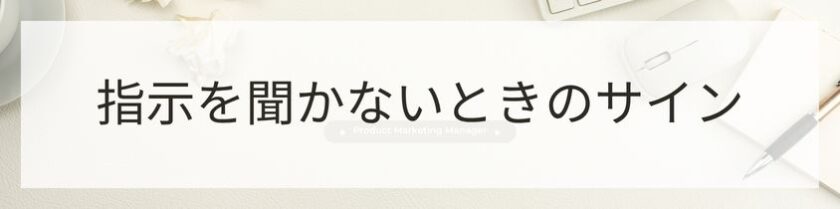
一見すると問題行動に思える「指示を聞かない」という態度も、部下が優秀である場合に限っては、別の意味を持つことがあります。
能力が高く、仕事への意欲もある部下が反発するとき、それはチームやあなた自身にとって重要な「サイン」である可能性が高いのです。
彼らが指示に従わないのは、単なるわがままではありません。
その行動の裏には、以下のようなポジティブな動機が隠れていることがあります。
- より良い方法を知っている
上司の指示よりも効率的、あるいは効果的なアプローチを考えている - 指示に論理的な矛盾を感じる
指示の目的や背景に納得できず、より合理的な判断を求めている - 成長意欲の表れ
より裁量のある仕事や、難易度の高い課題に挑戦したいと考えている
このような部下に対して、頭ごなしに「言うことを聞け」と押さえつけるのは最悪の対応です。
彼らのモチベーションを著しく低下させるだけでなく、貴重な改善提案やイノベーションの機会を潰してしまうことになりかねません。
最悪の場合、成長できる環境を求めて離職してしまうリスクもあります。
もし優秀な部下が反発してきたら、それはチャンスです。
「なぜそう思うのか?」「君ならどうする?」と問いかけ、彼らの意見に真摯に耳を傾けてみてください。
そこには、あなた自身やチームが一段階成長するためのヒントが隠されているはずです。
もちろん、最終的な意思決定は上司であるあなたが行う必要があります。
しかし、彼らの意見を一度受け止め、議論することで、より良い結論にたどり着けるだけでなく、部下との信頼関係も深まります。
優秀な部下の「反発」は、恐れるべきものではなく、むしろ歓迎すべきサインと捉える視点が大切です。
言うことを聞かない部下を放置せず育成する方法
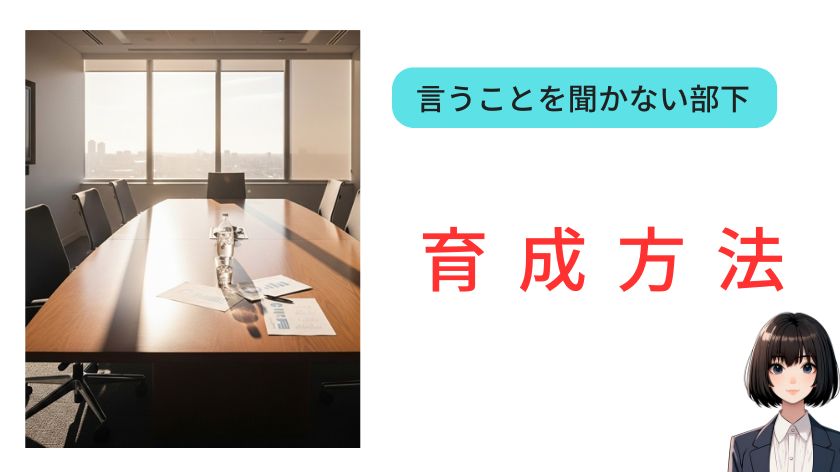
- 部下の態度は病気なのかと疑う前に
- 部下にストレスを与えてしまう上司の言動
- 部下を無能と決めつけてしまう危険性
- 正しい部下の扱い方と対応の基本
- 辞めさせるクビという最終手段の前に
- 部下を”ゲームの主人公”に変える!
- 「答え」を教えるな、「問い」を投げかけよ。
- 「作業指示」から「役割付与」へ。
- まとめ:言うことを聞かない部下の放置
部下の態度は病気なのかと疑う前に
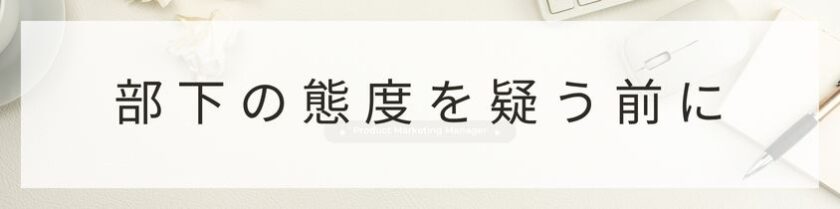
何を言っても響かず、コミュニケーションが全く成立しない部下を前にすると、「もしかしたら、発達障害などの病気が原因なのではないか」と考えてしまうことがあるかもしれません。
ネットで情報を検索し、部下の行動を何らかの障害に当てはめて納得しようとすることも、ある意味で自然な心理かもしれません。
そう考えてしまうお気持ちは、痛いほどよく分かります。
他に原因が見つからず、藁にもすがる思いですよね。
ですが、私たちが医師ではない以上、その可能性について言及することは、問題の本質を見えにくくしてしまうかもしれません。
たとえ本当に何らかの特性があったとしても、それを理由に「仕方がない」と諦めてしまっては、職場環境は改善されないのです。
まず目を向けるべきは「環境」とあなた自身です。
部下の問題行動を個人の資質のせいにする前に、まず問うべきは「その問題行動を許容し、成立させてしまっている職場環境」そのものです。
なぜ、その部下は指示に従わなくても、これまで働き続けることができたのでしょうか。
その行動を改めなくても困らない状況を、誰が作ってきたのでしょうか。
ベクトルを部下個人に向けるのではなく、自分たち、つまり上司やチーム、会社の体制に向けてみましょう。
指示系統は明確か、ルールは公平に運用されているか、問題行動に対して然るべき対応が取られているか。多くの場合、改善すべきは部下本人よりも、彼を取り巻く環境の方なのです。
安易な個人の資質という疑念は一度脇に置き、職場全体の機能不全を疑う視点を持つことが重要です。
部下にストレスを与えてしまう上司の言動
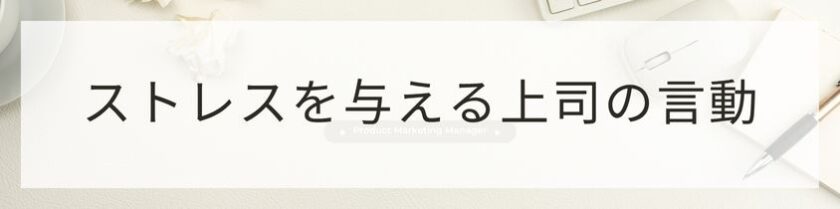
部下が言うことを聞かない原因の一つに、上司が気づかぬうちに部下に過度なストレスを与えているケースがあります。
上司としては「部下のためを思って」指導しているつもりでも、そのやり方が部下の心を追い詰め、反発心や無気力につながっているのかもしれません。
特に注意すべきなのは、以下のような言動です。
- マイクロマネジメント
仕事の進め方を細かく監視し、部下の裁量を一切認めない。これは部下の自主性を奪い、「言われたことだけやればいい」という思考停止を招きます。 - 感情的な叱責
人前で怒鳴りつけたり、人格を否定するような言葉を使ったりする。これは恐怖心しか植え付けず、信頼関係を完全に破壊します。 - 一貫性のない指示
言うことがコロコロ変わり、部下を混乱させる。上司への不信感を増大させます。 - 結果至上主義
プロセスや努力を一切評価せず、結果だけで判断する。部下は挑戦を恐れるようになり、失敗を隠すようになります。
かつての名将、山本五十六はこう言いました。
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ
話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず
これは、まさに理想のリーダーシップを示しています。
一方的に指示するだけでなく、自ら手本を示し、部下の実践を見守り、良い点を認めて褒める。
このプロセスが、部下の自発的な成長と信頼関係を育むのです。
もし部下との関係に悩んでいるなら、一度自分の普段の言動が部下にどのような影響を与えているかを振り返ってみましょう。
良かれと思ってやっていることが、実は大きなストレスの原因になっている可能性があります。
部下を無能と決めつけてしまう危険性
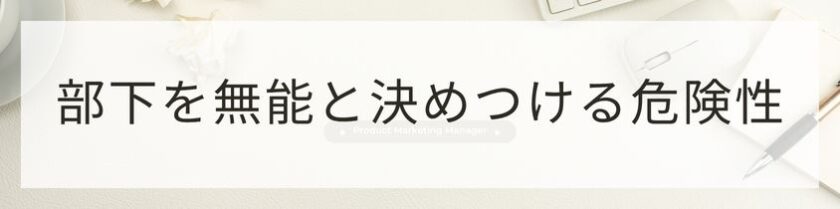
何度指導しても成果が出ない部下に対し、「もう、これ以上どうしようもない」と、心が折れそうになる瞬間があります。
上司にとって一種の思考停止であり、非常に危険な兆候です。
一度「無能」と見なしてしまうと、その部下の良い点や成長の可能性を見る努力を放棄してしまうからです。
人間は、他者から期待されることで成長する側面があります。(ピグマリオン効果)
逆に、上司から「こいつはダメだ」と思われていることを感じ取った部下は、セルフイメージが低下し、ますますパフォーマンスが悪化するという悪循環に陥ります。(ゴーレム効果)
これは、上司が自らの手で「無能な部下」を作り出していることに他なりません。
その部下は、本当に無能で、能力が低いのでしょうか。
もしかしたら、その人の特性と現在の仕事内容が合っていないだけかもしれません。
あるいは、上司であるあなたの指導方法が、その部下には適していない可能性もあります。
- 大勢の前で話すのは苦手だが、データ分析は得意かもしれない
- 新規開拓営業は苦手だが、既存顧客との関係構築は得意かもしれない
- あなたの指示の出し方では理解できないが、別の伝え方をすれば理解できるかもしれない
「無能」という一言で片づける前に、その部下の特性を多角的に観察し、適材適所を考えることが管理職の重要な仕事です。
そのための管理職といえるかもしれません。
部下の可能性を信じず、その芽を摘んでしまうことは、チームにとって大きな損失であり、上司としての責任を放棄する行為と言えるでしょう。
正しい部下の扱い方と対応の基本
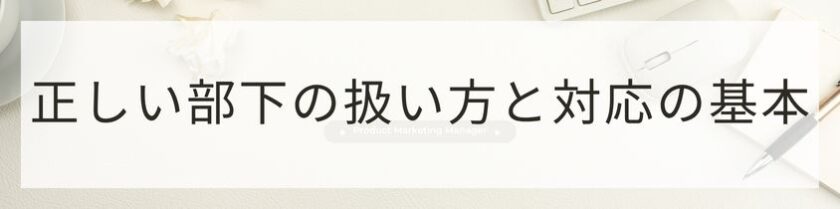
言うことを聞かない部下を変えようとするとき、多くの管理職が「どうすれば彼を説得できるか」と考えがちです。
しかし、根本的に重要なのは「説得」ではなく、「部下自身の行動に責任を負わせる」という毅然とした仕組みと姿勢です。
会社の業務命令に従わないのであれば、その結果として不利益を被るのは、本来、部下自身であるべきです。
しかし、多くの職場では、真面目に働く周囲の社員がその尻拭いをし、問題を起こした本人は全く困らない、という歪んだ構造が生まれています。
この「困るべき人が困っていない」状況こそが、問題行動を助長させているのです。
具体的な対応の流れ
- 事実確認と意思確認
まず、部下が指示に従えないという事実を冷静に確認します。「〇〇という業務指示について、納得できず、実行できないということで間違いないか?」と、脅しにならないよう穏やかに、しかし明確に問いかけます。 - 判断の委任
「これは会社の正式な業務指示です。従うか従わないか、最終的にはあなた自身が決めてください」と、判断を部下本人に委ねます。 - 結果の明示
「もし、業務命令に従わないという選択をするのであれば、就業規則に基づき、人事評価や処遇について然るべき対応を検討することになります。その点は理解しておいてください」と、行動がもたらす結果を客観的に伝えます。
こう話すことで、おそらく相手から反論されるはずですので、それが現状おもってる不満です。
それを一つずつ解決していけば良いんです。
このような対応は、一見すると冷たいように感じられるかもしれません。
しかし、これは部下を一人の責任能力ある大人として対等に扱う行為です。
いつまでもわがままを許容し、成長の機会を奪うことの方が、よほど無責任で冷たい対応と言えるでしょう。
「あなたと一緒に働きたいからこそ、ルールは守ってほしい」という、愛情に基づいた毅然とした態度が求められます。
このプロセスを通じて、部下に「自分の行動には責任が伴う」ことを自覚させることが、真の成長を促す第一歩となります。
▶ 人材育成への活用方法(厚労省)
辞めさせる、クビという最終手段の前に
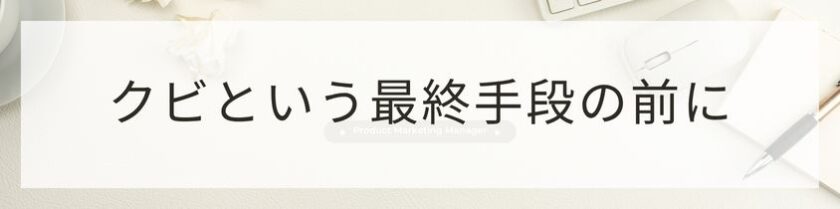
あらゆる指導や対策を講じても、部下の問題行動が改善されず、チームの秩序を著しく乱すような状況に至る場合があります。
そんなときは、最終手段として「退職勧奨」や、さらに重い「解雇(クビ)」を考えざるを得ない局面が来るかもしれません。
しかし、この段階に進むには、極めて慎重な判断と適切な手順が求められます。
安易な解雇は、不当解雇として法的なトラブルに発展するリスクが非常に高いためです。
単に「言うことを聞かないから」という理由だけで、社員を一方的に解雇することはできません。
最終手段を検討する前に、必ず確認すべきことはこちらです。
- 指導・注意の記録は十分か
いつ、誰が、どのような問題行動に対し、具体的にどう指導したか。その結果、改善が見られたか。これらを客観的な証拠(メール、面談記録など)として、時系列で記録・保管しているか - 就業規則との照合
部下の行動が、就業規則のどの条項(懲戒事由など)に該当するのかを明確にできるか - 懲戒処分の段階を踏んだか
問題の程度に応じて、譴責(けんせき)、減給、出勤停止など、解雇よりも軽い懲戒処分を段階的に実施し、改善の機会を与えてきたか - 人事部との連携
これらの対応について、独断で進めず、必ず人事・労務の専門部署と緊密に連携しているか
「辞めさせる」「クビにする」という結論ありきで動くのではなく、「会社として、上司として、やるべきことは全てやり尽くしたか」を自問自答する必要があります。
これらのプロセスを誠実に実行することは、万が一、法的な場での争いになった際に会社を守るだけでなく、上司であるあなた自身が「やり尽くした」という事実と向き合うためにも不可欠な手順です。
では、部下を育成していく方法を3つ紹介します。
部下を”ゲームの主人公”に変える!夢中にさせる目標設定の技術
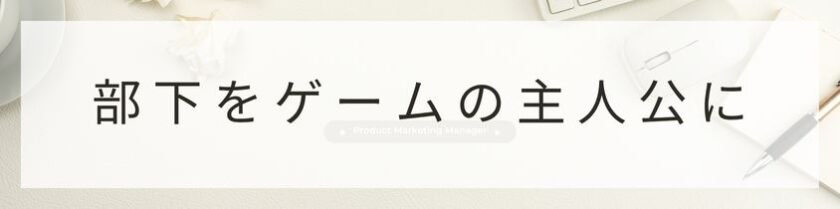
「仕事は、やらなければならないもの」。
この固定観念が、部下のパフォーマンスを縛っているのかもしれません。
もし、部下が自分の仕事を「やらされ仕事」ではなく、「攻略したくなるゲーム」のように感じられたとしたら、その行動は劇的に変わるでしょう。
この「ゲーミフィケーション」の考え方を、部下の育成と目標設定に応用するアプローチは非常に効果的です。
人は、明確なゴール、具体的なルール、そして自分の行動に対する即時のフィードバックがある環境で、驚くほどの集中力と達成意欲を発揮します。
この人間の特性を利用し、部下の内発的動機付けを引き出すのです。
仕事に「ゲーム性」を持たせる3つの仕掛け
難しく考える必要はありません。普段のマネジメントに少しの工夫を加えるだけで、仕事はゲームに変わります。
- 大目標を「スモールステップ(小さなクエスト)」に分解する
「今期中に売上1000万円」というような壮大な目標は、ラスボスのように見えてしまい、手をつけるのをためらわせます。これを「今週はまず見込み客リストを20件作成する」「今日はそのうち3件にアポイントの電話を入れる」というように、毎日・毎週クリア可能な小さなクエストに分解します。クエストをクリアする達成感が、次の挑戦へのエネルギーになります。 - 進捗を「経験値」として可視化する
クリアしたクエストや達成したタスクを、ただの完了報告で終わらせてはいけません。カンバンボードや共有のスプレッドシートなどを使い、チーム全員の「クリアしたクエスト一覧」や「獲得経験値」のように可視化します。自分の成長が目に見えることで、部下はRPGのレベルアップのような喜びを感じることができます。 - 即時的でポジティブなフィードバックを与える
小さなクエストをクリアした際には、間髪入れずに「ナイス!クエストクリアだね!」「今の対応で経験値100ゲットだ」というように、具体的でポジティブなフィードバックを送りましょう。月末の評価面談でまとめて褒めるよりも、日々の小さな承認の積み重ねが、部下のモチベーションを維持させます。
このように、仕事をゲームとして再設計することで、部下は「上司に言われたからやる」のではなく、「次のレベルに進みたいからやる」という、自発的で前向きな姿勢へと変わっていくでしょう。
「答え」を教えるな、「問い」を投げかけよ。部下の思考力を鍛えるコーチング術
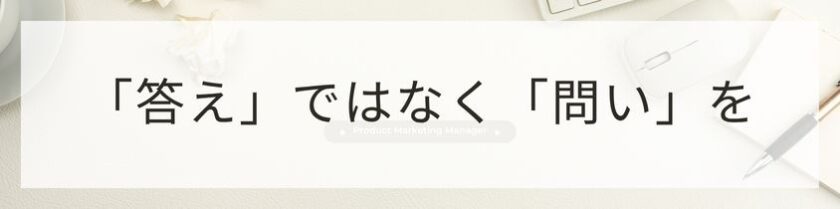
部下から「この件、どうすればいいですか?」と質問されたとき、あなたはどう対応していますか。
良かれと思って、すぐに自分の経験から導き出した「正解」を教えてしまってはいないでしょうか。
しかし、その親切心が、実は部下の思考力を奪い、指示待ち人間を育てる原因になっている可能性があります。
部下の根本的な問題解決能力を育てるためには、上司が答えを教える「ティーチング」から、質問を通じて部下自身に答えを見つけさせる「コーチング」へと、意識的に関わり方をシフトする必要があります。
ティーチングとコーチングの決定的な違い
両者は似ているようで、その目的と効果は全く異なります。
| ティーチング(Teaching) | コーチング(Coaching) | |
| 目的 | 知識やスキルを伝え、正しい答えを教える | 相手の内にある答えや可能性を引き出す |
| コミュニケーション | 上司が話す(一方通行) | 部下が話す(双方向) |
| 上司の役割 | 先生(Instructor) | 伴走者(Partner) |
| 部下への影響 | 依存心、指示待ち | 自律性、オーナーシップ |
例えば、部下が「お客様からクレームが来ました」と報告してきたとします。
ティーチングの上司:「分かった。まずはお詫びの電話をして、それから代替品をすぐに発送して」
コーチングの上司:「そうか、大変だったね。まず、君はこの状況をどうしたいと考えている?」「そのために、どんな選択肢が考えられるだろう?」
コーチング的な関わりは、一見すると時間がかかります。
しかし、部下は「上司に言われたからやった」のではなく、「自分で考えて判断した」という当事者意識を持つことができます。
この経験の積み重ねこそが、指示がなくても自分で考えて動ける、真に自律した人材を育てるのです。
「答え」をぐっとこらえ、「良い問い」を投げかけること。
それこそが、上司に求められる高度な育成スキルと言えるでしょう。
ただし、やりすぎると逆効果です。
何を聞かれても「君はどう思う?」「それはよくないね」など、答えを絶対に言わないと、相手は頭に来てやる気が全く無くなります。
ある程度、方向性を示しながら、ギリギリで正解にたどり着けるような質問で会話をしていくと、効果が高いです。
「作業指示」から「役割付与」へ。部下の当事者意識に火をつける方法
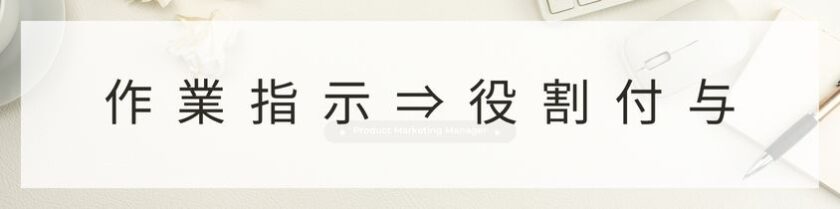
「この資料、30部コピーしておいて」「このデータ、明日までに入力お願い」。
こうした細切れの「作業指示」は、効率的に業務を回しているように見えて、実は部下のモチベーションを静かに削いでいます。
なぜなら、部下は自分が「何のために」その仕事をしているのかを見失い、自分を単なる「作業者」や「上司の手足」だと感じてしまうからです。
部下の当事者意識に火をつけ、自発的な行動を促すためには、単なる「作業(Task)」を指示するのではなく、チームにおける明確な「役割(Role)」を与えることが極めて重要です。
人は「自分はこのチームで〇〇という役割を担っている」という存在意義を感じることで、その役割を全うしようと強い責任感と誇りを持つのです。
「役割」を与えるコミュニケーション術
難しく考える必要はありません。
普段の指示の出し方を少し変えるだけで、部下の意識は大きく変わります。
- 悪い例(作業指示)
「A社の件、トラブルになったから対応しておいて」 - 良い例(役割付与)
「君はうちのチームの『対A社のリレーションシップ担当』だ。今回のトラブルは、今後の関係をより強固にするチャンスでもある。君の対話力を活かして、最高の形でこの事態を収めてくれることを期待している」
後者のように伝えられた部下は、「面倒なトラブル処理」ではなく、「重要なミッション」として仕事に取り組むでしょう。
ポイントは、なぜあなたにその役割を任せるのか、という期待の背景を具体的に言語化することです。
公式な役職とは別に、チームの中でユニークな役割を与えることも有効です。
- チームのムードメーカー
- チームのIT推進リーダー
- 新人たちのメンター役
これは、漫画『ワンピース』や『スラムダンク』を想像してもらえればわかりやすいです。
船長はルフィ、剣士はゾロ、コックはサンジ、ナミは航海士・・・
桜木はリバウンダー、流川はエース、ゴリはリムプロテクター、三井はシューター・・・
あなたのチームの人員が、誰に相当するのかを考えればワクワクしてきませんか?
このように、その人の得意なことや個性に光を当てた役割を与えることで、本人の自己肯定感を高め、チームへの貢献意欲を引き出すことができます。
部下を単なる作業者として扱うのをやめ、チームの重要な役割を担うパートナーとして尊重すること。
その姿勢こそが、彼らの眠っているポテンシャルを最大限に引き出す鍵となります。
まとめ:言うことを聞かない部下の放置はNG!
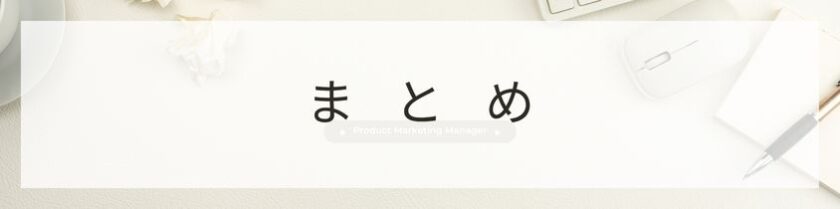
最後に、部下との関係に悩むのは、あなたが管理職という役割から逃げずに、真剣に向き合っている何よりの証拠です。
完璧な上司なんて、どこにもいません。
この記事で紹介したヒントが、あなたの明日からの挑戦を、ほんの少しでも明るく照らす光となれたなら、これほど嬉しいことはありません。
あなたのチームが、最高のチームになることを、心から応援しています。
- 言うことを聞かない部下を放置するとチーム全体の士気が低下する
- 問題行動の原因は部下だけでなく上司のマネジメントにもある
- 部下は上司の言動を映す鏡であることを自覚する
- 部下の行動の裏にある心理や本音を理解しようと努める
- 年上や優秀な部下などタイプに応じた敬意と対応が必要
- 安易に部下を無能や病気と決めつけるのは思考停止である
- ダメな上司の特徴に自分が当てはまっていないか省みる
- 部下に過度なストレスを与える無意識の言動に注意する
- 必要なのは説得ではなく行動に責任を負わせる仕組み
- 業務命令に従わない場合はその結果を客観的に示す
- 行動の判断はあくまで部下本人に委ねる
- 毅然とした態度は突き放しではなく部下の成長を願う行為
- 解雇は最終手段であり慎重な手順と記録が不可欠
- 上司としてやるべきことを全て尽くしたか自問自答する
- 部下との信頼関係構築こそが問題解決の根本である
- 部下をゲームの主人公に変える
- 答えを教えず、問いをなげかける
- 役割付与してチームを作る










