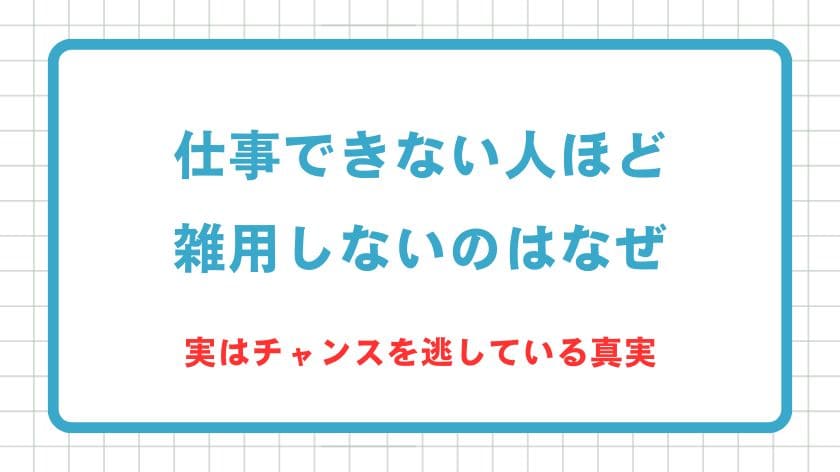「あいつ、雑用しないんだよね」
「仕事できない人ほど、しないよね」
「うちの職場にもいる…仕事できない人」
実は、仕事できない人ほど雑用しないという裏側には、はっきりとした理由があります。
本記事では、雑用をしない人の心理や仕事ができない人に共通する特徴を深掘りします。
例えば、目立つ仕事しかしない人や、平気で雑用を先輩にやらせる後輩、見て見ぬふりをする雑用をやらない同僚など、具体的なケースを紹介します。
そのうえで「こいつ仕事できないな」と思われる使えない社員の特徴や、つい口にしてしまう仕事できない人あるあるの口癖や特徴までを徹底的に解説します。
一方で、雑用という仕事はなく、職場で雑用を進んでやる人の方が仕事ができて、まわりからも評価される現実があります。
雑用ばかり頼まれると、「パワハラじゃないか?」と感じられるかもしれませんが、それは真逆の信頼の証かもしれません。
この記事を読めば、雑用に対する考え方が変わり、明日からの働き方にきっと良い変化が生まれるでしょう。
- 仕事ができない人が雑用をしない根本的な理由
- 雑用をしない人の具体的な行動パターンと心理
- 実は仕事ができる人が雑用を大切にするわけ
- 雑用への考え方を変えて職場の評価を高めるヒント
なぜ仕事できない人ほど雑用しないのか?その理由と特徴
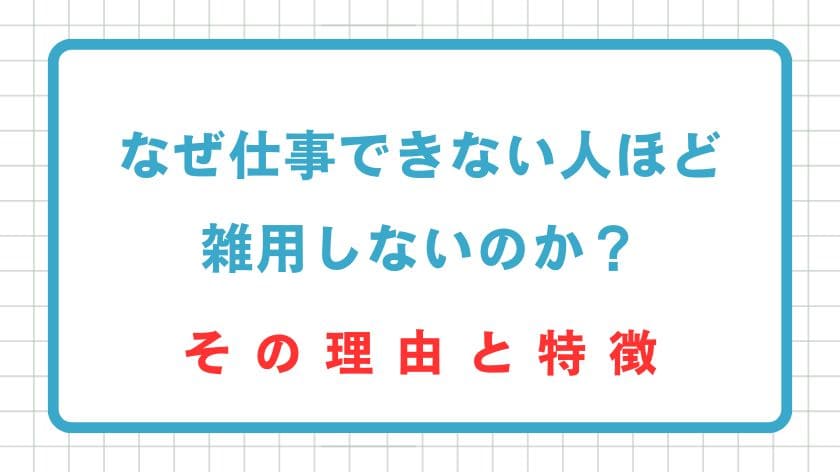
- 仕事できない人ほど雑用しない理由と共通する特徴
- 「こいつ仕事できないな」と思われる使えない社員の特徴と口癖
- 職場にいる雑用をしない人、雑用をやらない同僚
- 目立つ仕事しかしない人と雑用を先輩にやらせる人
- 自分の仕事ができないから雑用もできない!
仕事できない人ほど雑用しない理由と共通する特徴
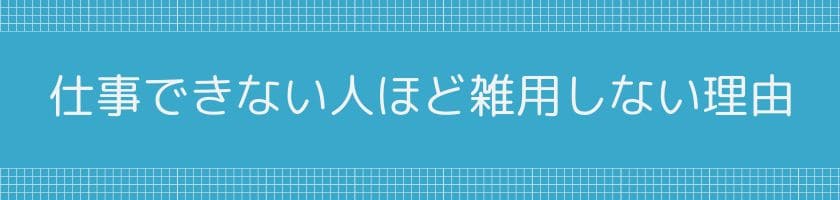
「仕事ができない人ほど雑用をしない」という現象は、多くの職場で聞かれる話です。
これには、大きく分けて2つの理由と、それに伴う共通する特徴が存在します。
一つは、純粋な能力不足やキャパシティの問題です。
自分の担当業務をこなすだけで精一杯で、他のことにまで注意を払う余裕がありません。
このような人は、悪気があるわけではなく、単純に「気づかない」あるいは「手を出す余裕がない」状態にあります。
もう一つは、意識やプライドの問題です。
雑用を「誰でもできる簡単な仕事」「自分のやるべき仕事ではない」と見下しているケースがこれにあたります。
彼らは、より責任のある華やかな仕事だけをやりたがり、地味な作業を軽視する傾向が強いです。
雑用をしない人の主な理由
- 能力・キャパシティ不足:自分の仕事で手一杯で、周囲を見る余裕がない
- 意識・プライドの問題:雑用を価値の低い仕事だと見下している
これらの理由から、仕事ができない人に共通する特徴として、視野の狭さや計画性の欠如が挙げられます。
仕事の全体像が見えていないため、一見地味に見える雑用が、部署全体の業務を円滑に進めるためにどれほど重要かを理解できないのです。
結果として、周囲への配慮に欠けた行動をとってしまい、「仕事ができない」という評価に繋がっていきます。
「こいつ仕事できないな」と思われる使えない社員の特徴と口癖
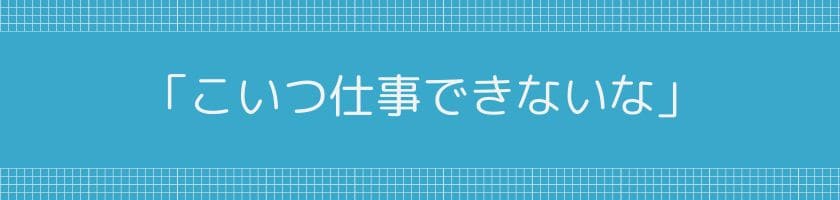
周囲から「こいつ仕事できないな」と思われてしまう人には、行動や口癖にいくつかの分かりやすい特徴が見られます。
これらの特徴は、雑用をおろそかにする姿勢とも密接に関連しています。
仕事ができない人の特徴
まず、計画性がなく、思いつきで行動する点が挙げられます。
タスクの優先順位をつけられないため、重要な業務を後回しにし、納期ギリギリで慌てることが少なくありません。
また、一度犯したミスを何度も繰り返す傾向もあります。
失敗から学ぼうとせず、なぜミスが起きたのかを分析しないため、成長が見られないのです。
さらに、デスク周りやPCのデスクトップが整理整頓されていないことも共通点の一つです。
必要な書類やデータをすぐに取り出せず、無駄な時間を費やしてしまいます。
これは、頭の中が整理できていないことの表れとも言えるでしょう。
仕事ができない人の特徴をまとめると、次のようになります。
| 行動・スキル | 具体的な内容 |
|---|---|
| 計画性 | 優先順位がつけられず、行き当たりばったりで仕事を進める。 |
| 問題解決能力 | 同じ失敗を何度も繰り返し、失敗から学ぼうとしない。 |
| 整理整頓 | 物理的な空間(机)や情報(PC内)の整理が苦手で、業務効率が悪い。 |
| コミュニケーション | 報告・連絡・相談が不足しがちで、周囲との連携が取れない。 |
仕事ができない人あるあるの口癖
口癖にも、その人の思考が表れます。
「でも」「だって」と言い訳から入る人は、自分の非を認めたがらない傾向があります。
また、「忙しい」が口癖の人は、タスク管理能力が低い可能性が高いです。本当に優秀な人は、忙しくてもそれを軽々しく口には出しません。
「後でやります」は先延ばし癖のサインであり、「知りませんでした」は情報収集を怠っている、あるいは当事者意識が欠如している証拠です。
これらの口癖が頻繁に聞かれる場合、周囲からの信頼を得るのは難しいでしょう。
あなたの周りにも、これらの口癖をよく使う人はいませんか?
もし自分自身に心当たりがあるなら、意識して改善することで、周りの評価も変わってくるかもしれません。
参考:働きがいのある職場づくりのために(引用元:厚労省)
職場にいる雑用をしない人、雑用をやらない同僚

職場には、なぜか頑なに雑用をしない人がいるものです。
コピー用紙の補充やシュレッダーのゴミ捨て、給湯室の掃除など、誰かがやらなければならないと分かっていながら、決して自らは動こうとしません。
このような「雑用をやらない同僚」には、いくつかのタイプが存在します。
- 指示待ちタイプ
言われなければ行動できないタイプです。「誰かが気づいてやってくれるだろう」と受け身の姿勢で、自発的に動くことがありません。悪気はないものの、主体性の欠如が問題です。 - 見て見ぬフリタイプ
雑用の必要性に気づいていながら、意図的に無視するタイプです。「これは自分の仕事ではない」と線引きをし、他人に押し付けようとします。自己中心的で、協調性に欠ける傾向があります。 - 「自分は特別」勘違いタイプ
「自分はもっと重要な仕事をするべき人間だ」という根拠のないプライドから、雑用を見下しているタイプです。自分の能力を過大評価し、周囲への配慮を怠ります。
このような雑用をやらない同僚がいると、真面目に雑用をこなしている人が不公平感を抱き、職場の士気が下がる原因になります。
本来、職場の雑務は全員で分担すべきものです。
もし特定の人にばかり負担が偏っている状況であれば、一度チーム内でルールを設けるなどの対策が必要かもしれません。
雑用をしない人への対処法
直接注意するのが難しい場合は、当番制を提案したり、チームミーティングの議題として「業務環境の整備について」話し合う場を設けたりするのが有効です。
個人的な問題ではなく、チーム全体の問題として提起することがポイントです。
目立つ仕事しかしない人と雑用を先輩にやらせる人

雑用をしない人の中でも、特に周囲の反感を買いやすいのが「目立つ仕事しかしない人」と、あろうことか「雑用を先輩にやらせる人」です。
目立つ仕事しかしない人の心理
このタイプは、極端に承認欲求が強く、他人からの評価を常に気にしています。
自分の実績や能力をアピールできる派手な仕事には積極的に取り組みますが、評価に直結しにくい地味な作業は徹底的に避ける傾向にあります。
彼らにとって仕事の価値は「評価されるかどうか」であり、組織への貢献という視点が欠けています。
一見すると仕事熱心に見えるため、上司からの評価は高い場合もあります。
しかし、その裏で地道な作業を他の誰かが肩代わりしていることを、周囲のメンバーは冷めた目で見ているものです。
長期的に見れば、チームワークを乱す存在として信頼を失っていくでしょう。
雑用を先輩にやらせる人の問題点
後輩が先輩に雑用をさせるという状況は、通常では考えにくいですが、実際に存在するケースです。
この背景には、後輩の甘えや社会人としての常識の欠如があります。
先輩が優しいから、あるいは注意しないからといって、その状況に甘んじているのです。
また、「先輩が確認するのが当たり前」といった歪んだ責任感を持っている場合もあります。
このような後輩は、雑用に限らず、主要な業務においても細かな確認を怠り、最終的に大きなミスを引き起こす可能性が高いと言えます。
先輩としては、優しさで許すのではなく、組織の一員としての責任を教える意味でも、言うべきことははっきりと伝える必要があります。
放置することは、本人のためにもなりません。
自分の仕事ができないから雑用もできない!
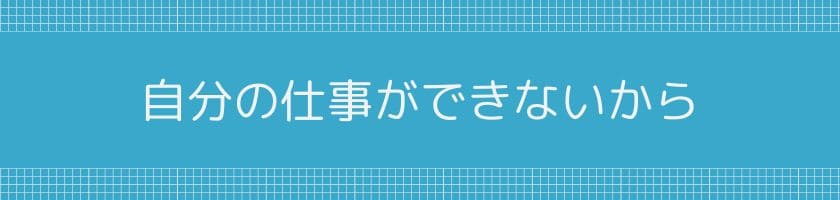
結論から言うと、「自分の仕事ができないから雑用もできない」という側面は間違いなく存在します。
自分の担当業務で手一杯になってしまう人は、そもそも仕事の処理能力や管理能力が低い可能性があります。
そのため、複数のタスクを同時に管理したり、優先順位を判断したりすることができず、結果として雑用にまで手が回らないのです。
逆の視点で見れば、雑用をテキパキと、かつ正確にこなせる人は、タスク管理能力が高いと言えます。
だからこそ、「雑用ができる人は仕事もできる」と評価されるのですね。
もしあなたが「自分の仕事でいっぱいいっぱいで雑用なんてできない」と感じているなら、まずは自分の仕事の進め方を見直す必要があるかもしれません。
タスクをリストアップし、優先順位をつけ、一つひとつ着実にこなしていく訓練を積むことが、結果的に雑用にも対応できる余裕を生み出す第一歩となるでしょう。
「仕事できない人ほど雑用しない」を卒業する思考法
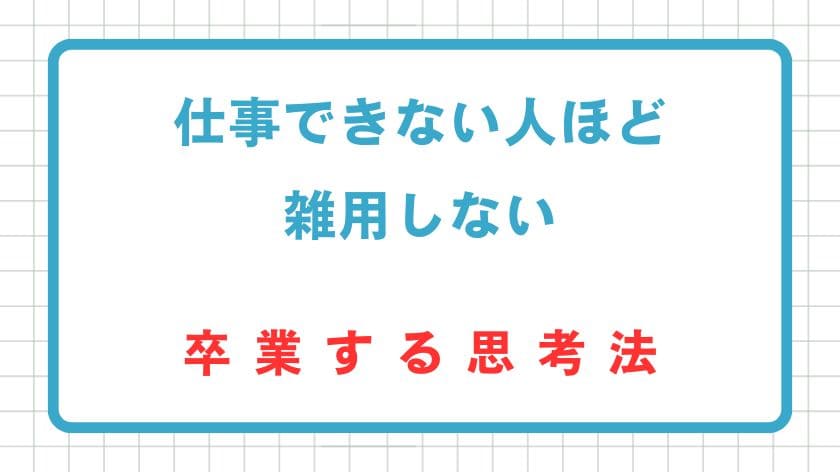
- 「雑用は自分でやれ」と言われる前にできること
- 雑用も仕事。その本当の意味と隠された意味
- 職場では気づいた人が雑用を進んでやるべきか
- 進んでやる人は、実は仕事ができるようになる
- 雑用ばかり頼まれるのはパワハラじゃない理由
- 「できる人」になるための最高のチャンス
- 人間的魅力がアップして他人の見る目もアップ
- 人事評価を上げるための未来への「自己投資」
「雑用は自分でやれ」と言われる前にできること
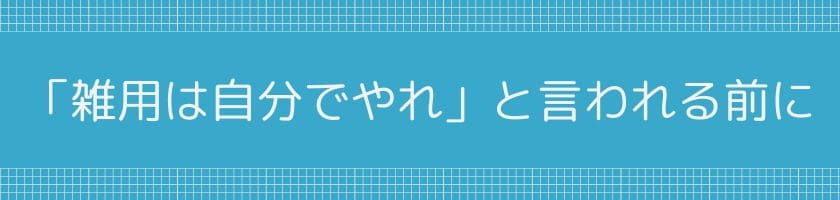
上司や先輩から「雑用くらい自分でやれ」と指摘されてしまう前に、自ら行動を変えることが重要です。
受け身の姿勢から脱却し、主体的に動く意識を持つことで、周囲からの評価は大きく変わります。
まず、自分の仕事の範囲を限定しすぎないことが大切です。
「これは自分の担当ではない」と線を引くのではなく、「チームの仕事」として捉える視点を持ちましょう。
例えば、共有スペースが汚れていたら、自分の業務の合間にさっと片付ける。
コピー用紙が切れそうなら、気づいた人が補充する。
こうした小さな行動の積み重ねが、職場全体の生産性を高め、良好な人間関係を築く土台となります。
また、自分の仕事に余裕が出てきたときには、「何か手伝えることはありますか?」と周囲に声をかける習慣をつけるのも有効です。
たとえ手伝うことがなくても、その気遣い自体が、あなたの評価を高めることに繋がります。
主体的に動くための3つのステップ
- 当事者意識を持つ
チームや部署で起きていることを「自分ごと」として捉える。 - 小さなことから始める
ゴミ捨てや整理整頓など、すぐにできることから行動に移す。 - 周りへの気遣いを忘れない
余裕があるときには、積極的にサポートを申し出る。
「誰かがやってくれるだろう」という考えを捨て、自らが「その誰か」になること。
この意識改革こそが、「雑用をしない人」から卒業するための最も確実な方法です。
雑用も仕事。その本当の意味と隠された意味
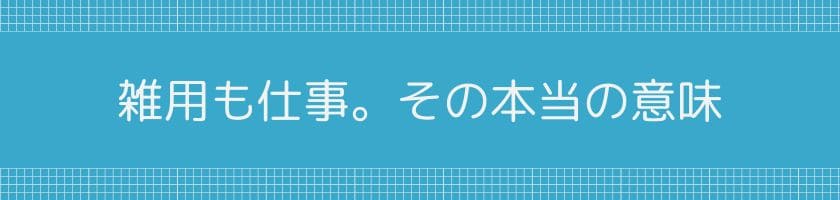
そもそも、「雑用」という名の仕事は本来存在しません。
一般的に雑用と呼ばれる業務は、「雑な用事」ではなく、「その他の様々な用事」を指す言葉です。
そして、これらの業務には、会社の根幹を支える重要な意味が隠されています。
雑用の本当の意味とは
雑用の本当の意味は、組織全体の業務を円滑に進めるための潤滑油としての役割です。
書類の整理、備品の管理、会議室の予約といった業務が滞れば、主要な業務の進行にも遅れが生じます。
誰かがやらなければならない、必要不可欠な仕事なのです。
この大前提を理解すれば、「雑用を見下す」という考えには至らないはずです。
すべての仕事に貴賤はなく、一つひとつの業務が組織を成り立たせているという意識が、プロフェッショナルとして不可欠と言えます。
雑用に隠されたスキルアップの機会
雑用をすることで得られるスキルはこちらです。
- 観察する力
何が不足しているか、誰が困っているかに気づく力が養われます。 - 工夫する力
「どうすればもっと効率的にできるか」を考えることで、改善提案能力が身につきます。 - 実行する力
考えたことをすぐに行動に移す習慣が身につきます。 - 管理能力
備品の在庫管理や経費精算などを通じて、基本的な管理スキルが向上します。
脳科学者の茂木健一郎氏も、著書の中で「細かな雑用を粘り強く、精度高くこなすことで、どんなことでも持続して成果を出す脳の耐性ができる」と述べています。(IQも才能もぶっとばせ! やり抜く脳の鍛え方)
雑用は、仕事の基礎体力を鍛えるトレーニングなのです。
天才と言われたアインシュタインでさえ、研究だけに没頭できる環境ではかえって成果が出なかったという話もあるほど、雑用は重要な役割を担っています。
職場では気づいた人が雑用を進んでやるべきか

「職場の雑用は、気づいた人がやるべきだ」という考え方には、メリットとデメリットの両側面があります。
どちらが良いかは、その組織の文化や状況によって異なります。
「気づいた人がやる」文化のメリット・デメリット
この文化の最大のメリットは、主体性やチームワークの精神が育まれる点です。
全員が「自分ごと」として職場の環境に関心を持つようになり、柔軟でスピーディーな対応が可能になります。
ルールで縛らないため、自発的な行動が促されやすい環境と言えるでしょう。
一方で、デメリットは負担が特定の人に偏りがちになることです。
よく気づき、真面目な人ほど多くの雑用をこなすことになり、不公平感が生じやすくなります。
「自分ばかりが損をしている」と感じる人が増えると、かえって職場の雰囲気は悪化してしまいます。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 気づいた人がやる | ・主体性が育つ ・柔軟でスピーディー | ・負担が偏りやすい ・不公平感が生まれやすい |
| 当番制 | ・負担が公平 ・責任の所在が明確 | ・やらされ感が出やすい ・柔軟性に欠ける |
最適な分担方法とは
理想的なのは、基本的には「気づいた人がやる」という主体性を尊重しつつも、負担が偏らないように配慮する仕組みを取り入れることです。
例えば、ゴミ捨てや掃除など、定期的に発生する業務については緩やかな当番制を導入し、それ以外の突発的な雑務については、気づいた人が協力して対応するといったハイブリッドな形が考えられます。
重要なのは、全員が「雑用はみんなの仕事である」という共通認識を持つことです。
その上で、自分たちの職場に合った最も公平で効率的な方法を、チームで話し合って決めるのが良いでしょう。
進んでやる人は、実は仕事ができるようになる!
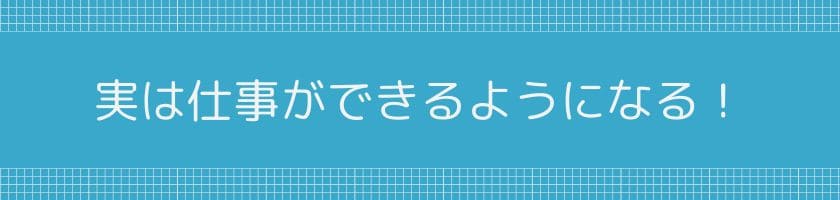
一見すると、雑用に時間を費やすのは非効率に思えるかもしれません。
しかし、自ら雑用を進んでやる人こそ、実は仕事ができる人になるケースが非常に多いのです。
彼らの行動には、優秀なビジネスパーソンになるための共通する特徴が表れています。
第一に、視野が広く、仕事の全体像を把握しようと心がける点です。
彼らは、自分の担当業務だけでなく、チームや部署全体がスムーズに機能するために何が必要かを常に考えています。
だからこそ、コピー用紙の補充といった小さな作業の重要性を理解し、誰かに言われる前に行動できるのです。
第二に、段取り力とマルチタスク能力が高くなることが挙げられます。
自分の仕事を効率的にこなし、余った時間や思考のリソースを他の人の仕事をサポートしようと心がけます。
同僚たちがスムーズに仕事できるための準備をして、全体の生産性を高めているのです。
メジャーリーガーの大谷翔平選手がグラウンドのゴミを拾う姿は有名ですが、これも一流の姿勢の表れです。
「誰かが捨てたゴミ」ではなく「自分が気づいたゴミ」と捉え、当たり前のように行動する。
仕事ができる人の雑用への姿勢も、これと全く同じなのです。
雑用を丁寧に行うことは、周囲からの信頼を積み重ねる行為でもあります。
「あの人に任せれば、細かいところまで気を配ってくれる」という評価は、やがてより大きな仕事を任されるきっかけに繋がっていきます。
雑用への取り組み方は、その人の仕事に対する誠実さを示すバロメーターなのです。
雑用ばかり頼まれるのはパワハラじゃない理由
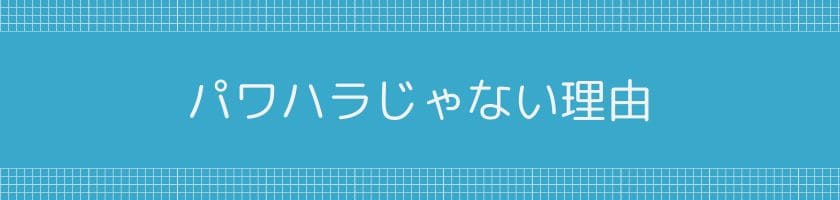
「自分だけ雑用ばかり頼まれる…これはパワハラではないか?」と感じてしまうこともあるかもしれません。
もちろん、意図的に特定の人物をおとしめるための雑用強要もあるかもしれません。
しかし、多くの場合、雑用を頼まれることには、パワハラとは異なる理由があります。
最も大きな理由は、あなたへの「信頼」です。
上司の立場からすると、雑用は「誰にでも頼める仕事」ではありません。
むしろ、「安心して任せられる人」に頼みたいと考えるのが自然です。
上司が雑用を頼む相手に求めること
- 正確性
指示された内容を間違いなくこなしてくれるか。 - スピード
テキパキと効率よく終わらせてくれるか。 - 責任感
嫌な顔をせず、最後までやり遂げてくれるか。
つまり、あなたが雑用をよく頼まれるのだとすれば、それは上司があなたの仕事ぶりを高く評価している証拠である可能性が高いのです。
「この人に頼めば、きっときちんとやってくれる」という期待があるからこそ、声がかかるのです。
ただし「テイカー」には要注意
一方で、自分の利益のために他人を都合よく利用しようとする「テイカー(Taker)」タイプの人からの依頼には注意が必要です。
相手があなたへの感謝や敬意を欠き、単に便利な存在として利用していると感じる場合は、安易に引き受けず、時には断る勇気も必要です。
頼まれた仕事が信頼の証なのか、それとも単なる利用なのかを見極めることは大切です。
しかし、基本的には、雑用を頼まれることはあなたの評価を高めるチャンスですし、期待に応えることで、さらに大きな信頼を獲得していけます。
参考:若年技能者人材育成支援等事業(厚労省)
「できる人」になるための最高のチャンス
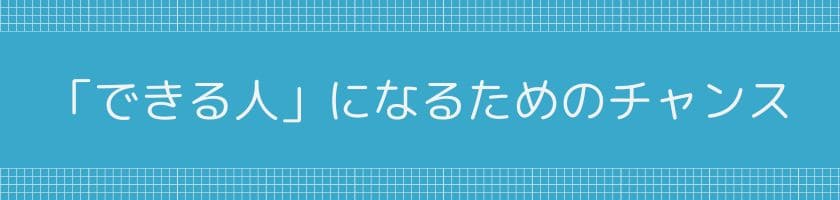
「一人前のビジネスパーソンになりたい」「もっと仕事ができるようになりたい」と考えるなら、まず取り組むべきは「雑用」です。
一見、誰にでもできる単純作業に見えるかもしれませんが、実は雑用こそが、仕事の基本スキルを最も効率的に学べるトレーニングの場だからです。
例えば、複数の部署から頼まれた資料のコピーを期日までに正確にこなすには、どうすれば効率的かを考える「段取り力」や「タスク管理能力」が求められます。
オフィスの備品が切れそうなことに気づき、先回りして補充する行為は、問題が起きる前に対処する「観察力」と「リスク管理能力」の表れです。
このように、雑用の中には仕事の根幹をなすエッセンスが凝縮されています。
そして何より、上司や同僚はあなたのその姿勢を見ています。
地味で目立たない仕事にも真摯に取り組む姿は、「この人は誠実だ」「小さなことでも手を抜かない」という絶大な信頼に繋がります。
仕事における成長は、「スキル」と「信頼」という両輪で成り立っています。
信頼がなければ、そもそもスキルを発揮するチャンス(=責任ある仕事)は与えられません。
進んで雑用を引き受けることは、スキルを磨きながら信頼を積み立てる、最も確実で最高のチャンスなのです。
人間的魅力がアップして他人の見る目もアップ

意外に思われるかもしれませんが、「雑用ができるかどうか」は、異性からの魅力を大きく左右する重要な要素です。
なぜなら、雑用への取り組み方には、その人の人間性やパートナーとして考えた際の魅力が色濃く反映されるからです。
職場で誰かが困っているときにさっと手伝ったり、共有スペースが汚れていたら率先して片付けたりする姿は、「気遣いができる優しい人」という印象を与えます。
それを見た人には、「きっとわたしにもやさしく気遣ってくれる」というイメージが定着するはずです。
さらに、自分のことだけでなく、周囲の状況に目を配れる「視野の広さ」と「心の余裕」は、頼りがいのあるパートナーとして映るでしょう。
「見て見ぬふりをしない」という誠実な態度は、恋愛や結婚といった長期的なパートナーシップにおいて、最も大切な資質の一つです。
また、職場の整理整頓や備品管理といった雑務をテキパキとこなす姿は、無意識のうちに「この人と一緒に生活したら、快適に過ごせそうだ」という家庭的な能力を連想させ、安心感を与えます。
特別なアピールをしなくても、日々の雑用への真摯な態度は、あなたの内面的な魅力を雄弁に物語っています。
もしあなたが異性からの評価を高めたいと考えるなら、まずは身の回りの小さな「誰かがやらなければならないこと」に、進んで取り組んでみてはいかがでしょうか。
人事評価を上げるための未来への「自己投資」

給料を上げたい人は、目先の大きな成果だけを追い求めようとしがちです。
ですが、遠回りに見えて、実は最も確実な給与アップ戦略の一つが「進んで雑用をすること」です。
多くの企業の給与は、「業績評価(目に見える成果)」だけでなく、「能力評価(スキル)」や「情意評価(勤務態度)」といった複数の要素で決定されます。
たとえば、業績は最高なのに、なぜか出世しなかったり、給料がそれほど高くない人もいるのは、そういったことが関係しています。
雑用は、直接的な売上などの「業績」にはなりにくいですが、「協調性」「責任感」「規律性」といった情意評価の項目で、あなたを高く評価させるための格好の材料となります。
上司は、部下の普段の働きぶりをよく見ています。
あなたが上司だったら、誰もが嫌がる仕事を文句も言わずに引き受け、丁寧にこなす部下がいればどう思われますか?
「彼はチームへの貢献意識が高い」「安心して仕事を任せられる」と感じ、人事評価の際に必ずプラスに勘案するでしょう。
この「信頼残高」が貯まっていくと、より責任のあるポジションへの昇進や、重要なプロジェクトへの抜擢の機会が巡ってきます。
責任の重さに応じて給与が上がるのは当然のことです。つ
まり、雑用をこなすことは、目先の評価を地道に積み上げ、将来の大きな昇給・昇進に繋がる布石を打つ行為なのです。
雑用をおろそかにする人は、知らず知らずのうちにこのチャンスを自ら手放していると言えるでしょう。
まとめ:仕事できない人ほど雑用しないのは本当か
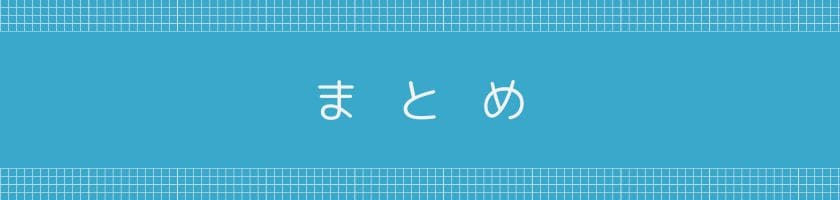
この記事のまとめです。
- 「仕事できない人ほど雑用しない」は多くの職場でみられる現象
- その理由は能力的な問題と意識的な問題に大別される
- 能力不足の人は自分の仕事で手一杯で雑用に気づけない
- 意識が低い人は雑用を価値の低い仕事だと見下している
- 仕事ができない人の特徴に計画性の欠如や同じミスの繰り返しがある
- 「でも」「忙しい」といった口癖は注意が必要なサイン
- 職場には見て見ぬフリをする人や目立つ仕事しかしない人がいる
- 雑用を先輩にやらせる後輩は社会人としての常識が欠如している
- タスク管理能力が低いと自分の仕事も雑用もできなくなる
- そもそも「雑用」という名の仕事はなく、すべてが重要な業務
- 雑用には観察力や工夫力などスキルアップの機会が隠されている
- 雑用を自ら進んでやる人は視野が広く、仕事の全体像を把握している
- 雑用ができる人は段取り力が高く、周囲からの信頼を得やすい
- 雑用をよく頼まれるのは、パワハラではなく信頼されている証拠の場合が多い
- 雑用への取り組み方を変えることが、自身の評価を高める第一歩となる