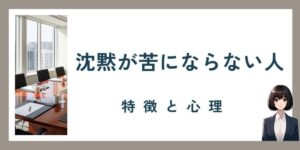「苦手な人に萎縮してしまう」
「怒られると萎縮してしまう」
「苦手な人には何も言えない」
という悩みを抱えていませんか。
特定の上司や先輩など、目上の人に萎縮してしまい、うまく喋れない・・・
その結果、萎縮して仕事ができない、あるいは萎縮してしまって、さらにミスが増えるという悪循環に陥ることもあります。
特定の人に怒られると萎縮する人の多くは、この状況を「直したい」と強く願っています。
しかし、何をどうしたら良いのか、その糸口もよくわからないと悩んでいます。
萎縮しない人との違いはどこにあるのでしょうか。
この記事では、苦手な人を前にすると萎縮してしまう心理的な特徴や原因を解説していきます。
30代・40代のビジネスパーソンが身につけたい具体的な対策と思考法を紹介します。
- なぜ特定の人の前で萎縮してしまうのか、その心理的メカニズム
- 萎縮しやすい人が持つ思考のクセや特徴
- 萎縮の悪循環を断ち切り、「萎縮しない人」に変わるための具体的な思考法
- どうしても状況が改善しない場合の最終的な対策
なぜ苦手な人に萎縮してしまうのか?
- 萎縮しやすい人の心理的な「特徴」
- 怒られると萎縮するのは過去の経験から?
- なぜ、目上の人に萎縮しやすいのか
- 相手の怖さの正体を言語化する
- 萎縮してミスが増えると負のループに
- 萎縮して「喋れない」「仕事ができない」とどうなる?
萎縮しやすい人の心理的な「特徴」
苦手な人を前にすると特に萎縮しやすい人には、いくつかの共通した心理的な特徴があります。
これはあなたの「弱さ」ではなく、一種の「思考のクセ」や「傾向」です。
まず、他者からの評価を過度に気にする傾向があります。
「失敗してはいけない」「悪く思われたくない」というプレッシャーが強すぎるんです。
相手の些細な言動に敏感になっていて、ちょっと強く言われただけで、体が硬直してしまいます。
次に、ミスを「終わり」だと捉えてしまう完璧主義的な側面も関係します。
一度の失敗で自分の価値がすべて決まってしまうかのように感じているはずです。
ミスを極端に恐れるあまり、挑戦的な行動が取れなくなります。
また、責任感が強すぎることも、自分を追い込む原因になります。
と仕事を抱え込み、余裕のない状態で苦手な人と接することで、さらに緊張が高まってしまうのです。
怒られると萎縮するのは過去の経験から?
「怒られると萎縮する人」の反応は、多くの場合、過去の経験が引き金になっています。
苦手な人が、過去に自分を深く傷つけた人物(例えば、厳格な親や教師)と、無意識のうちに重なってしまうのです。
たとえば、子供の頃に、高圧的な態度で怒鳴られたり、人格を否定されるような叱責を受けた経験があるのではないでしょうか。
そういった経験があればあるほど、脳がその状況を「強い脅威」として記憶します。
そして大人になり、似たような雰囲気(大きな声、きつい口調、睨むような表情)を持つ人に遭遇するだけで、当時の恐怖記憶が自動的に呼び起こされ、防御反応として体が萎縮してしまうのです。
これは、あなたの意志とは関係なく作動する脳の安全装置のようなものです。
「またあの時のように傷つけられるかもしれない」
という無意識の恐怖が、あなたの心をガードするために身構えるんです。
なぜ、目上の人に萎縮しやすいのか
特に「目上の人に萎縮」してしまうのには、明確な理由があります。
これは心理学で「権威との葛藤」と呼ばれる問題と関連していることがあります。
多くの場合、幼少期に自分にとっての「権威者」は、父親や母親、祖父母などです。
その人達との関係性で、自分の意見を自由に言えなかったり、支配・コントロールされたりした経験が影響します。
自分の意見や価値観を表明することを諦め、権威者の意向を受け入れてきたのではないでしょうか、
そういった行動で自分を守ってきたパターンが、大人になっても繰り返されるのです。
そのため、上司や取引先といった「立場が上の人」を前にすると、自動的に過去のパターンが発動します。
目上の人と言うだけで、「逆らってはいけない」「口答えしてはいけない」と無意識に言い聞かせるんです。
そうなると、
という恐れが先に立ち、対等な大人同士としてのコミュニケーションが取れなくなってしまうのです。
参考:こころの耳(厚労省)
相手の怖さの正体を言語化する
あなたが「苦手だ」「怖い」と感じている相手は、本当に「怖い人」なのでしょうか。
それとも、あなたが「怖い」と感じているだけなのでしょうか。
この違いを認識するために、まずは相手の「怖さの正体」を客観的に言語化してみましょう。
ただ「怖い」と漠然と捉えている状態では、対処のしようがありません。
以下のように、何が自分を萎縮させるのかを具体的に分析します。
| 怖さのタイプ | 具体的な特徴 |
|---|---|
| ①表情や口調がキツい | 無表情、睨まれているように感じる、語気が強い、声が大きい |
| ②感情の起伏が激しい | 突然キレる、機嫌に波がある、何を言い出すかわからない |
| ③立場や影響力が大きい | 上司・経営者など。評価を握られていることへの恐れ |
このように言語化することで、
と、相手の行動と自分の感情を切り離して考えられるようになります。これが客観視の第一歩です。
萎縮してミスが増えると負のループに
苦手な人を前にして萎縮することの最大の問題点は、パフォーマンスが著しく低下し、「萎縮してミスが増える」という最悪の負のループに陥ることです。
という不安と緊張は、脳のリソースを過剰に消費します。
その結果、普段なら簡単にできるはずの作業に集中できなくなり、注意力が散漫になります。
心臓がドキドキし、手が震え、頭が真っ白になる。
このような状態では、普段はしないようなケアレスミスを誘発しやすくなります。
そして、そのミスを相手に指摘されることで、「やっぱり自分はダメだ」とさらに萎縮し、次もまたミスをしてしまう…。
この悪循環は、あなたの自信を根こそぎ奪い、セルフイメージを著しく低下させてしまいます。
萎縮して「喋れない」「仕事ができない」とどうなる?
萎縮の症状がさらに進むと、報告や相談といった基本的な業務遂行すら困難になる「萎縮して仕事ができない」状態に陥ります。
苦手な上司を前にすると、言いたいことが整理できず、声が小さくなったり、しどろもどろになったりします。
「何を言っているのかわからない」とさらに強い口調で言われ、ますます頭が真っ白になり、ついには「喋れない」状態になってしまうのです。
こうなると、業務上の必要なコミュニケーションが取れなくなります。
報連相が滞り、問題の発見が遅れ、結果としてさらに大きなトラブルに発展しかねません。
萎縮は、単なる「気持ちの問題」ではなく、業務に実害を及ぼす深刻な問題であることを認識する必要があります。
ただし、これはあなただけの問題ではなくて、相手にももちろん問題があります。
あなたをそういった状態にしてしまう上司にも、能力の欠如が見られます。
苦手な人に萎縮してしまう癖をの対処法
- 萎縮する自分を「直したい」あなたへ
- 相手はあなたが作った「虚像」かも
- 「萎縮しない人」の実践思考:課題の分離
- 感情を抜き、事実だけを見る技術
- 萎縮しても話せる「結論ファースト」の型
- 萎縮より「ミスを減らす努力」に集中
- 最終的な「対策」:相談・転職も視野に
- まとめ:苦手な人に萎縮してしまう原因と対策
萎縮する自分を「直したい」あなたへ
まず最初に、「萎縮してしまう自分を直したい」と考えるあなたにお伝えしたいことがあります。
それは、「萎縮してしまう自分」を責める必要はない、ということです。
前述の通り、その反応は、多くの場合、あなたを過去の脅威から守ろうとする脳の正常な防衛反応です。
「自分が弱いからだ」「甘えているだけだ」と自分を責めることは、自己肯定感をさらに下げ、問題を悪化させるだけです。
大切なのは、自分を責めることではなく、「自分にはこういう反応のクセがあるんだな」と客観的に自分のパターンを認識することです。
その上で、
という対策を考えていきましょう。
自分を変えようとするのではなく、「思考のクセ」を見直すことから始めるのです。
相手はあなたが作った「虚像」かも
あなたが「怖い」と感じている相手は、本当に実在するその人でしょうか。
もしかしたら、あなたは「自分が作り上げた虚像(おばけ)」に怯えているだけかもしれません。
私たちは、過去の経験や偏見(バイアス)を通して相手を見てしまいます。
相手の「無表情」を「怒り」と解釈し、「口調の強さ」を「攻撃性」と判断し、「沈黙」を「不満」と決めつけてはいませんか?
一度「この人は怖い人だ」とラベリングしてしまうと、脳はそのラベリングを裏付ける情報ばかりを無意識に集め始めます(確証バイアス)。
その結果、相手が普通にしていることさえも「怖い」証拠として解釈します。
そのため、あなたの中で相手はどんどん怖くなっていき、「巨大な恐ろしい虚像」としてデフォルメされていくのです。
相手はただ仕事に真面目なだけかもしれませんし、単にコミュニケーションが不器用なだけかもしれません。
まずは、自分のフィルターを疑ってみることが大切です。
「萎縮しない人」の実践思考:課題の分離
では、「萎縮しない人」はどのように考えているのでしょうか。
彼らが実践している強力な思考法の一つに、アドラー心理学でいう「課題の分離」があります。
「課題の分離」を使って、相手の課題とあなたの課題を分けてみます。
相手の課題
相手がどんな機嫌でいるか。相手がどんな口調で話すか。相手があなたのことをどう評価するか。
あなたの課題
仕事でミスをしないように最善を尽くすこと。事実を正確に報告すること。相手の言葉から必要な情報を受け取ること。
相手がイライラしていたとしても、それは相手が自分の感情をコントロールできていないという「相手の課題」です。
あなたがその責任を取る必要はありません。
あなたが介入すべきは、自分の課題である「仕事のパフォーマンスを上げること」だけです。
「相手の機嫌」と「自分の仕事」を切り離す。
この思考法は、対人関係のストレスを劇的に減らしてくれます。
感情を抜き、事実だけを見る技術
「課題の分離」を実践するために有効なのが、相手の言動から「感情」を抜き、「事実(テキスト情報)」だけを受け取る技術です。
例えば、上司が強い口調で「なんでこんなミスしたんだ!」と言ったとします。 この時、萎縮してしまう人は、「怒鳴られた(怖い)」「自分はダメだ」という「感情」をダイレクトに受け止めてしまいます。
そうではなく、怒鳴る、怖い顔といった相手の感情を抜いて、相手が何を言おうとしているのかを考えてみます。
すると、あなたを怒鳴りたいのではなくて、『ミスが起きた原因』と『その対策』を求められているということがわかるはずです。
相手は教えることに対して未熟なので、あなたのミスをなるべく早く直させようとして、怒りという感情を顔に出してるに過ぎません。
相手がどんなに感情的でも、あなたが受け取るのは「事実」と「業務上の指示」のみ。
相手はあなたの命を奪うわけでもありませんし、あなたは相手の感情のゴミ箱になる必要はありません。
この練習を積むことで、相手の威圧感に飲み込まれにくくなります。
繰り返します。
相手が怒鳴ったり、きつい口調でなにか言ってきたら、あなたに何をしてもらいたいと言ってるのかを、考えることです。
そのうえで、
と確認してください。
萎縮しても話せる「結論ファースト」の型
ただ、思考法を変えるといっても、長年のクセはすぐには直りません。
「頭ではわかっていても、いざとなると頭が真っ白になって喋れない」という時のために、思考停止しても使える「会話の型」を持っておくことをお勧めします。
それは、「結論 → 理由 → (感謝または謝罪)」というシンプルな型です。
【報告の例】
「(結論)〇〇の件、完了しました。(理由)特に問題はありませんでした。」
【謝罪の例】
「(結論)申し訳ありません。〇〇の件でミスがありました。(理由)確認不足が原因です。今後は〜〜のように対策します。(謝罪)ご迷惑をおかけしました。」
【相談の例】
「(結論)〇〇の件でご相談があります。(理由)A案とB案で判断に迷っています。(感謝)お時間をいただけますでしょうか。」
萎縮すると、言い訳や曖昧な言葉から入ってしまいがちです。
この「型」を準備しておくだけで、頭が真っ白になっても、最低限伝えるべきことを伝えることができます。
萎縮より「ミスを減らす努力」に集中
前述の通り、相手が怒るのには(理不尽な場合を除き)何らかの原因があります。
その多くは、あなたの「仕事上のミス」や「報連相の不足」です。
相手の機嫌を伺うことにエネルギーを使うのはやめましょう。
あなたが集中すべきは、「萎縮しないこと」よりも「ミスをしないこと」です。
相手を「怖い人」と捉えるのをやめ、「仕事に厳しい(=ミスを許さない)人」と捉え直します。
そうすれば、あなたが取るべき行動は「相手に怯えること」ではなく、「相手に指摘されないよう、自分の仕事の精度を上げること」に変わります。
- 作業後のチェックを徹底する。
- わからないことは、怒られる前に「確認」する。
- 報連相を怠らない。
- 一度指摘されたことは、二度と間違えないようにメモを取り、対策する。
仕事によって、やるべきことは変わってくるはずです。
基本的には、同じミスを繰り返さないということです。
あなたの仕事が完璧に近くなれば、相手はあなたを「怒る」理由がなくなります。
萎縮するエネルギーを、自己研鑽と業務改善に振り向けることが、最も建設的な解決策です。
最終的な「対策」:相談・転職も視野に
これまでの対策を試みても、どうしても萎縮が改善しない。
あるいは、相手の言動が明らかに「指導」の範囲を超えた「パワハラ」や「人格否定」である場合。
その場合は、我慢する必要は一切ありません。
あなたの心身の健康が限界を迎える前に、最終的な対策として「環境を変える」ことを真剣に検討してください。
- 第三者に相談する
まずは、信頼できる同僚や、別の上司、人事部、社内の相談窓口に相談しましょう。あなた一人で抱え込むのをやめ、状況を客観的に判断してもらうことが重要です。(参考:法テラス) - 異動を願い出る
可能であれば、その人がいない部署への異動を願い出るのも現実的な解決策です。 - 転職する
職場の空気全体がピリついていたり、相談しても会社が動いてくれない場合は、その環境自体があなたに合っていません。それは「逃げ」ではなく、自分を守るための「戦略的撤退」です。
仕事や会社は修行じゃないです。
どうしても耐えられなかったら、他の会社に逃げることも選択肢の一つになります。
あなたの心と体を守れるのは、あなただけです。
まとめ:苦手な人に萎縮してしまう原因と対策
「苦手な人に萎縮してしまう」という悩みは、だれでも感じています。
苦しいときには、思考法と行動を変えることで、心が少し軽くなるかもしれません。
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 萎縮しやすいのは、評価を気にする、完璧主義、責任感が強いといった心理的特徴がある
- 過去に怒られたトラウマや、親など目上の人との関係(権威との葛藤)が原因の場合も多い
- まずは相手の「怖さの正体」(口調、表情など)を言語化し客観視する
- 萎縮はパフォーマンスを低下させ「ミスが増える」という負のループを生む
- 「萎縮して喋れない」「仕事ができない」のは深刻な業務支障
- 萎縮する自分を「弱い」と責めず、「思考のクセ」として認識する
- 相手は、あなたが過去の経験から作り上げた「虚像」かもしれない
- 「萎縮しない人」は「課題の分離」を実践している
- 相手の機嫌(相手の課題)と自分の仕事(自分の課題)を切り離す
- 相手の言動から「感情」を抜き、「事実(テキスト情報)」だけを受け取る
- 頭が真っ白になった時のために「結論ファースト」の会話の型を持つ
- 萎縮することより「ミスを減らす」努力にエネルギーを集中させる
- あなたの仕事が完璧になれば、相手は怒る理由を失う
- 最終的な対策として、一人で抱え込まず「相談」や「転職」も重要な選択肢
- 自分を守るための「戦略的撤退」を恐れない