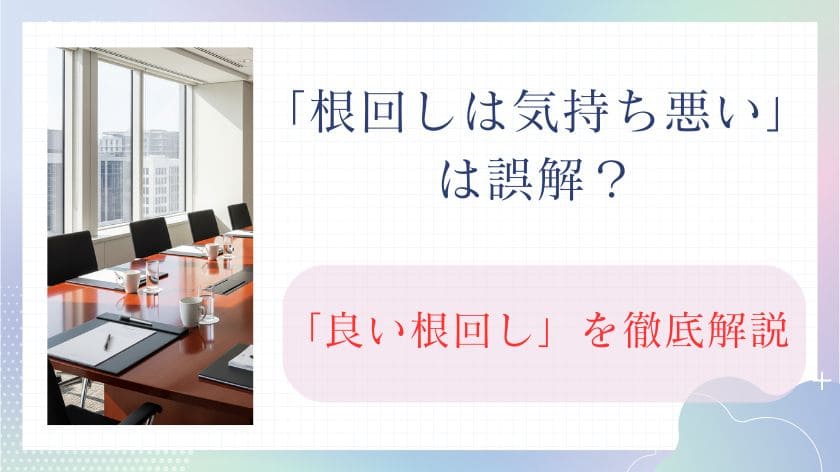「根回しは気持ち悪い」
「根回しするのは汚い」
「根回ししたくない」
と感じていませんか?
仕事で根回しばかりする人の特徴を見ていると、根回しばかりしていることにうんざりすることもあるでしょう。
特に「根回し」というと、 悪い意味での「裏工作」のようなイメージが強く、根回しはめんどくさいと感じます。
その結果、根回しは悪いもので、そのデメリットを強く意識するのも当然です。
また、女性は根回しが苦手というイメージがある一方、根回し上手な女性がいたり、根回しばかりしているように見える女性がいるのも事実です。
しかし、「トヨタ」でも実践されているように、仕事で根回しが上手いことは、重要なビジネススキルなんです。
「根回し」というので嫌悪感がでますが、事前相談とか段取りと言いかえれば、その重要さをおわかりになるはずです。
段取り八分と言われるように、ビジネスでなくてはならないものが、事前相談、段取り、つまり、良い根回しなんです。
この記事では、そのネガティブなイメージを払拭し、生産性を上げるそういった「良い根回し」について解説します。
- 「根回しは気持ち悪い」と感じる心理的理由
- 「悪い根回し」と「良い根回し」の決定的な違い
- 生産性を上げる「良い根回し」の具体的な手順
- 根回しをしない場合の重大なリスク
なぜ「根回しは気持ち悪い」と感じるのか
- 「悪い根回し」とは?
- 「悪い根回し」ばかりする人の特徴
- 仕事で「悪い根回し」ばかりする不健全さ
- 悪い根回しのデメリットとは
- なぜ根回しはめんどくさいのか
「悪い根回し」とは?
「根回し」と聞くと、多くの人が「気持ち悪い」「くだらない」といったネガティブな印象を抱きます。
これは、根回しが昔から持つ「悪い意味」の側面が強くイメージされているからです。
「悪い根回し」とは、主に以下のような行為を指します。
- 裏工作: 会議などの公式な場以外で、一部の人たちだけで物事を決定してしまうこと。
- 不公平感: 事前に話が通っている人とそうでない人が存在し、議論が公平に行われないこと。
- 隠蔽(いんぺい): 反対意見を事前に封じ込め、会議を「決定事項を報告するだけ」の形骸化したものにすること。
いわゆる談合とか、裏取引、インサイダー取引などですね。
オープンな議論をせず、水面下での交渉や社内政治によって物事が決まっていきます。
その様子は、「不誠実だ」「ズルい」という嫌悪感を引き起こします。
会議が「シャンシャン会議(=事前にシナリオが決まっている会議)」になっていると知った時、多くの人は「根回しは気持ち悪い」と感じるのです。
「悪い根回し」ばかりする人の特徴
あなたの周りにも「悪い根回し」ばかりする人はいませんか。
彼らにはいくつかの共通した特徴が見られます。
最大の特徴は、「自分の利益や都合を最優先する」ことです。
彼らにとって根回しは、自分の意見を通すための「社内政治」や「下工作」です。
そのため、以下のような行動を取りがちです。
- キーマンにだけ話を通す: 最終決裁者や影響力のある人物にだけ事前に同意を得て、外堀を埋めようとします。
- 情報を操作する: 自分に都合の良い情報だけを伝え、不利な情報を隠して賛同を得ようとします。
- 「誰々さんも賛成している」と名前を使う: 他の人の権威を利用して、半ば強引に同意を迫ります。
彼らは「仕事ができる」ように見えるかもしれません。
でもその実態は、公明正大な議論を避け、自分の保身や利益誘導のために動いているだけ、というケースが少なくありません。
仕事で「悪い根回し」ばかりする不健全さ
前述のような「悪い根回し」が横行し、仕事が「悪い根回しばかり」になっている職場は、非常に不健全な状態にあると言えます。
なぜなら、組織の風通しが著しく悪くなるからです。
水面下で物事が決まるため、公式な会議の場では活発な議論が起こりません。
若手や立場の弱い人が正しい意見を持っていたとしても、「どうせ上層部で決まっているんだろう」と発言を諦めてしまいます。
結果として、客観的なデータや事実よりも、「声の大きな人」や「根回しが上手い人」の意見ばかりが通るようになります。
これは、組織全体で考える力を失わせ、イノベーションの芽を摘むことにつながります。
優秀な人ほど、こうした理不尽さに嫌気が差し、会社を去っていくリスクも高まるでしょう。
悪い根回しのデメリットとは
悪い根回しがもたらす最大のデメリットは、意思決定者が「裸の王様」になってしまうことです。
決裁者が、根回しによって整えられた「賛成意見」や「都合の良い情報」ばかりに触れていると、現場の実態や潜在的なリスクを正確に把握できなくなります。
異なる視点や反対意見は、より良い意思決定のために不可欠な情報です。
しかし、悪い根回しはこれら の「意見の不一致」を意図的に排除します。
その結果、衆知(多くの人々の知恵)が集まらず、偏った判断や間違った意思決定が下されるリスクが非常に高くなります。
組織としては、短期的に物事がスムーズに進んでいるように見えます。
ですが、長期的には大きな失敗や組織の腐敗につながる、深刻なデメリットを抱えているのです。
なぜ根回しはめんどくさいのか
一方で、多くの人が「根回しは気持ち悪い」以前に、「正直めんどくさい」と感じているのも事実です。
たとえそれが「良い根回し」であったとしても、大きな手間と心理的コストがかかります。
具体的には、以下のような点が「めんどくさい」と感じる理由です。
- 時間的コスト: 会議の前に、関係者一人ひとりにアポイントを取り、個別に説明する時間が必要です。
- 資料作成のコスト: 全体会議用の資料とは別に、説明用の簡易資料やたたき台が必要になる場合があります。
- 心理的コスト: 反対されそうな人に事前に話を通し、意見を調整する作業は、精神的に大きな負担となります。
- 人間関係への配慮: 「誰から先に話を通すべきか」といった順序や、相手のメンツを潰さないような配慮が求められます。
「会議で一度に説明すれば済むことを、なぜわざわざ個別に?」と思ってしまうのは当然の感覚です。
この「めんどくささ」が、根回しという行為そのものを敬遠させる大きな要因となっています。
「根回しは気持ち悪い」を克服する「良い根回し」の方法
- 「根回しなし」で会議に臨むリスク
- 根回しが上手い人の特徴
- 生産性を上げる「良い根回し」の手順
- なぜ女性には根回しが苦手という意識がある?
- 根回し上手な女性と根回しばかりしている人の違い
- トヨタも実践する「根回し」の本当の意味
- まとめ:根回しは気持ち悪い?
「根回しなし」で会議に臨むリスク
「悪い根回しはダメだ」
「根回しはめんどくさい」
と、一切の根回しをせずに会議に臨むとどうなるでしょうか。
実はそこには、「通るべき正しい提案が通らない」という最大のリスクが潜んでいます。
なぜなら、決裁者や関係者は、会議の場で初めてその情報に触れることになるからです。
想像してみてください。
あなたが上司の立場で、部下から「数千万円のコストダウンになる」という触れ込みの設備投資案を、会議の席でいきなり詳細資料と共に提示されたらどうでしょう。
「本当にコストダウンになるのか?」
「他の部署への影響は?」
「予算はどこから出す?」
多くの確認事項が頭に浮かびますが、その場ですべてを理解し、判断するのは不可能です。
時間的なプレッシャーもあり、「よくわからないし、リスクもありそうだから、今回は見送ろう」という判断になってしまう可能性が非常に高いのです。
根回しをしないことは、一見「公明正大」に見えますが、実際には相手に「情報を整理する時間」と「冷静に考える余裕」を与えない、不親切な行為とも言えます。
結果、素晴らしい提案が「説明不足」や「準備不足」という理由で却下されてしまうのです。
根回しが上手い人の特徴
「根回し」は気持ち悪いという印象を覆す、「良い根回し」ができる人、すなわち「仕事が上手い人」には共通する特徴があります。
それは、彼らが根回しを「裏工作」ではなく、「物事を円滑に進めるための調整・段取り」として捉えている点です。
- 人脈が広い
日頃から社内外問わず良好な人間関係を築いており、誰に相談すればよいかを把握しています。 - 相手の立場に立てる
相手が何を懸念し、何を重視するかを想像し、その人に合ったアプローチができます。 - 信頼されている
普段の仕事ぶりや誠実な態度で、「あの人の言うことなら」という信頼を得ています。 - リサーチ力がある
決定権を持つキーパーソンや、その人が重視するポイントを事前に分析しています。
彼らは、自分の意見を通すためではありません。
関係者全員が納得し、プロジェクトがスムーズに進むための「最適な解」を見つけるために根回しを行います。
参考:こころの耳(厚労省)
生産性を上げる「良い根回し」の手順
「悪い根回し」と「良い根回し」は、その目的と手順が全く異なります。
「良い根回し」は、言い換えれば「生産性を高めるための事前相談・段取り」です。
会議を「決める場」ではなく「議論を深める場」にするために、以下の手順を踏みます。
【良い根回し(事前相談)の3ステップ】
- 知ってもらう(たたき台の共有)
まずは関係者に「今、こういうことを考えています」とたたき台(草案)を共有します。「まだ決まっていません」という前提で、事前にインプットする時間を提供します。 - 相談する(意見の収集)
「この案について、〇〇さんのご意見を伺えませんか?」「何か懸念点はありそうでしょうか?」と、「相談」の形で意見や反対意見を事前に収集します。これにより、相手は「尊重された」と感じ、会議での無用な反発が減ります。 - 了承(合意形成)と資料への反映
収集した意見や懸念点への対策を資料に反映させます。会議の場では「事前にいただいたご意見を反映し、論点を〇〇にまとめました」と、最初から深い議論をスタートさせることができます。
この手順を踏むことで、会議の場での「それは何の話だ?」「聞いていない」という無駄な時間をなくします。
その結果、質の高い意思決定(=生産性の向上)が可能になります。
なぜ女性は根回しが苦手という意識がある?
女性は根回しが苦手とよく言われますが、いくつかの要因が考えられます。
これは性別による能力差ではなく、社会的な傾向やイメージが影響している可能性があります。
一つは、前述の通り「根回し=悪」というネガティブなイメージです。
公平性や透明性を重視する人にとって、水面下での調整は「不誠実な行為」と映り、心理的な抵抗感が生まれやすいのです。
また、従来の日本企業における「根回し」が、飲み会やゴルフといった、旧来の男性中心的なコミュニティで行われてきた側面も否定できません。
そうした「古い社内政治」への嫌悪感が、「根回しは苦手だ」という意識につながっている可能性もあります。
根回し上手な女性と根回しばかりしている人の違い
一方で、「根回し上手な女性」も存在します。
彼女たちと、単に「根回しばかり」している人との違いは何でしょうか。
ここでも「良い根回し」か「悪い根回し」かが分岐点となります。
| 根回し上手(良い根回し) | 根回しばかり(悪い根回し) | |
|---|---|---|
| 目的 | プロジェクトの成功、円滑な進行 | 自分の利益、保身、他者の排除 |
| 手段 | 「事前相談」による意見収集と調整 | 「裏工作」による情報の操作と分断 |
| 周囲の印象 | 「段取りが良い」「配慮がある」 | 「社内政治ばかり」「信用できない」 |
「根回し上手」な人は、相手の立場や感情に配慮し、全員にとってのWin-Winを目指す「健全な調整」を行います。
対して「根回しばかり」の人は、自分の利益のために特定の人物を陥れたり、派閥を作ったりする「不健全な社内政治」に終始しがちです。
トヨタも実践する「根回し」の本当の意味
効率化の象徴ともいえるトヨタ自動車。
そのトヨタ生産方式には「7つのムダ」という考え方があります。
興味深いことに、その中には「会議のムダ」「調整のムダ」「上司のプライドのムダ」が含まれています。
トヨタでは、「決まらない会議」や「報告のためだけの資料」はムダだとされています。
さらに、「私は聞いていない」という上司のプライドもムダであり、「情報は上司自ら取りに行きましょう」とされています。
これは、裏を返せば「会議を有意義なものにするための事前の情報共有(=良い根回し)はムダではない」ということを示しています。
「悪い根回し(上司のご機嫌伺い)」は徹底的に排除しつつ、会議の生産性を上げるための「健全な根回し(事前相談・段取り)」は、トヨタのような超効率企業でも重要視されているのです。
まとめ:根回しは気持ち悪い?
「根回し 気持ち悪い」という感情は、多くの場合、「悪い根回し(=不公平な裏工作)」に対して抱くものです。
その感情は、公平性を求める上で非常に健全です。
しかし、その嫌悪感から「一切の事前調整」を拒否することは、ビジネス上大きなリスクを伴います。
この記事の結論として、押さえるべきポイントをまとめます。
- 根回しは気持ち悪いと感じる原因は、不公平な「悪い根回し」のイメージにある
- 「悪い根回し」は、自分の利益のために情報を操作し、組織を腐敗させる
- 根回しばかりする人は、社内政治に終始し、長期的に信頼を失う
- 一方で、一切の根回しをしないと、会議で「情報不足」や「反発」を招く
- 通るべき案も通らなくなるリスクがある
- 仕事ができる人が行う「良い根回し」とは、「事前相談」や「段取り」のこと
- その目的は、関係者の意見を事前に収集し、会議の生産性を上げること
- 良い根回しの手順は「たたき台の共有」「相談ベースでの意見収集」「資料への反映」
- 「女性が根回しが苦手」というのはイメージ先行で、本質は「悪い根回し」への嫌悪感
- トヨタの「7つのムダ」も、会議の生産性を上げるための「事前共有」の重要性を示している
- 「悪い根回し」は徹底して避ける
- 議論を深めるための「良い根回し(事前相談)」は積極的に行うべき
- 「事前相談」は、相手への配慮であり、プロジェクト成功のための必須スキルである