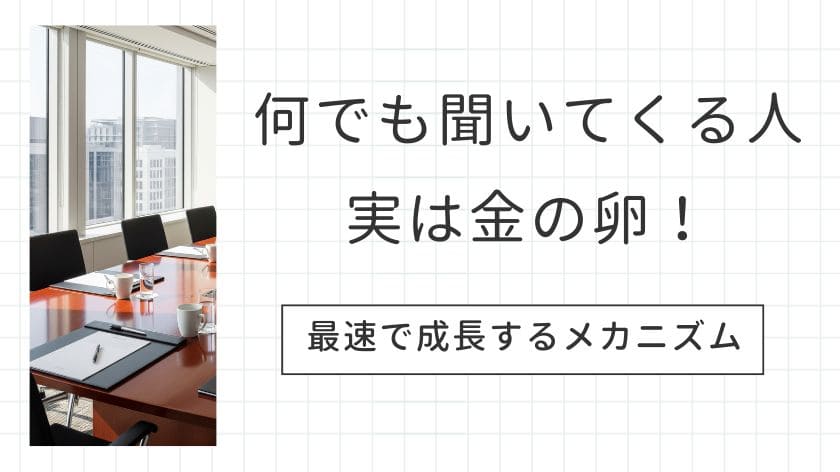あなたの職場に、何でも聞いてくる人はいませんか?
「少しは自分で考えてほしい」と感じ、うざいとか、疲れると思ってしまうこともあるでしょう。
すぐ人に聞く人や、いちいち確認してくる人の心理を勘ぐり、その人の末路を案じてしまうかもしれません。
しかし、「まずググれ」という風潮は、本当に正しいのでしょうか。
実は、質問こそが成長の最短ルートであり、教えることは人材を育てる上での重要な役割なのです。
わからないものはいくら考えてもわかるわけがないし、考えた結果が間違っていたら、お互いに損でしかないです。
この記事では、一般的にネガティブに捉えられがちな「質問する行為」の本当の価値や意味を解説します。
最後まで読んでもらえれば、わからないものは聞いたほうが、お互いにお得だということがおわかりになるはずです。
- 「何でも聞いてくる人」に対するよくある誤解
- 彼らが驚異的なスピードで成長する本当の理由
- 「まずググれ」が人材育成を阻害するワケ
- 部下や後輩の才能を伸ばす正しい関わり方
「何でも聞いてくる人」はうざい?その本当の心理
- うざい、疲れると感じる聞かれる側の心理
- すぐ人に聞く人の心理は「わからないものはわからない」
- 質問は成長を加速させる「タイムマシン」である
- いちいち確認してくる人の心理と背景
- 「まずググれ」と言いたくなる気持ちと弊害
- 「まずググれ」が組織を破壊する?教育放棄がもたらす大きな代償
- 人を育てるには考えさせてはダメ?
- アドラー心理学における「共同体感覚」
うざい、疲れると感じる聞かれる側の心理
「すみません、これってどういう意味ですか?」
「この次は何をすればいいですか?」
次から次へと飛んでくる質問に、思わず「またか…」とため息をつき、うざい、疲れると感じてしまう。
その気持ちは、非常によく分かります。
これは、質問に答える側の人間として、ごく自然な心理的反応です。
なぜなら、他者からの質問は、自分の集中を中断させ、思考のリソースを奪う行為だからです。
あなたが自分の業務に深く集中している時、外部から割り込まれるわけです。
集中状態が一時途切れ、再び元の状態に戻るまでに多大な精神的エネルギーを要求します。
これが、疲労感の直接的な原因です。
また、「こんなことも知らないのか」「少しは自分で調べてほしい」という気持ちは、相手の未熟さや依存心に対する苛立ちから来ています。
特に、自分で調べればすぐに分かりそうなことを聞かれると、「相手は思考を放棄して、自分に責任と労力を押し付けているのではないか」と感じ、不公平感を覚えてしまうのです。
しかし、これは「聞かれる側の心理」です。
質問する側は、誰でもすぐに分かる質問なのか、どこを調べればわかるのかわからないので、聞いてくるんです。
そもそも、一番初めは、誰もがそんな感じだったんじゃないでしょうか。
すぐ人に聞く人の心理は「わからないものはわからない」
すぐ人に聞く人の行動を、「思考停止」や「依存心」と捉えるのは、実は大きな誤解です。
彼らの心理の根底にあるのは、極めてシンプルで、しかし多くの人が見過ごしがちな一つの真実です。
それは、「わからないものは、考えてもわからない」ということです。
経験豊富な私たちは、過去の知識や経験の引き出しから、類推したり、検索キーワードを工夫したりして、未知の問題に対する答えの糸口を見つけることができます。
しかし、初心者はその「引き出し」自体を持っていません。
知識の前提がゼロの状態では、どれだけ一生懸命に考えようとしても、思考は空回りするだけで、答えにはたどり着けないのです。
彼らがすぐに質問するのは、怠慢なのではありません。
むしろ、自分の「わからない」という現状を素直に認め、最短時間でそのギャップを埋めようとする、極めて合理的で、成長意欲の高い行動なのです。
質問は成長を加速させる「タイムマシン」である
「何でも聞いてくる人」が持つ最大の強みは、時間の使い方に対する、極めて合理的な感覚です。
「何でも聞いてくる人」は、悩んでもわからないと想うし、その悩んでる時間がとてももったいないと無意識に感じてるんです。
つまり、「一人で30分間、暗闇で悩み続けるよりも、既に光を見つけた専門家に1分で道を尋ね、残りの29分でその道を走り出す方が遥かに生産的である」という、本質的な真理に気づいているんです。
初心者が一人で悩む時間は、脳に過剰な「認知的負荷(Cognitive Load)」をかけ、思考を空回りさせるだけで、解決策を生みません。
これは、地図を持たずに広大な森をさまようようなもので、多大なエネルギーを消耗するだけです。
しかし、専門家へのたった1分の質問は、相手が長年かけて蓄積した経験や知識を「レバレッジ(Leverage)」として活用する行為に他なりません。
これは、心理学者ヴィゴツキーが提唱した「最近接発達領域(ZPD)」の考え方そのものです。
他者の助けを借りて、独力では到達できない一歩先のレベルへとジャンプする、最も効率的な学習法なのです。
節約できた29分という時間は、単なる時間の節約ではありません。
それは、次の学びや実践に再投資できる、貴重な資源となります。
質問は、依存や思考停止ではなく、時間を無駄にしないための、最も賢明で戦略的な選択なのです。
いちいち確認してくる人の心理と背景
「この手順で合っていますか?」「このまま進めて大丈夫でしょうか?」と、いちいち確認してくる人。
その行動は、一見すると自信のなさの表れに見え、聞かれる側を苛立たせるかもしれません。
しかし、その心理と背景を深く探ると、そこには「失敗を回避したい」という、強い責任感と誠実さが見えてきます。
自分の判断で勝手に仕事を進め、もしそれが間違っていた場合に、チームや組織に迷惑をかけることを極度に恐れています。
なので、確認作業は、単なる不安の解消ではありません。
起こりうるリスクを最小限に抑え、仕事の質を担保するための、プロフェッショナルとして当然のプロセスなのです。
特に、過去に自分の判断で失敗し、手痛い経験をしたことがある人は、この傾向が強くなります。
「あの時、ちゃんと確認しておけば…」という後悔が、彼らを慎重にさせているのです。
確かに、過度な確認は業務のスピードを落とすかもしれません。
しかし、それは「独断で進めて大きな手戻りを発生させる」という、最悪の事態を回避するための、賢明なリスク管理とも言えるのです。
彼らの質問を「依存」と捉えるのではなく、「品質へのこだわり」や「責任感の表れ」と捉え直すことで、あなたの彼らに対する見方は大きく変わるはずです。
「まずググれ」と言いたくなる気持ちと弊害
「そんなこと、聞く前にまず自分でググれよ」
よく聞きますが、効率を重視する現代において、多くの人が共有する感覚でしょう。
しかし、この一見すると正論に聞こえる「まずググれ」という突き放しこそが、実は部下や後輩の成長を著しく阻害する大きな弊害を孕んでいます。
なぜなら、初心者が直面している問題の多くは、そもそも「何というキーワードで検索すれば良いか分からない」というレベルにあるからです。
業界特有の専門用語や、問題の根本原因を特定するための適切な語彙を知らなければ、検索すらできないんです。
経験者であれば5秒で終わる検索が、初心者にとっては30分以上かかることも珍しくありません。
そして、やっと見つけた情報が、本当に正しいのか、自分の状況に当てはまるのかを判断することも、彼らにとっては至難の業です。
「まずググれ」が組織を破壊する?教育放棄がもたらす大きな代償
「聞く前にまず自分で調べなさい」という指導は、一見すると部下や後輩の自立心を育む、もっともらしい正論に聞こえます。
しかし、その実態は、組織全体の生産性を著しく低下させる、極めて非効率な「教育の放棄」に他なりません。
なぜなら、初心者は問題解決に必要な専門用語や背景知識の体系、いわゆる「スキーマ」が欠けています。
そもそも「何という言葉で検索すれば正解に辿り着くか」さえ分からないからです。
経験者が「その件は〇〇の公式ドキュメントを見て」と10秒のヒントを与えるだけで、後輩が闇雲な検索と誤情報の判別に費やす30分という貴重な時間を節約できます。
組織全体で見た時、この29分50秒の差がもたらす生産性の違いは明白です。
この10秒の「ナレッジトランスファー(知識移転)」を惜しむ態度は、「無知は罪であり、質問することは無能の証である」という強力な信仰に基づいています。
そのたった10秒のために、チームの「心理的安全性」を根底から破壊します。
質問を恐れるようになったメンバーは、小さな疑問や違和感を報告せずに抱え込み、やがてそれは手遅れの大きなミスへと発展するのです。
そういう意味では、傲慢さや心の狭さ、自己中の極みだと言っても過言ではないです。
「まずググれ」という言葉は、本来チームで負担すべきコミュニケーションコストと教育コストを、組織で最も経験の浅い個人に一方的に転嫁する行為です。
それはチーム全体の成長機会を奪い、長期的には組織の活力を削ぐ、非常に危険な言葉だと認識する必要があります。
人を育てるには考えさせてはダメ?
「すぐに答えを教えるのは、本人のためにならない。自分で考えさせることが、人を育てる上で重要だ」
そういう考え方は、教育論の王道として、長らく信じられてきました。
しかし、この考え方は、場合によっては「考えさせてはダメ」、むしろ有害であるという、逆説的な真実を見過ごしています。
それは、知識や情報という「考えるための材料」が全くない状態で、初心者に「考えろ」と要求するケースです。
これは、料理の仕方を知らない人に、食材だけを渡して「美味しい料理を作れ」と言っているようなものです。
彼は途方に暮れるだけで、何も生み出すことはできません。
人を育てる上で本当に重要なのは、「考えさせる」ことと「教える」ことの順番です。
- まず、必要な知識や手順を、明確に、そして惜しみなく「教える」。
- その知識を使って、実際に一度やらせてみる。
- その上で、「このプロセスを、もっと効率的にするにはどうすればいいと思う?」と、応用や改善について「考えさせる」。
この順番が不可欠です。
基礎知識という土台がないまま「考えろ」と突き放すのは、教育ではなく、ただの思考の丸投げです。
それは相手の自信を奪い、「考えることは苦痛なことだ」というネガティブな刷り込みを与えてしまう、最悪の育成法と言えるでしょう。
まずはこちらが徹底的に「与える」。
そして、その与えられた武器の使い方を、本人に工夫させる。
この順番を間違えないことが、人を育てる上での要なのです。
アドラー心理学における「共同体感覚」
「何でも聞いてくる人」に対して、なぜ私たちは面倒くさがらずに応えるべきなのか。
その哲学的な答えの一つを、アドラー心理学が示してくれます。それは、「共同体感覚」という、アドラー心理学の最終目標とも言える重要な概念です。
共同体感覚とは、「自分は、この共同体(家族、職場、地域社会など)に所属しており、その一員として貢献できている」という感覚のことです。
そして、アドラーは、他者に関心を持ち、仲間として信頼し、貢献することこそが、人間の幸福の根源であると説きました。(参考:日本アドラー心理学会)
この視点から、後輩からの質問に答えるという行為を捉え直してみましょう。
質問は、あなたの時間を奪う「邪魔」な行為ではありません。
むしろ、あなたが持つ知識や経験というリソースを使って、共同体(=職場)の仲間(=後輩)に「貢献」する、絶好の機会なのです。
後輩があなたの助けによって成長し、チームの一員としてより良く機能するようになることは、巡り巡って、あなた自身の働きやすさや、チーム全体の成果へと繋がっていきます。
「後輩の成長は、私自身の課題でもある」と、問題を「共同の課題」として捉えること。
この共同体感覚を持つことで、後輩からの質問は「面倒な割り込み」から、「チームを強くするための、価値ある投資」へと、その意味を大きく変えるのです。
教えることは、後輩のためだけでなく、あなた自身の幸福と貢献感をも満たす、尊い行為なのです。
なぜ「何でも聞いてくる人」は爆速で成長するのか
- よく質問する人の方が圧倒的に成長する理由
- 将来的にすごいスピードで成長する
- 職場ではすぐに教えるのが当たり前という考え
- 質問は最強のインプット兼アウトプット法
- 知識の蓄積が思考力を生む
- まとめ:何でも聞いてくる人の本質
よく質問する人の方が圧倒的に成長する理由
よく質問する人の方が、一人で黙々と悩む人よりも、圧倒的に成長するのはなぜでしょうか。
その理由は、彼らが無意識のうちに、学習効率を最大化するための、極めて合理的なサイクルを回しているからです。
第一に、フィードバックの速度と頻度が圧倒的に高い点です。
一人で悩む場合、自分の考えが正しいかどうかが分かるのは、最終的な成果物への評価が下される時だけです。
一方で、質問する人は、疑問が生じたその瞬間に、専門家(先輩)から即座にフィードバックを得ることができます。
この短いフィードバックループを何度も繰り返すことで、間違いを早期に修正し、常に正しい方向に努力を続けることができるのです。
第二に、他者の知識や経験という「巨人の肩に乗る」ことができるからです。
あなたが10年かけて築き上げた知識やノウハウを、後輩はたった5分の質問で学ぶことができます。
これは、一人で学ぶことに比べて、圧倒的な時間短縮です。
彼らは、他者の知恵をレバレッジとして活用し、驚異的なスピードで成長の階段を駆け上がっていきます。
質問がもたらす学習効果
教育心理学の研究では、単に情報を受け取る受動的な学習よりも、自分で問いを立てたり(質問)、学んだことを思い出したりする(想起)能動的な学習の方が、記憶の定着率が格段に高いことが示されています。
質問する行為は、まさにこの能動的な学習プロセスそのものなのです。(参考:Strengthening the Student Toolbox)
これらの理由から、質問することを恐れない姿勢こそが、成長速度を決定づける最も重要な要素であると言えるのです。
将来的にすごいスピードで成長する
では、「何でも聞いてくる人」の気になる将来、つまり、その行動を続けた先に何が待っているのでしょうか。
一部の人が想像するような、「いつまでも自立できない、指示待ち人間になる」という未来ではありません。
むしろ、その正反対の、驚くべきスピードで成長を遂げ、いずれは教える側に回るという輝かしい未来が待っているのです。
最初は些細なことばかり聞いていた新人や後輩も、質問と実践を繰り返すうちに、知識の点と点がつながり、やがて線となり、そして面となっていきます。
彼らは、成功体験と失敗体験の両方を、高頻度のフィードバックを通じて高速で蓄積していきます。
その結果、わずか1年後には、一人で悩んでいた同期とは比べ物にならないほどの、実践的な問題解決能力と、体系的な知識を身につけているでしょう。
そして、彼らが一人前の専門家となった時、今度は自分自身が、かつての自分と同じように、何でも聞いてくる新しい後輩に対して、快く、そして的確に教える側に回るのです。
なぜなら彼らは、「質問することの価値」と「教えてもらえることのありがたさ」を、誰よりも深く理解しているからです。
質問することを恐れない文化は、こうして次世代へと受け継がれ、組織全体を成長させる、強力なエンジンとなります。
「何でも聞いてくる人」の末路は、個人の成功に留まらず、組織全体の知的レベルを底上げする、非常にポジティブなものなのです。
職場ではすぐに教えるのが当たり前という考え
プロフェッショナルが集う職場においては、質問されたことに対しては、知っている人間が「すぐに教えるのが当たり前」という考え方を持つことが、組織全体の利益に繋がります。
これは、単なる優しさや親切心の問題ではなく、極めて合理的な生産性の問題です。
組織の目的は、チームとして最大の成果を出すことです。
一人の初心者が30分間悩み、その間タスクが停滞することは、チーム全体の損失に他なりません。
その問題を、経験者が1分で解決できるのであれば、そうしない理由はありません。
その1分は「時間の浪費」ではなく、チームの損失を29分間も食い止める、
極めて投資対効果の高い「時間の使い方」なのです。
「自分で調べさせる」という自己満足的な教育方針は、学生時代の部活動までにしておくべきです。
成果と効率が求められる職場においては、知識は独占するものではなく、可能な限り迅速に共有し、組織全体の力に変えるべき資産です。
その共有を円滑に行う文化こそが、強い組織を作り上げるのです。
質問は最強のインプット兼アウトプット法
「何でも聞いてくる」という行為がなぜこれほどまでに成長を加速させるのか?
その秘密は、質問がインプット(入力)とアウトプット(出力)を同時に、かつ極めて効率的に行う、最強の学習法であるという点にあります。
一般的に、学習は「本を読む」「講義を聞く」といったインプットから始まります。
しかし、インプットだけでは、知識は頭に入っただけで、本当に理解し、使えるようになったとは言えません。
知識を自分のものにするためには、それを使う「アウトプット」のプロセスが不可欠です。
そして、「質問する」という行為は、この二つを同時に実現します。
- アウトプットのプロセス
質問をするためには、まず「自分が何を分かっていて、何を分かっていないのか」を、自分の中で整理し、それを言語化する必要があります。この「分からないことを、言葉にして相手に伝える」という行為自体が、非常に高度なアウトプットなのです。 - インプットのプロセス
そして、その質問に対して、専門家(先輩)から返ってくる答えは、自分が今まさに必要としている、最も的確で、無駄のない、質の高い情報です。これは、本やインターネットで手当たり次第に情報を探すよりも、遥かに効率的なインプットと言えます。
つまり、質問一回には、「自己分析」「言語化」「課題設定」というアウトプットと、「最適な情報の獲得」というインプットが、凝縮されているのです。
これほど効率的な学習法は、他にはなかなかありません。
「何でも聞いてくる人」は、この最強の学習サイクルを、無意識のうちに、そして凄まじい回数で回し続けています。
彼らが驚異的なスピードで成長するのは、科学的に見ても、至極当然のことなのです。
知識の蓄積が思考力を生む
「自分で考えさせないと、思考力が育たない」という意見があります。
これは一見すると正しいように聞こえますが、重要な前提が抜け落ちています。
それは、そもそも「思考力」とは、ゼロからは生まれないということです。
真の思考力、特に創造的な問題解決能力は、土台となる膨大な「知識の蓄積」があって初めて、その力を発揮するのです。
将棋の名人が、数手先まで読み、最善の一手を導き出せるのは、彼らの頭の中に、過去の膨大な棋譜(知識)がデータベースとして蓄積されているからです。
優れた経営者が、複雑な市場の変化に対応できるのは、経済、歴史、心理学といった、幅広い分野の知識を統合して物事を判断しているからです。
思考とは、頭の中にある既存の知識と知識を、新しく結びつける作業です。
結びつけるべき知識の絶対量が少なければ、生まれてくるアイデアの数も、その質も、おのずと貧弱なものになります。
この観点から見ると、「何でも聞いてくる人」の行動は、極めて理にかなっています。
彼らは、質問という最も効率的な手段を用いて、思考の土台となる「知識」を、凄まじいスピードで蓄積しているのです。
今はまだ、一つひとつの知識を応用する段階に至っていないかもしれません。
しかし、その知識の蓄積が一定の臨界点を超えた時、それらは脳内で爆発的な化学反応を起こし、誰にも真似できない、独自の「思考力」として開花するのです。
知識なき思考は、空虚です。質問によって知識の土台を固めることこそが、真の思考力を育むための、最も確実な道筋なのです。
まとめ:何でも聞いてくる人の本質
この記事では、「何でも聞いてくる人」に対する従来のネガティブな見方を覆し、彼らの行動がいかに成長に繋がるか、そして私たちがどう向き合うべきかについて解説してきました。
「何でも聞いてくる人」は、未来のエース候補です。彼らの質問を、面倒な割り込みではなく、才能の芽を育てる貴重な機会と捉え直すこと。
その視点の転換が、あなた自身を、そしてあなたの職場を、より成長させるきっかけとなるはずです。
最後に、その要点をまとめます。
- 「何でも聞いてくる人」がうざい、疲れると感じるのは自然な心理
- しかし、すぐ聞く心理は「成長意欲」の表れである
- わからないことは考えてもわからないため、聞くのが最も効率的
- いちいち確認するのは、失敗を避けたいという責任感の高さから
- 「まずググれ」は、初心者の時間を奪い成長を阻害する悪手
- 人を育てるには、まず教え、その上で応用を考えさせることが重要
- よく質問する人は、フィードバックの回数が多く、圧倒的に成長する
- 彼らの末路は、いずれ教える側に回るというポジティブなもの
- 質問は、自己分析(アウトプット)と情報収集(インプット)を同時に行う最強の学習法
- 思考力は、知識の蓄積という土台があって初めて生まれる
- 質問を歓迎する文化が、組織全体の知的レベルを向上させる
- 聞かれる側のあなたの役割は、後輩の成長を支援する教育者である
- 面倒くさがらずに教えることが、未来への最も賢明な投資
- あなたの10秒が、後輩の30分を、そして会社の未来を創る