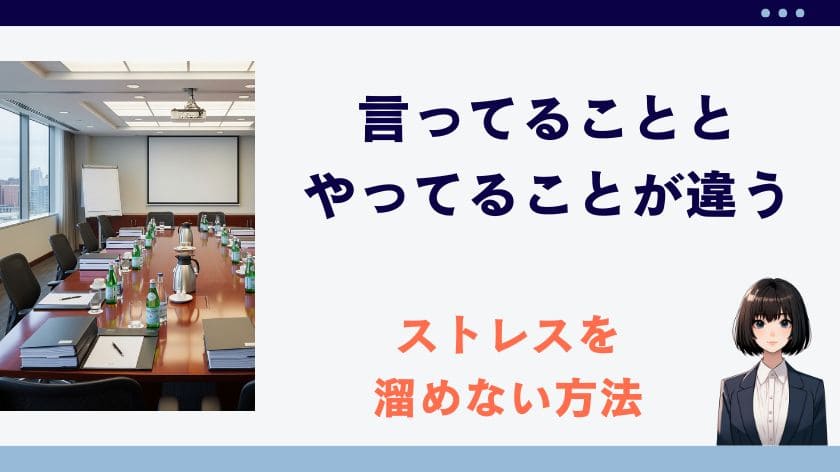「残業するな」
「何でも相談してくれ」
「挑戦しろ」
そう言われたのに、真逆のことを言ってくる上司や会社に、ストレスや不信感を抱えていますよね。
この問題は、単に一個人の性格だけでなく、男性と女性の思考の違いや、会社全体の構造的な課題が絡んでいることも少なくありません。
また、仕事を進める上で、人によって言うことが違う、あるいは人によってやり方が違う状況も、混乱を招き、モチベーションの低下に直結します。
なぜあの人は行動が伴ってないのか、その背景にある心理や理由を理解しなければ、有効な対策は打てません。
この記事では、言動不一致が起こる根本原因を多角的に分析し、明日から実践できる具体的な対処法を詳しく解説します。
- 言動が一致しない人の心理や根本的な理由がわかる
- 上司や同僚など関係性別の具体的な対処法がわかる
- 職場のストレスを減らし自分の心を守る方法がわかる
- 改善しない場合の最終的な選択肢までわかる
なぜ?言ってることとやってることが違う職場の心理
- 言動が一致しない心理的な理由
- なぜあの人は行動が伴ってないのか
- 結果を重視しがちな男性の傾向
- プロセスを気にする女性の傾向
- 会社の方針そのものが矛盾している
- 「ダブルバインド」が引き起こす混乱
- 言行不一致がまかり通る組織の特徴
言動が一致しない心理的な理由
職場で「言ってること」と「やってること」が違う人がいる根本的な理由は、人間の「思考」と「感情」が分離していることにあります。
これは特定の誰かが悪いというより、多くの人が無意識に抱える心の仕組みです。
「言ってること」は、多くの場合、論理や理性に基づいた「こうあるべきだ」という思考から生まれます。
「約束は守るべきだ」「目標は達成すべきだ」といった社会的な正しさや建前がこれにあたります。
一方で、「やってること(行動)」は、好き嫌いや快・不快といった感情(本音)に大きく影響されます。
「面倒くさい」「やりたくない」「自信がない」といった感情が行動を鈍らせるのです。
自立した大人であればあるほど、この思考と感情の分離は起こりやすくなります。
そのため、本心では自信がなかったり、乗り気でなかったりしても、頭では「やります」と答えてしまい、結果として言動の不一致が生まれるのです。
なぜあの人は行動が伴ってないのか
前述の「思考と感情の分離」に加え、行動が伴わない人にはいくつかの共通した心理が働いていることがあります。
その場しのぎで答えている
相手を納得させたい、その場の空気を悪くしたくないという気持ちから、深く考えずに「はい、やります」「大丈夫です」と返事をしてしまうタイプです。
後でどうするかという見通しが甘く、結果的に約束を果たせなくなります。
承認欲求が強く、自分を大きく見せたい
「できる自分」をアピールしたいという気持ちが強く、自分の能力以上のことを安請け合いしてしまう傾向があります。
プライドが高く、できないことを認めたくないため、口先だけで終わってしまうのです。
想像力が不足している
自分の言葉が相手にどのような影響を与え、どのような責任が発生するかを具体的に想像できていないケースです。
自分の発言の重みを理解していないため、安易な言動を繰り返してしまいます。
結果を重視しがちな男性の傾向
言動の不一致には、男女の思考パターンの違いが影響していることもあります。
もちろん個人差はありますが、一般的に男性性(男性的な思考)は「結果主義」であると言われます。
これは、「最終的に良い結果が出れば、途中の細かいことや多少の嘘は問題ない」と考える傾向です。
例えば、「このプロジェクトを成功させる」という大きな目標があれば、そのための小さな約束や発言のブレはあまり重要視しないことがあります。
そのため、目的達成のために発言を変えたり、以前の言葉を忘れているかのような行動を取ったりしても、本人に悪気がないケースも少なくありません。
言葉そのものよりも、目指すゴールや結果に意識が向いているのが特徴です。
プロセスを気にする女性の傾向
一方で、女性性(女性的な思考)は「プロセス思考」が強いとされています。
これは、結果だけでなく、そこに至るまでの過程やコミュニケーション、気持ちの共有を非常に大切にする考え方です。
そのため、「言ったこと」と「やっていること」が一致しているかどうかは、信頼関係を築く上で非常に重要な要素となります。
発言の不一致は、約束を軽んじられている、信用されていないと感じ、深く傷つく原因になります。
女性が多い職場で言動の不一致が問題になりやすいのは、この「言葉」や「約束」を信頼の基盤と捉えるプロセス重視の価値観が背景にあると言えるでしょう。
会社の方針そのものが矛盾している
個人の問題だけでなく、会社や組織全体が矛盾したメッセージを発しているケースも少なくありません。
これは、社員に強いストレスを与える大きな要因となります。
例えば、経営層は朝礼で「失敗を恐れずどんどん挑戦しよう!」と高らかに宣言する一方で、現場のマネージャーは「絶対にミスをするな」「予算をオーバーするな」と減点主義の管理を徹底している、といった状況です。
他にも、「風通しの良い組織を目指す」と言いながら、実際には意見を言うと睨まれたり、評価が下がったりする文化が根付いていることもあります。
このように、掲げられている理想と現場の実態がかけ離れていると、社員は何を信じて行動すれば良いのか分からなくなり、組織全体が「言ってることとやってることが違う」状態に陥ります。
「ダブルバインド」が引き起こす混乱
前述のように、相反する二つのメッセージを同時に受け取り、どちらに従っても罰せられるような状況に置かれることを、心理学用語で「ダブルバインド(二重束縛)」と呼びます。
例えば、「何かわからないことがあれば、すぐに相談して」と言う上司に相談に行くと、「そのくらい自分で考えろ」と突き返されるケースが典型例です。
相談しても怒られ、相談しなくても「なぜ報告しないんだ」と怒られる。
このような状況では、部下は身動きが取れなくなってしまいます。
ダブルバインドは、受け手に対して以下のような深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。
- 強い精神的ストレスやメンタル不調
- 自信や自主性の喪失
- 指示待ちの姿勢や思考停止
- 組織全体のパフォーマンス低下
言動の不一致は、単なる「困った人の問題」ではなく、社員のやる気を削ぎ、組織を蝕む危険性をはらんでいるのです。
言行不一致がまかり通る組織の特徴
特定の個人の問題ではなく、職場で言行不一致が常態化している場合、その組織の文化や体制に問題が潜んでいる可能性が高いです。
言行不一致が起こりやすい組織の3つの特徴
- コミュニケーションが不足している
部門間の連携が悪く、情報共有がなされていない組織では、各部署や担当者がバラバラの方針で動いてしまいます。結果として、顧客や他部署に対して矛盾した対応が生まれます。 - 責任の所在が曖昧
「誰が最終的な決定権者なのか」が不明確な組織では、その場しのぎの発言や無責任な約束が横行しがちです。問題が起きても誰も責任を取らないため、同じ過ちが繰り返されます。 - 評価制度が機能していない
言ったことを実行する人が正当に評価されず、口先だけの人が評価されるような環境では、真面目にやる気を出す人はいなくなります。結果として、組織全体で言行不一致がまかり通るようになります。
もしあなたの職場がこれらの特徴に当てはまるなら、それは個人の努力だけで解決するのが難しい、根深い問題を抱えているサインかもしれません。
言ってることとやってることが違う職場での対処法
- 上司の言動が違う場合の対応策
- 同僚や部下の場合はどう接するべきか
- 仕事で人によって言うことが違う場合
- 人によってやり方が違う時の進め方
- ストレスを溜めないための基本対処法
- 指摘せずに自覚を促す質問アプローチ
- 自分の評価とメンタルを守る心構え
- 改善が見込めないなら転職も視野に
- まとめ:言ってることとやってることが違う職場との向き合い方
上司の言動が違う場合の対応策
仕事の指示を出す上司の言動が一致しない場合、業務への影響は深刻です。
感情的にならず、自分の身を守るための対策を冷静に実行しましょう。
指示は必ず「記録」に残す
最も重要な自己防衛策です。
口頭での指示を受けた場合は、必ず
と伝え、テキストとして証拠を残しましょう。
これにより、「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぐことができます。
「確認ですが」と質問形式で切り返す
以前の指示と違うことを言われた際は、
と、あくまで確認という形で質問します。相手を責めるのではなく、事実確認に徹することで、角を立てずに矛盾を認識させることができます。
期待値をコントロールする
残念ながら、言動が一致しない上司は簡単には変わりません。
「この人はこういう人だ」とある程度割り切り、過度な期待を持たないことも心の平穏を保つためには必要です。
重要なのは、振り回されずに自分の業務を淡々と遂行することです。
同僚や部下の場合はどう接するべきか
同僚や部下の言動不一致も、チームの生産性を下げる要因になります。
相手の立場に応じて、接し方を変えるのがポイントです。
同僚の場合:深入りせず、客観的な事実で関わる
同僚の言動不一致に対して、あなたが責任を負う必要はありません。
愚痴に同調したり、代わりに仕事を引き受けたりすると、都合よく利用される可能性があります。
協力すべき業務については、いつまでに何をやるのかを明確にし、タスク管理ツールなどで進捗を可視化すると良いでしょう。
プライベートでは距離を置くのが賢明です。
部下の場合:具体的な行動を促し、仕組みで管理する
部下の「やります」という言葉を鵜呑みにせず、具体的な行動計画に落とし込ませることが重要です。
「具体的に、いつから、どのように進める?」と問いかけ、定期的な進捗報告を義務付けるなど、仕組みで管理しましょう。
行動が伴わない場合は、なぜできないのかを一緒に考え、サポートする姿勢を見せることで、信頼関係を築きながら改善を促せます。
仕事で人によって言うことが違う場合
複数の上司や担当者から矛盾した指示を受け、板挟みになるのは非常につらい状況です。
混乱したまま作業を進めると、最終的にあなたの責任問題になりかねません。
このような状況では、「誰の指示が最終決定なのか」を明確にすることが最優先です。
可能であれば、指示を出した関係者全員を集めた場で、
と、方針の統一を依頼するのが最も確実です。
もし直接対話を依頼しにくい場合は、メールのCCに関係者全員を入れ、テキストで確認を取りましょう。
自分の判断でどちらかの指示を優先するのではなく、必ず責任者に判断を委ねることが、あなた自身を守ることに繋がります。
人によってやり方が違う時の進め方
同じ業務なのに、教える人によってやり方がバラバラで、新しく入った人が混乱してしまう…というのも、よくある問題です。
これは業務の属人化を招き、品質の低下や非効率の原因となります。
この問題への対処法として有効なのが、業務マニュアルや手順書の作成を提案することです。
と、組織全体のメリットを提示して提案すると、受け入れられやすくなります。
作成にあたっては、関係者それぞれのやり方を聞き取り、最も効率的で間違いの少ない方法を「標準のやり方」としてまとめます。
これにより、業務の基準が明確になり、「あの人はこう言っていた」という混乱を減らすことができます。
ストレスを溜めないための基本対処法
言ってることとやってることが違う人に振り回され続けると、心は疲弊してしまいます。
自分のメンタルを守るための基本的な心構えは、「相手に期待しない」そして「課題を分離する」ことです。
「課題の分離」とは、心理学者アドラーが提唱した考え方で、これは誰の課題なのかを冷静に見極めることを指します。
言動が一致しないのは、あくまで「相手の課題」であり、あなたがコントロールできる問題ではありません。
そのことであなたが悩み、ストレスを感じるのは「あなたの課題」です。
相手を変えようとエネルギーを注ぐのではなく、「相手の課題」には介入せず、自分の課題である「どうすれば自分がストレスなく仕事ができるか」に集中することが大切です。
「あの人はそういう人だから」と割り切り、感情的に振り回されないように心の境界線を引く意識を持ちましょう。
指摘せずに自覚を促す質問アプローチ
相手の矛盾を真正面から「言ってることとやってることが違いますよ!」と指摘すると、相手は自己防衛に走り、関係が悪化するだけです。
相手を追い詰めず、自ら矛盾に気づかせるような、質問ベースのアプローチが有効です。
相手を傷つけずに気づきを促す4ステップ
- 評価基準を相手に語らせる
「確か以前、〇〇については、〜が大事だとおっしゃってましたよね?」と、相手が過去に言った「あるべき姿(建前)」を再確認します。 - ズレた行動を穏やかに提示する
「それで思ったのですが、今回の件は少しその方針と違うように見えるのですが、いかがでしょうか?」と、あくまで疑問形で、行動とのズレを優しく問いかけます。 - 客観的な視点を促す
「もし、他の部署が同じようなことをしていたら、私たちはどう感じるでしょうか?」と、第三者の視点を持ち出すことで、自分を客観視させます。 - 自分の感情を伝える(Iメッセージ)
「方針が分からなくなってしまって、少し悲しかったです」のように、「あなた」を主語にするのではなく、「私」を主語にして自分の気持ちを伝えることで、相手は非難されたと感じにくくなります。
この方法は高度なコミュニケーションスキルを要しますが、相手との関係性を壊さずに行動変容を促したい場合に非常に有効です。
自分の評価とメンタルを守る心構え
矛盾の多い職場で健全に働き続けるためには、他人の言動に振り回されず、自分軸をしっかり持つことが不可欠です。
自分の評価とメンタル、この二つを意識的に守っていきましょう。
事実と感情を切り分ける
「上司が指示を変えた(事実)」ことと、「私は軽く見られているのではないか(感情)」ということは全く別の問題です。
事実だけを冷静に受け止め、ネガティブな感情と結びつけない練習をしましょう。
仕事の記録と成果を整理しておく
自分の業務内容、指示系統、そして出した成果を、いつでも説明できるように整理しておきましょう。
これは、理不尽な評価から自分を守るための重要な武器になります。客観的な事実が、あなたの正当性を証明してくれます。
職場以外に心の拠り所を持つ
仕事のストレスを職場だけで解決しようとすると、視野が狭くなりがちです。
趣味、家族、友人など、仕事とは全く関係のない世界に没頭する時間を作りましょう。
心の拠り所が複数あることで、職場の問題が自分の全てであるかのように感じるのを防げます。
改善が見込めないなら転職も視野に
これまで様々な対処法を紹介してきましたが、問題が個人の資質ではなく、組織全体の文化や体質に根ざしている場合、個人の努力だけでは改善が困難なケースも少なくありません。
言行不一致が常態化し、誠実な人が損をするような職場で我慢し続けることは、あなたの貴重な時間とキャリア、そして心身の健康を蝕むだけです。
もし、以下のような状況であれば、環境を変えること、つまり転職も真剣に検討すべきです。
- 上司や会社に相談しても、全く改善の兆しが見えない。
- ストレスで心身に不調(不眠、食欲不振など)が出始めた。
- 会社の将来性や自分のキャリアに希望が持てない。
転職は決して逃げではありません。
あなた自身の価値を正当に評価し、心身ともに健康に働ける環境を求める、前向きなキャリア戦略です。
転職活動を始めるだけでも、自分の市場価値を客観的に知ることができ、視野が広がるきっかけになります。
言ってることとやってることが違う職場との向き合い方
この記事では、「言ってることとやってることが違う職場」で生き抜くための原因分析と具体的な対処法を解説してきました。
最後に、この理不尽なストレスと上手に付き合っていくための要点をまとめます。
- 言動不一致の根本原因は「思考」と「感情」の分離にある
- 行動が伴わないのはその場しのぎや承認欲求が原因の場合がある
- 会社自体の方針が矛盾している「ダブルバインド」も存在する
- 上司の指示は必ずメールなどで記録に残し自己防衛する
- 部下には具体的な行動計画を立てさせ仕組みで管理する
- 人によって言うことが違う場合は責任者に判断を委ねる
- 業務のやり方が違うならマニュアル化を提案する
- 基本は「相手に期待しない」と割り切ることが心の平穏に繋がる
- 相手の課題と自分の課題を切り離して考える
- 正面から指摘せず質問形式で相手の自覚を促す
- 仕事の記録と成果を整理し自分の評価を守る
- 職場以外に心の拠り所を持ちストレスを溜めない
- 組織文化に問題がある場合は個人の努力には限界がある
- 心身に不調をきたす前に環境を変える「転職」も重要な選択肢
- あなた自身の心とキャリアを守ることを最優先に行動する